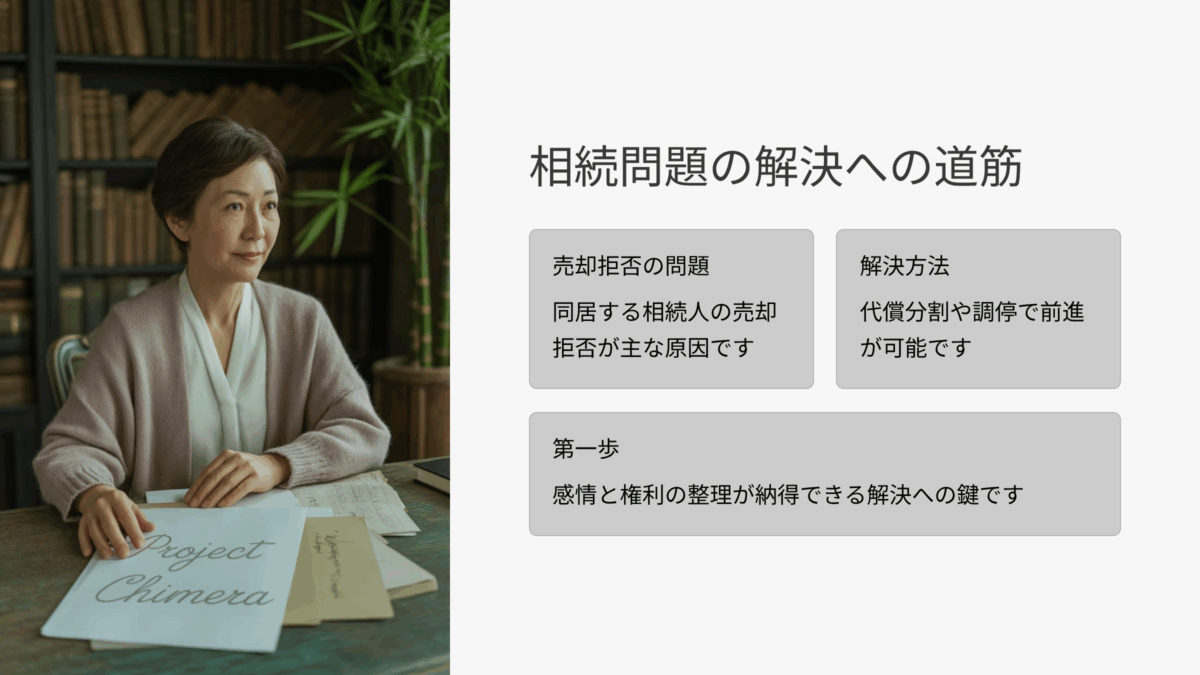実家を相続したけれど、次男が住み続けて売却できず話し合いも進まない…。そんなお悩みに、現場の視点から解決策を整理しました。目次を見て必要なところから読んでみてください。
実家に住む次男が売却に応じないと相続はどうなる?【よくあるトラブルの全体像】
「実家の相続、そろそろ話し合わなきゃ…」そう思いながらも、いざ進めようとすると、同居している家族の反対で止まってしまう。
そんなご相談を、私たち“めーぷる岡山中央店”でもよくお受けします。
とくに多いのが、「次男が実家に住んでいて、売るにも分けるにも話がまとまらない」というケース。
ここでは、そうした状況でなぜ相続が進まないのか、どんな壁があるのかを、整理してお伝えしますね。
相続が進まない典型パターン:住み続ける相続人の存在
「兄弟は実家を売りたい。でも住んでいる弟は出たくない」
このようなケース、実はとても多いんです。
問題は、住み続けている人が“不動産に強い権利を持っている”ように見えて、そうとは限らないこと。
法的には、遺産分割が終わるまでは全員が“共有の相続人”です。誰かひとりが勝手に住み続けたり、売却を拒んだりできる立場ではありません。
とはいえ、実際には「今そこに住んでいる」という事実が強く働きます。感情のもつれや、親との関係性、過去の経緯などが複雑に絡むからです。
✅相続が止まりやすい典型パターン
- 実家に一人だけ同居している相続人がいる
- その人が売却に応じない・遺産分割協議に出てこない
- 他の相続人が遠慮して話し合いが進まない
- 結果として、不動産の相続登記や売却ができない
こうした「動きようがない」状況になってしまうと、固定資産税の支払いや管理の負担だけが増え、誰も得をしないまま時間だけが過ぎてしまいます。
遺産分割協議が成立しないとどうなる?
結論から言えば、不動産を売ることも、名義を変えることも、できません。
相続が発生したら、まず「誰が何を相続するか」を決める必要があります。これが遺産分割協議です。
協議がまとまれば、不動産の名義変更(相続登記)や売却に進めますが、一人でも反対すれば協議は成立しません。
そして厄介なのが、「話し合いができていない=何も進められない」という状態が、何年も続くことがあること。
例えばこんなご相談がありました。
✅【相談事例】
「父が亡くなって3年、次男が実家に住んでいて出る気がない。兄弟で話し合おうとしても“今はその気になれない”と言われて何も進みません」
このようなケースでは、調停や家庭裁判所の手続きを検討する必要があります。
でも、その前に「なぜ話が進まないのか」「どんな着地点があるのか」を整理することが大切です。
不動産が相続のカギを握る理由
実は、相続トラブルの7〜8割は不動産が絡んでいると言われています。
現金なら分けやすいですが、不動産は「分けられない」「使っている人がいる」「すぐには売れない」と、とにかく扱いが難しいのが特徴です。
✅【不動産が相続の難所になる理由】
| 課題 | 説明 |
|---|---|
| 分けられない | 土地や家は現物のままでは均等に分けにくい |
| 評価が分かれやすい | 不動産の価値を相続人同士でどう見るかで意見が分かれる |
| 誰かが住んでいる | 出ていく・住み続ける・賃貸に出すなど、意思のズレが大きくなる |
| 売るタイミングが難しい | 売却には手続き・費用・協力が必要。相続人全員の合意が前提 |
だからこそ、相続の話し合いは「不動産から手をつける」のが鉄則です。
そして、住んでいる人がいる場合は、なおさら丁寧な対話と情報整理が必要になります。
次のステップでは、売却に応じない次男の「本当の気持ち」と向き合う視点をご紹介しますね。
関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方
売却できない原因は?次男が実家に居座る主な理由と心理
「どうして次男が出ていかないのか、何を考えているのかわからない」
そんなふうに、相続の話し合いが止まってしまう背景には、表に出てこない“本音”が隠れていることが少なくありません。
めーぷる岡山中央店にも、同じようなご相談が寄せられます。
話し合いをしようにも「売りたくない」「今はその話をしたくない」とだけ言われて前に進めない。
ここでは、次男が実家に居座る本当の理由と、法的な立場を整理してみましょう。
「住み続けたい」以外にある3つの本音とは?
一見、「住み慣れた家を手放したくない」だけのように思えるかもしれません。
でも、もっと深い事情がある場合も多いです。
✅次男が出て行かない“3つの本音”
- 経済的な不安がある
→ 新しく住む場所を借りる費用がない、仕事が不安定、ローンが組めない…など - 親の介護を自分が担ってきたという自負
→ 「兄弟は何もしなかったのに、なぜ平等に分けるのか?」という気持ちがある - 親との思い出や過去に対する執着
→ 実家が「心のよりどころ」になっていて、手放すことに心理的な抵抗がある
こうした気持ちは、言葉にして出てこないことが多く、感情のもつれがトラブルの本質だったりします。
「なぜ出ていかないの?」とストレートに聞いても、本音は出てこないかもしれません。
だからこそ、まずは理解しようとする姿勢が大切です。いきなり「売ってほしい」と詰め寄るより、「どうしたいと思ってる?」という会話の糸口が解決への第一歩になることもあります。
同居相続人の立場と権利:法的にはどう扱われるか
「住んでいるからこの家は自分のもの」
そう思ってしまう気持ちは分かりますが、法的にはそうではありません。
相続が発生したあと、遺産分割がまとまっていない状態では、実家は相続人全員の共有財産です。
つまり、次男が勝手に「売らない」「出ない」と主張しても、それがそのまま通るわけではありません。
✅同居している相続人の法的立場
| 状況 | 権利・制限 |
|---|---|
| 遺産分割前 | 全相続人の“共有”とみなされる。単独での売却・居住継続の主張は不可 |
| 相続人が住み続けている | 生活権の保護は考慮されるが、他の相続人の同意なく勝手な処分はできない |
| 協議が不成立 | 家庭裁判所での調停・審判を通じて分割が決定されることも |
注意したいのは、「住んでいる=優先権がある」ではないということ。
ですが、長年住んでいたことや介護の有無などは、協議や裁判での判断材料になることがあります。
だからこそ、「法的にどうか」だけでなく、「人としてどうか」も考えながら、落としどころを探っていく必要があります。
話し合いがどうしても進まない場合は、調停などの第三者を介した場を活用することもひとつの選択肢です。
次回は、こうした行き詰まりを解決に導くための「実務的な7つの方法」をご紹介します。
関連記事:岡山エリアの遺品整理業者選びに役立つ情報
相続を進めるために取れる7つの対処法【専門家が解説】
「実家が売れない」「話し合いが進まない」そんな状態でも、手がないわけではありません。
私たち“めーぷる岡山中央店”にも、「兄弟で話がまとまらず、何年も相続が止まったまま…」というご相談がよくあります。
ここでは、相続を前に進めるための具体的な7つの対処法を、専門家の視点で整理してお伝えします。
家族の関係性や経済状況に合わせて、現実的な選択肢を見つけていきましょう。
① 遺産分割協議の再交渉:代償分割を提案する
もし話し合いが一度決裂していても、状況が変われば再交渉の余地はあります。
特に有効なのが、「代償分割(だいしょうぶんかつ)」の提案です。
これは、実家を相続したい人(たとえば次男)が他の相続人に現金などを支払うことで公平を図る方法。
「住みたい人」と「現金が欲しい人」のニーズがかみ合えば、争いを避けながらスムーズに話がまとまることもあります。
✅【代償分割のポイント】
- 不動産の評価額を明確にする(不動産業者の査定など)
- 支払える金額かどうか、無理のない範囲で提案
- 分割協議書に具体的な代償金額・支払い方法を記載する
次男に支払能力がない場合は難しいですが、金融機関の相続ローンなどを活用する事例もあります。
② 家庭裁判所に調停を申し立てる
話し合いがどうしても進まない場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用するのが次の一手です。
調停では、裁判官と調停委員が中立の立場で間に入り、話し合いを促してくれます。
「親族だけだと感情的になってしまう」
「誰かが出てこない、口を聞いてくれない」
そんなときでも、第三者が関わることで前に進むことができるケースが多いです。
調停が成立しない場合は、自動的に「審判」に移行し、裁判所が分割内容を決定します。
③ 不動産を共有から単独名義にする方法
今のままでは、実家が相続人全員の共有名義になっていることがほとんどです。
このままでは売却も、建て替えも、賃貸も、何もできません。
ここで考えたいのが、共有状態を解消し、1人の名義にすること。
そのためには、他の相続人が持つ持分を買い取ったり、話し合いで譲渡を受けたりする必要があります。
✅【共有名義の解消手段】
- 他の相続人に代償金を支払い、単独で名義を取得
- 名義変更には相続登記と贈与・売買の登記が必要
- 贈与扱いになると贈与税がかかる場合があるので注意
不動産を活用するためには、まず「誰が所有者なのか」を明確にするのが第一歩です。
④ 換価分割で現金化してから分配する
「どうしても話がまとまらない」
「家は要らない、現金で分けたい」
そんな場合には、不動産を売却してから代金を分け合う“換価分割(かんかぶんかつ)”が有効です。
ただしこの方法には、相続人全員の同意が必要です。誰か1人でも反対すると進められません。
話し合いで合意が難しい場合は、調停や審判で換価分割を求めることも可能です。
不動産の価値を客観的に評価して、売却に向けた準備を進めるとよいでしょう。
⑤ 不動産業者による任意買取の活用
相続人同士でまとまったとしても、「買い手がなかなか見つからない…」という問題もあります。
そんなときは、不動産買取業者による“任意買取”を検討するのも一つの方法です。
✅【任意買取のメリット】
- 手間をかけずに早く現金化できる
- 残置物があっても相談できる場合がある
- 相続人全員の合意があれば進めやすい
市場価格よりもやや低くなるのが一般的ですが、スピード重視・リスク回避を考えるなら有効な手段です。
⑥ 調停でも解決しないときの裁判対応
調停が不成立となった場合は、「審判」や場合によっては「訴訟」に進むことになります。
ここでは、家庭裁判所が不動産をどう分けるか、最終的な判断を下します。
審判は形式的な手続きではありますが、家族の関係性に亀裂が入る可能性もあるため、慎重に判断が必要です。
弁護士に相談しながら、他に選択肢がないか、改めて見直すことをおすすめします。
⑦ 相続土地国庫帰属制度の可能性は?
「誰も欲しくない」「処分にも困っている」
そんな土地については、国に引き取ってもらう制度が2023年から始まりました。これが相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)です。
ただし、利用には以下のような条件があります。
✅【主な適用条件】
- 更地であること(建物が残っていると不可)
- 担保権がついていない
- 隣接トラブルなどがない
- 管理コストがかかりすぎない土地であること
建物付きの実家には使えないことが多いですが、「不要な土地」の整理には有効です。
以上が、相続を前に進めるために取れる7つの現実的な方法です。
それぞれのご家庭の状況に応じて、どこから手をつけるべきか、一緒に考えていきましょう。
成功事例:住み続けたい次男と売却したい兄姉が合意できたケース
「うちの場合はもう無理かもしれない…」
そう思っている方にこそ知ってほしいのが、現実に“話し合いで解決できた”事例です。
もちろん、ご家族ごとに事情は違います。ですが、「お互いの希望を尊重しながら折り合う道」は、想像以上に見つかるものです。
ここでは、実際に私たち“めーぷる岡山中央店”にも寄せられた相談をもとに、解決のヒントになる3つの成功パターンをご紹介します。
【ケース1】代償金を支払い次男が単独相続した例
相談者は、4人きょうだいのうちの長女。
父が亡くなり、実家には次男が1人で住み続けていました。
他の相続人は「もう誰も住まないし、売って分けたい」と考えていましたが、次男は「出ていくつもりはない」と強硬な姿勢。
そこで提案したのが、「次男が実家を相続し、他の兄弟に代償金を支払う」方法でした。
不動産会社に査定を依頼し、家の評価額をベースに一人当たりの相続分を算出。
次男は貯金と金融機関からの借り入れで、兄弟3人に代償金を一括で支払いました。
結果として、
- 次男は住み慣れた家を守れた
- 他のきょうだいも公平な相続を受け取れた
「家を売る」以外にも選択肢があるんだと気づけたのが大きかったというお言葉をいただきました。
【ケース2】調停で第三者を入れてスムーズに解決した例
もう一つは、感情のもつれから協議が難航していたケースです。
きょうだい間で過去の確執があり、話し合いはまったく進まない状態でした。
そこで家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、第三者を交えて協議を再スタート。
調停委員が各相続人の意見を丁寧に聞き取りながら、冷静で現実的な着地点を探ってくれました。
結果、
- 次男は一定期間住み続ける権利を得る
- 他の相続人はその後に売却することに同意
- 売却益の配分方法を事前に決定
「調停って裁判みたいで大ごとに感じてたけど、むしろ安全な話し合いの場だった」と振り返られたのが印象的でした。
【ケース3】期限付きで居住継続→その後売却の合意を形成
3つ目は、双方の妥協によって落としどころを見つけたパターンです。
次男は「まだ出ていく気持ちになれない」、姉は「相続を先延ばしにしたくない」。
平行線に見えましたが、よく話を聞くと、次男にも「いずれ出るつもりはある」という本音がありました。
そこで双方が合意したのは、「あと3年だけ住み、その後売却する」という中間案。
売却までの間の管理費・固定資産税は次男が負担する、という条件も加えました。
このように「今すぐ売る or 一生住む」という二択ではなく、“期限付きの猶予”という第3の選択肢も可能です。
お互いが納得できる条件を一つずつ整理していけば、前向きな合意にたどり着くことができます。
解決できた事例の背景には、感情を整理しながら選択肢を可視化するプロセスがあります。
ご自身のケースと照らし合わせて、どの方向が現実的か、一歩ずつ考えてみてくださいね。
関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方
今すぐやるべきことチェックリスト【相続停滞を抜け出す第一歩】
「動かなきゃとは思ってる。でも、何から始めればいいのか分からない」
そんな声を、私たち“めーぷる岡山中央店”でもよくお聞きします。
実家の相続が止まっていると、時間とともに問題は複雑になりがちです。
だからこそ、今すぐできる“整理と準備”が、すべてのスタートになります。
ここでは、相続が進まない状態から一歩踏み出すための、実務的なチェックリストをご紹介します。
✅ 相続人・不動産の状況を整理する
まず最初に取り組むべきなのは、「誰が相続人なのか」「何が遺産として残っているのか」を明確にすることです。
✅【チェックポイント】
- 相続人全員の把握(戸籍の確認が必要な場合も)
- 実家の名義(まだ亡くなった親の名義?相続登記済み?)
- 不動産の評価額(固定資産税評価額・不動産業者の査定など)
- 共有名義の有無(登記簿謄本で確認できます)
- 維持費や管理費(固定資産税・修繕費などの現状)
「誰のものか分からない」「名義変更していない」ままでは、何も進みません。
紙とペンで簡単な表を作るだけでも、次のアクションが見えてきます。
✅ 次男の意思と現実的な提案の準備
話し合いが進まない原因は、相手の立場を想像できていないことにある場合がほとんどです。
だからこそ、「何を望んでいるのか」「何なら受け入れてくれそうか」を冷静に整理しておくことが大切です。
✅【準備すべき視点】
- 次男が住み続けたい理由(生活・感情・介護など)
- 金銭的な負担能力(代償金の支払いが可能か)
- 他の相続人が納得できる条件は何か(期限付き居住、維持費負担など)
- 売却せずに済む選択肢(共有継続、賃貸転用など)
いきなり「売って」と言っても、反発されるだけです。
提案するなら、現実的で相手の立場も尊重した内容を準備しましょう。
✅ 専門家に相談する前にすべきこと
専門家に相談するのはとても有効ですが、事前に状況を整理しておくと、相談の質も結果も大きく変わります。
✅【相談前にまとめておきたい情報】
- 相続人の構成と関係性
- 遺産の内訳(不動産・預金・借金など)
- 実家の利用状況と誰が住んでいるか
- 過去の話し合いの経緯(合意・対立のポイント)
- 今後の希望や妥協点(できれば各相続人の考えも)
ここまで整理できていれば、司法書士・弁護士・不動産業者のどこに相談すべきかも明確になってきます。
相続の停滞は、ほんの小さな一歩で動き出すことがあります。
「話せない」ではなく、「どう話すか」。
「解決しない」ではなく、「どこから始めるか」。
その第一歩を、今日ここから踏み出してみてください。
関連記事:遺品整理を安く済ませるための完全ガイド
よくある質問Q&A:売却を拒否する家族にどう対応する?
「うちの家族、話が通じないんです…」
相続の現場では、理屈だけでは割り切れない感情や関係性が立ちはだかります。
なかでも多いのが、「売却にどうしても反対する家族」に関するご相談。
ここでは、よくある質問とその対応方法をQ&A形式でまとめました。
実際に現場で繰り返されてきたやり取りだからこそ、“次にどう動けばいいか”が見えてくる内容です。
相続人の一人が売却に反対しているときはどうすれば?
まず大前提として、不動産を売却するには共有者全員の合意が必要です。
つまり、誰か一人でも反対していれば、原則として売ることはできません。
では、そこで行き詰まるかというと、そうではありません。
✅【対応の選択肢】
- 再交渉の余地がないか確認する(代償分割・期限付き案などを提示)
- 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
- 調停が不成立の場合は、審判や換価分割(売却後に現金で分ける)を裁判所に求めることも可能
「話が進まないからもう諦める」のではなく、法的に次のステップを踏む仕組みが用意されていることを知っておくと安心です。
同居している相続人に立ち退いてもらえる?
とてもデリケートな問題ですが、法的には「住み続ける権利」が無制限に認められているわけではありません。
ただし、強制的に立ち退きを求めるには条件があります。
✅【立ち退きを求めるには】
- 所有権者が確定している(共有状態が解消されている)
- 占有者に対して明確な通知・要請を行っている
- 相手が任意に応じない場合は、明渡請求訴訟を起こすことが必要
実家に長く住んでいたり、介護をしていた経緯がある場合には、裁判所もその事情を考慮する傾向があります。
強制的な手段をとる前に、できる限りの話し合いや代替案を提示することが大切です。
不動産の評価額は誰が決めるの?
評価額によって、代償金の金額や分配方法が大きく変わるため、「どの価格を採用するか」は非常に重要なポイントです。
✅【よく使われる3つの評価基準】
| 評価方法 | 説明 | 特徴 |
|---|---|---|
| 固定資産税評価額 | 市町村が課税のために算定 | 一般的に実勢価格の7割程度 |
| 路線価評価 | 相続税の申告で使う基準 | 実勢価格の80%前後が目安 |
| 実勢価格(査定) | 不動産会社が市場価格をもとに算出 | 最も現実的な売買価格に近い |
公平に評価したい場合は、複数の不動産会社に査定を依頼し、その平均値を参考にするのが実務的です。
必要に応じて、不動産鑑定士による正式な鑑定評価を依頼する方法もあります。
不動産がからむ相続では、「感情」と「法律」と「お金」のバランスが問われます。
どれか一つに偏るのではなく、全体像を整理しながら一歩ずつ進めることが大切です。
関連記事:遺品整理費用節約の秘訣とおすすめ手順