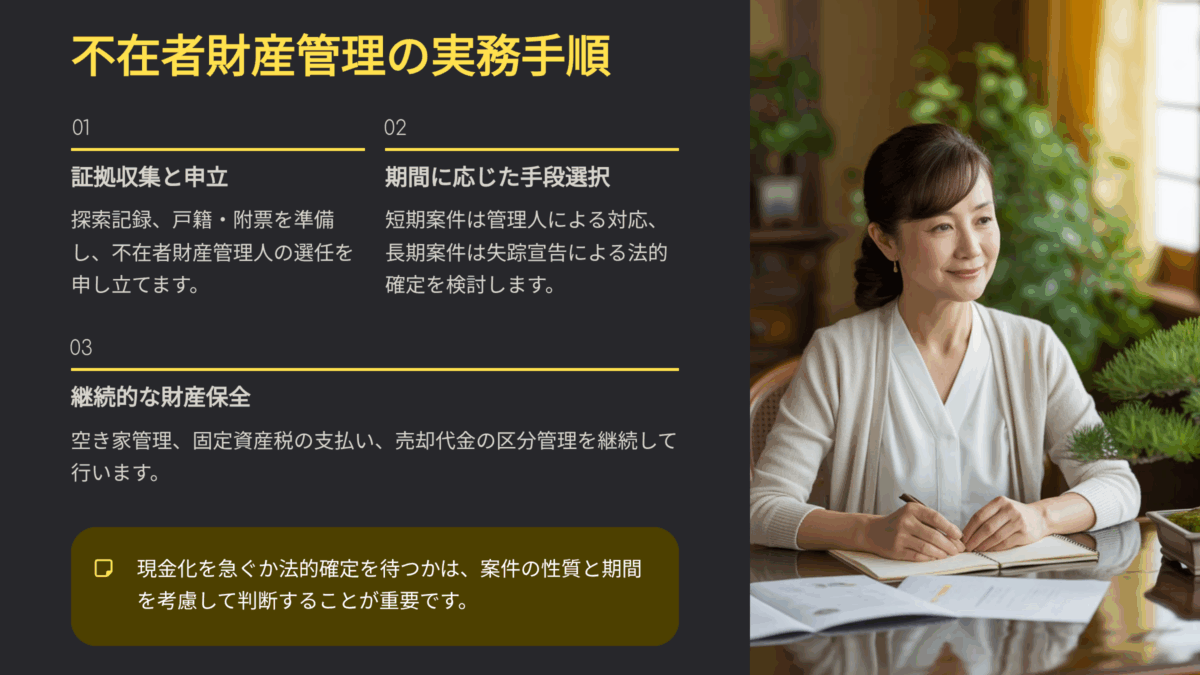相続人が行方不明で相続が止まった方へ。不在者財産管理人・失踪宣告・空き家管理と売却の実務をやさしく整理しました。目次を見て必要なところから読んでみてください。
- 事例概要:70歳、相続人が行方不明で相続手続きが止まったケースの全体像
- 家族構成・資産の内訳(不動産・預貯金)と何が止まっているか
- 行方不明の期間・連絡経路・探索実績の整理ポイント
- どの局面で「相続人不明」が法的な壁になるのか(登記・売却・金融機関)
- 遺産分割協議が成立しない理由と有効性の要件
- 金融機関手続き・相続登記・不動産売却に及ぶ影響
- 税務(相続税・固定資産税)と管理責任の注意点
- 住民票・戸籍・附票の追跡と公的端緒の集め方
- 親族・勤務先・ライフライン等への照会履歴の記録化
- 警察届出・失踪届では足りない点と限界
- 申立要件・必要書類・申立先と流れ
- 管理人にできること/できないこと(同意・売却・保全)
- 期間と費用の目安・予納金の考え方
- 実務で併用される遺産分割調停・許可申請の関係
- 相続財産管理人選任が適切な場面
- 公示送達で進める調停・審判の使いどころ
- 特別代理人・選任申立との違い
- 0〜90日:探索と証拠化/申立準備
- 3〜6か月:選任後の許可取得・資産保全
- 6〜12か月:分割成立・登記・売却・税務完了
- 管理義務・損害防止(修繕・保険・近隣トラブル予防)
- 差し迫る固定資産税・維持費への対処
- 売却タイミングと価格下落リスクの見極め
- 委任状・受任範囲の設計と進捗管理
- 書類・連絡ログ・費用台帳のテンプレ活用
- 家族間連絡のルール化(代表者・頻度・意思決定)
- 選択肢の比較検討と意思決定プロセス
- 具体的なスケジュール・費用・結果(数値例)
- つまずきポイントと回避策
- 何年待てば失踪宣告できる?不在者財産管理人で代替できる?
- 探索はどこまで必要?どの程度で“尽くした”といえる?
- 売却代金はどう保管する?配当はいつ可能?
- 途中で行方不明者が見つかったらどうなる?
- ケース別の使い分け指針(当面の現金化/長期見据え)
- 迷ったら「証拠化→申立→許可取得」の王道手順
事例概要:70歳、相続人が行方不明で相続手続きが止まったケースの全体像
「相続人が行方不明で、相続手続きが一歩も進まない」——そんなご相談は少なくありません。相続人行方不明は、登記や解約、売却のあらゆる場面で壁になります。ここでは全体像を整理し、どこで止まり、何から着手すべきかを実務の目線でまとめます。私、めーぷる岡山中央店の星川あきこが、最初の一歩を一緒に描きますね。
家族構成・資産の内訳(不動産・預貯金)と何が止まっているか
まずは「誰の相続で、誰が相続人で、財産は何か」を見取り図にします。ここが曖昧だと、後の手続きが二度手間になります。
【ケースの前提(例)】
- 被相続人:母(単独名義の自宅あり)
- 相続人:長男(同居・申立て担当)、次男(行方不明・10年連絡なし)
- 主な遺産:自宅(土地建物)、普通預金、定期預金、少額の有価証券
【どこが止まっている?】
- 遺産分割協議:相続人全員の合意が必要。行方不明者の署名押印が得られず成立不可。
- 相続登記(名義変更):分割協議書がないため申請できない。
- 金融機関解約:相続人全員分の書類が揃わず凍結状態。
- 不動産の売却・賃貸:処分行為に全員の同意が要るため進められない。
表:資産ごとの「止まりポイント」と必要書類(概要)
| 資産区分 | 目的 | 典型的に止まる理由 | 主要書類の要件 |
|---|---|---|---|
| 不動産 | 相続登記・売却 | 分割協議不成立 | 分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明) |
| 預貯金 | 解約・払戻し | 相続手続書類が不備 | 相続関係説明図、戸籍一式、分割協議書 |
| 証券 | 名義変更・換金 | 同意欠如 | 取引先指定書式+分割協議書 |
| 動産(家財等) | 形見分け・処分 | 誰が決めるか不明確 | 分割協議の合意(メール記録でも目安に) |
✅ポイント:全資産に共通して「相続人全員の同意」が鍵です。同意できない=一括で止まるため、まずは「同意の代替手段」を検討します。
この章を読んだらやること
- ✅ 家族構成(相関図)と資産目録を1枚に整理
- ✅ どの資産がどの書類で止まっているかを可視化
行方不明の期間・連絡経路・探索実績の整理ポイント
裁判所に申し立てる際、「探したけれど見つからない」ことの証拠化が重要です。感覚的な説明では足りません。行方不明の期間・連絡手段・探索履歴を、時系列で残しましょう。
整理のコツ
- 期間の特定:最後に連絡が取れた日付、最終のSNS・メール・通話記録。
- 連絡経路:電話・メール・SNS・手紙・実地訪問など、経路ごとに結果を記録。
- 公的な足取り:住民票の附票(住所履歴)、戸籍の本籍移動、転出入の有無。
- 第三者への照会:親族、元勤務先、管理会社、ライフライン(電気・ガス・水道)への在籍・契約の有無。
- 警察届出の位置づけ:行方不明者届=探索の一要素。ただし、これだけでは手続きの代替にはならないことを理解。
- 記録の形式:日付・先方・方法・結果をチェックリスト型で。メールや封書は写しを保管。
簡易テンプレ(抜粋)
| 日付 | 連絡方法 | 先方 | 結果 | 添付 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/6/10 | 電話 | 次男携帯 | 不通 | 通話履歴 |
| 2023/7/01 | 住民票附票取得 | 市区町村 | 転出先不明 | 取得写し |
| 2023/8/15 | 親族Aに照会 | 従兄 | 数年前から不明 | メモ |
✅ポイント:「尽くした」可視化が、裁判所の判断を後押しします。結果が空振りでも意味があります。手間ですが、ここを丁寧に。
この章を読んだらやること
- ✅ 直近6〜12か月分の探索ログを作成
- ✅ 戸籍・附票など公的資料の取得順序を決める
どの局面で「相続人不明」が法的な壁になるのか(登記・売却・金融機関)
行方不明の相続人がいると、「処分」や「解約」に関わる局面が軒並み停止します。理由は単純で、相続人全員の関与が前提だからです。具体的には次のとおりです。
主なボトルネック
- 遺産分割協議:一人でも欠けると無効リスク。書面の形式要件も厳格。
- 相続登記(名義変更):分割協議書がないと登記申請ができない。令和の制度改正で登記義務化が進む流れの中、遅延は不利。
- 不動産の売却・賃貸:売買契約は処分行為。全員の同意か、不在者財産管理人(家庭裁判所が選ぶ代理人)の関与+許可が必要。
- 金融機関手続き:各行の相続手続きは相続人全員の署名押印が基本。例外運用は限定的。
- 税務・維持管理:固定資産税や保険、修繕は待ったなし。ただし、誰が支払うか・立替精算の根拠を記録しておく。
対処の方向性(概要)
- 短期の安全確保:空き家の保全、保険の確認、最低限の支払い継続。
- 法的な前進策:
- 不在者財産管理人の選任申立て(行方不明でも進めるための中核手段)
- 公示送達や調停の活用(連絡が取れない相手への手続的アプローチ)
- 失踪宣告(原則7年行方不明で死亡とみなす制度。長期戦の選択肢)
✅結論:相続人不明は、合意・登記・解約・処分の全工程で足止めになります。だからこそ、探索の証拠化→家庭裁判所での手段選択が王道です。
この章を読んだらやること
- ✅ 止まっている工程を「合意・登記・解約・処分」に分類
- ✅ 不在者財産管理人か失踪宣告、どちらを軸にするか家族で方向づけ
相続人が行方不明だと何ができなくなる?法的ボトルネックの整理
「相続人 行方不明」で止まるのは、感覚ではなく要件が満たせないためです。めーぷる岡山中央店の星川あきこです。ここでは、遺産分割協議・相続登記・金融機関・売却の各局面で、どこに壁が立つのかを実務目線で整理します。先に全体像を押さえ、次に打ち手を選びましょう。
遺産分割協議が成立しない理由と有効性の要件
遺産分割協議は、相続人全員の合意が前提です。ひとりでも欠けると、合意自体が成立しません。行方不明は「反対」ではなく不在。だからこそ、協議書を作っても有効性に欠けるのです。
協議が無効・不成立となる主な理由
- 相続人の欠缺:一人不明でも全員合意が未充足です。
- 範囲の不備:相続人の漏れ・認定ミス(再婚・認知などの見落とし)。
- 方式の不備:書面の署名・実印・印鑑証明が揃わない。
- 意思表示の瑕疵:代理人の権限が曖昧、本人確認が不十分。
有効な遺産分割協議書の要点(実務チェック)
- 相続関係の確定:戸籍一式+相続関係説明図で全員確認。
- 対象財産の特定:不動産は所在・地番・家屋番号、預貯金は金融機関・支店・口座番号まで。
- 全員の署名押印:実印+各人の印鑑証明書。
- 日付と原本管理:成立日を明記、原本は複数作成し長期保管。
ここでの打ち手
- 不在者財産管理人の選任(家庭裁判所の制度。不在者の利益保護と協議参加を代替)
- 公示送達+調停・審判の併用(連絡不能時の手続きルート)
- 失踪宣告(原則7年で死亡擬制。長期戦の最終選択肢)
✅結論:「全員の合意」という壁を越えるには、裁判所手続きで代替するのが現実的です。
金融機関手続き・相続登記・不動産売却に及ぶ影響
行方不明は、解約・名義変更・処分の各工程で止まります。理由は相続人全員関与の要件と、金融機関・法務局の実務運用にあります。
影響の全体像(どこで止まり、何が要るか)
| 手続き | どこで止まるか | 典型的に求められるもの | 代替・突破口 |
|---|---|---|---|
| 預貯金の払戻し | 相続人全員の同意欄が空欄 | 戸籍一式、相続関係説明図、遺産分割協議書 | 不在者財産管理人選任→同意・払戻し手続き |
| 投資商品の換金 | 売却・払戻しの同意 | 金融機関指定書式+協議書 | 管理人の必要処分許可で実行可 |
| 相続登記(名義変更) | 申請書の添付不足 | 協議書、登記原因証明情報 | 管理人関与の協議/審判確定書で代替 |
| 不動産の売却 | 売買は処分行為で同意必須 | 全員合意、委任状 | 管理人+家庭裁判所の許可で実行可能 |
| 賃貸・一時使用 | 利益相反・権限外の恐れ | 合意・委任 | 管理人の管理行為として許容される範囲で可 |
実務の注意
- 金融機関は独自基準が細かいです。書式や必要書類は支店で事前確認が鉄則です。
- 売却代金の保管は、管理人名義の供託・別口座で区分管理が基本。
- スピード感を出すには、探索記録を整えて申立書の説得力を高めるのが近道です。
✅結論:同意が取れない領域=停止。管理人+裁判所許可で段階的に動かすのが王道です。
税務(相続税・固定資産税)と管理責任の注意点
相続人が不明でも、税や管理は待ってくれません。期限や責任の所在を押さえ、立替と精算の根拠を残しましょう。
押さえるべき論点
- 相続税の申告期限:原則10か月。不明者がいても期限は進みます。必要なら延納・物納や更正の請求を視野に。
- 準確定申告:被相続人の所得税は4か月以内。漏れやすいので担当を決めます。
- 固定資産税:名義が変わらなくても毎年発生。納税通知書の受け口を確保し、立替台帳で見える化。
- 空き家の管理責任:倒壊・漏水・害虫などの損害防止義務。保険(火災・施設賠償)の継続を確認。
- 費用の性質:修繕・保険・固定資産税等は相続財産の保存費用として、後日精算対象にできます。
ミニチェックリスト
- ✅ 税の期限カレンダーを作成(10か月/4か月の2本柱)
- ✅ 固定資産税・保険の支払いを自動化し、立替台帳に記録
- ✅ 空き家の目視点検と鍵管理、近隣への連絡先明示
- ✅ 必要に応じて管理人選任申立てで保全と費用支出の根拠を確保
✅結論:税と管理は止めずに走らせる。支払いと記録を続け、後で公正に清算できる形に整えておくことが、結果的に家族を守ります。
まず着手する探索と証拠化:行方不明者の所在調査
「探したけれど見つからない」を伝えるには、感情ではなく証拠が必要です。最初に集めるのは公的資料(住民票・戸籍・附票)、次に民間の足取り(親族・勤務先・ライフライン)。最後に警察届の位置づけを整理します。順番を決め、淡々と記録化していきましょう。私も横でチェック表を一緒に作るつもりでご案内します。
住民票・戸籍・附票の追跡と公的端緒の集め方
最短で芯を取りにいきます。まずは戸籍一式で相続人を確定し、住民票の附票(住所履歴)で足取りをたどる。ここがズレると、後工程が総崩れになります。
公的資料の取り方・使い方(実務版)
| 資料 | 何が分かるか | 取得先・請求者 | 申請のコツ | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 戸籍(全部事項) | 相続人の範囲・続柄・本籍の変遷 | 本籍地の市区町村/法定相続人等 | 出生から死亡までの連続取得 | 婚姻・認知の見落としに注意 |
| 戸籍の附票 | 本籍に紐づく住所の履歴 | 本籍地 | 期間指定で過去分を請求 | 保存年限により古い履歴が欠落も |
| 住民票(除票含む) | 住民登録の現住所(過去含む) | 住民登録地 | 職務上請求事由を明示(相続手続き) | 除票は保存年限に注意 |
| 不在住・不在籍証明 | その市区町村にいない証明 | 該当市区町村 | 「転出先不明」の裏取りに | ピンポイントで使う |
申請理由の書き方の要点
- 目的を具体化:「相続人の所在確認のため」「家庭裁判所への申立資料のため」
- 関係性を明記:「被相続人の長男・法定相続人」など
小さなつまずき対策
- 保存年限で古い履歴が取れない→本籍・住所の両方の附票を当たり、断片をつなぐ。
- 本籍が分からない→直近の住民票の附票から本籍手がかりを拾う。
- 役所で断られた→目的と相続関係の説明資料(相続関係説明図・死亡の戸籍)を添付。
この節を読んだらやること
- ✅ 戸籍は出生〜現在の連続取得を指示
- ✅ 住民票の附票(現住所・本籍側)を双方請求
- ✅ 相続関係説明図を1枚で作り、更新日を入れる
親族・勤務先・ライフライン等への照会履歴の記録化
公的資料で足が途切れたら、民間の足取りを丁寧に。ここで重要なのは結果が空振りでも記録すること。裁判所が見るのは“結果”だけでなく探索の尽力です。
記録化テンプレ(コピーして使えます)
| 日付 | 先方(関係) | 連絡方法 | 要点 | 結果 | 添付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 従兄(親族) | 電話 | 最終接触時期の確認 | 2018年以降不明 | 通話履歴 |
| 2025/03/15 | 旧勤務先 | 書面 | 退職時期・連絡先照会 | 回答なし | 発送控え |
| 2025/03/20 | 管理会社 | メール | 旧住所の退去日確認 | 2020/5退去 | 返信印刷 |
| 2025/03/25 | 電力会社 | 書面 | 契約継続の有無 | 取次不可 | 申請控え |
実務メモ
- 連絡手段は分散(電話・書面・メール)。同一先でも時期を変えて複数回。
- 質問は限定:「最終連絡時期」「退去日」「郵送物の転送」など事実のみに集中。
- 個人情報の壁:ライフラインや勤務先は原則開示しません。回答不可の通知も“探索の証拠”になります。
- 封筒面の写し、配達記録、メールヘッダーなど形式的証拠を残す。
この節を読んだらやること
- ✅ 直近6〜12か月ぶんの探索ログをまとめる
- ✅ 「誰に・いつ・どうやって・何を聞いたか」を1行で言語化
- ✅ 不達・沈黙も結果として記録
警察届出・失踪届では足りない点と限界
「警察に届けたから大丈夫」——ここがよくある誤解です。行方不明者届(捜索願)は大切ですが、家庭裁判所の判断を代替する資料にはなりません。役割の違いを押さえましょう。
押さえるべきポイント
- 目的の違い:警察は保護・安全確認が主目的。相続・登記・売却の同意代替にはならない。
- 情報開示の限界:警察から所在情報は原則非開示。届出受理番号の写しは“探索の一部”として添付。
- 裁判所手続きの要:不在者の利益を守りつつ手続きを前に進めるには、不在者財産管理人の選任や公示送達・調停が必要。
- 失踪宣告のハードル:原則7年の不在(特別失踪は災害・事故など)。緊急の資産処分には不在者財産管理人+許可が現実的。
現実解(最短ルート)
- 公的資料で所在履歴を固める
- 探索ログで尽力を可視化
- 家庭裁判所へ申立て(管理人選任)
- 必要に応じて許可申請で売却や払戻しへ
この節を読んだらやること
- ✅ 警察届は受理番号・届出日を記録し写しを保管
- ✅ 次の一歩として管理人選任の申立書案を作りはじめる
- ✅ 「失踪宣告は長期戦」—短期は管理人+許可軸で設計
手続きを前に進める中核選択肢① 不在者財産管理人の選任(家庭裁判所)
「相続人が行方不明のままでは、合意も登記も動かない」。そこで現実解になるのが不在者財産管理人です。家庭裁判所が第三者を選び、不在者の利益を守りつつ同意や処分を代替できます。ここでは、申立ての要件から費用・期間、併用手続きまで一気に整理します。
申立要件・必要書類・申立先と流れ
要件の芯はシンプルで、①対象者が長期間所在不明、②財産の管理・手続きに支障が出ている、の2点です。証拠は探索ログ+公的資料で固めます。
申立てに用意する主な書類
- 申立書(事情・目的を具体化)
- 戸籍・住民票・附票(所在追跡の裏づけ)
- 探索の記録(照会履歴・不達記録・受理番号等)
- 財産目録(不動産登記事項、預貯金残高、保険等)
- 相続関係説明図(誰が相続人かを一枚で)
- 予納金関係書類(金額案内、郵便切手等)
申立先と標準フロー
- 管轄家庭裁判所へ申立て(被相続人の最後の住所地が目安)
- 裁判所の審理・照会(不足資料の補充)
- 管理人の選任審判(弁護士等が選ばれるのが一般的)
- 就任・引継ぎ(財産の把握、通帳・鍵・書類の受領)
- 必要に応じて許可申請(売却・払戻し等の処分行為)
- 定期報告・精算(区分管理・費用の清算)
✅ここまでの結論:「探索の証拠化→申立→選任」の一直線。書類の説得力が審理の速さを左右します。
この章を読んだらやること
- ✅ 探索ログと財産目録を最新化
- ✅ 相続関係説明図を一枚で整備
- ✅ 管轄裁判所と予納金の目安を電話で確認
管理人にできること/できないこと(同意・売却・保全)
不在者財産管理人の権限は、管理行為は原則OK/処分行為は許可が必要、が基本線です。線引きを把握すると、申請の順番がブレません。
できること(典型例)
- 管理・保存行為:通帳・権利証の保全、保険継続、軽微な修繕
- 情報収集:残高照会・評価取得・明細取り寄せ
- 賃料や果実の受領:既存賃貸の管理、滞納催促
- 調停・審判への関与:不在者の立場で遺産分割調停に参加
許可が必要なこと(処分)
- 不動産の売却・解体、新規賃貸(期間・条件により)
- 預貯金の払戻し・解約、有価証券の売却
- 訴訟提起・和解(事件性による)
できないこと(禁止・制約)
- 本人の意思決定の完全代替(利益相反は厳格回避)
- 勝手な分配・贈与(清算・配当は裁判所の枠組みで)
- 権限外の長期契約(将来拘束が大きい契約は原則不可)
運用のコツ
- まずは評価・査定・残高照会で事実を固め、次に許可申請へ。
- 売却は価格の相当性(複数査定・相場資料)で許可が通りやすくなります。
- 代金は区分口座・供託で厳密に分離管理。
✅ここまでの結論:管理は即時、処分は許可。段取りを分けるだけで前進スピードが上がります。
この章を読んだらやること
- ✅ 「管理」「処分」「報告」にToDoを仕分け
- ✅ 売却を狙うなら査定2〜3本を同条件で取得
- ✅ 払戻しは目的明確化(税・保全費用等)で申請
期間と費用の目安・予納金の考え方
裁判所・財産規模・資料の完成度でブレますが、おおまかな目安を持っておくと計画が立てやすいです。
期間のイメージ(目安)
| フェーズ | 期間の目安 | ボトルネック | 短縮のコツ |
|---|---|---|---|
| 申立準備 | 2〜6週間 | 戸籍・附票の収集、探索整理 | 早期に出生〜死亡の連続戸籍を取得 |
| 選任審理 | 3〜8週間 | 補正対応、候補者調整 | 不足ゼロで初回申立て |
| 許可申請 | 2〜6週間 | 相場資料・必要性の説明 | 複数査定+用途明確化 |
| 売却・払戻し実行 | 1〜3か月 | 契約・決済・名義変更 | 事前に書式・必要書類を確認 |
費用のイメージ(概算)
| 費目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙・郵券 | 数千円〜 | 事件種別・管轄で変動 |
| 予納金 | 20万〜50万円程度 | 財産規模・調査範囲により上下 |
| 管理人報酬 | 数十万〜 | 事案の難度・期間で裁判所が相当額を決定 |
| 売却関連費 | 査定・登記・仲介等 | 実費+成功時の報酬が中心 |
予納金の考え方
- 調査・通知・公告等の原資。大きめに積んで不足を避け、余剰は清算返還。
- 先に資産の流動性(預金の有無)を把握し、キャッシュ化までのつなぎ資金を見積もる。
✅ここまでの結論:期間は数か月単位、費用は数十万円単位が一般的。探索の精度と書類の完成度で短縮が可能です。
この章を読んだらやること
- ✅ 自分の地域の予納金相場を裁判所に確認
- ✅ 期間表を家族と共有(税の期限と重ねる)
- ✅ つなぎ資金の手当て計画を作成
実務で併用される遺産分割調停・許可申請の関係
管理人を選任しただけではゴールではありません。遺産分割調停や個別の許可申請を並走させることで、停滞を減らせます。
併用の型(よくある流れ)
- 型A:先に売却資金を確保
- 管理人選任 → 2) 売却許可 → 3) 売却・代金区分管理 → 4) 分割調停で配分協議
- 型B:先に配分の枠を固める
- 管理人選任 → 2) 遺産分割調停で方針合意 → 3) 必要な売却・払戻しを許可申請
調停・許可を通すコツ
- 必要性の明確化:固定資産税・老朽化・事故リスク等、保全の必然性を数字で。
- 価格の相当性:査定複数本、近隣成約、路線価・公示地価など客観データ。
- 配慮義務:不在者の不利益にならない配分案・期限管理、報告の透明性。
最後に——星川からひとこと
- 最短ルートは「証拠化→選任→許可」。途中で迷ったら、目的(保全・換価・配分)を一行で言えるかを確認しましょう。言えれば、次の書類が決まります。
もう一つの選択肢:相続財産管理人・公示送達・調停等の補助ツール
不在者財産管理人だけでは動かしにくい場面があります。相続人全体の不明・連絡不能や、相手方への送達ができないときは、相続財産管理人・公示送達・特別代理人といった補助ツールを組み合わせると前に進みます。星川が実務の使いどころを具体的に整理します。
相続財産管理人選任が適切な場面
相続人全員が不明または相続放棄により管理者不在など、遺産そのものに管理者がいないときの“全体管理”の切り札です。目的は、遺産の保全・換価・債権者対応を中立的に進めること。
主に次のようなときに相性が良いです。
- 相続人が誰も分からない/連絡不能が多数
- 固定資産税・保険・修繕などの保存費用を誰も決められない
- 空き家・貸家の危険性が高く、早期の保全措置や換価が必要
- 債務・滞納があり、配当の枠組みが要る
相続財産管理人でできる主なこと
- 遺産の一体管理・換価・配当(公告・債権届出を経て公平に配分)
- 必要な売却・解約の実行(許可が前提)
- 未知の相続人探索・公告による関係者の把握
申し立ての勘所
- 遺産目録と危険性(老朽化・滞納など)を具体化
- 費用原資の見込み(預金・売却予定)を示す
- 公告・配当までの道筋をタイムラインで提示
この節を読んだらやること
- ✅ 相続人の把握状況を一覧化(確定/不明/連絡不能)
- ✅ 保存費用・危険箇所を写真と数字で記録
- ✅ 管理人選任の申立草案に、換価・配当の方針を一行で明記
公示送達で進める調停・審判の使いどころ
相手の住所が分からず書類が届かないと、調停・審判が進みません。そこで登場するのが公示送達。裁判所掲示などの方法で「送達があったものとみなす」制度です。連絡不能の相手を手続に乗せるための実務ツールと捉えてください。
使いどころ
- 遺産分割調停で一部相続人に連絡がつかない
- 管理人選任後の許可申請で関係人通知が必要
- 登記や換価に関する審判で相手方の所在が不明
通しやすくするコツ
- 探索の尽力を証拠化(戸籍・附票・照会履歴・不達封筒)
- 宛先候補すべてに打診→不達記録を積み上げる
- 公示後に備え、掲示期間と次回期日をカレンダーへ反映
留意点
- 形式は満たしても、実質の相手理解は進まないため、後日の紛争再燃リスクに備え、価格相当性・配慮義務の記録を厚めに。
この節を読んだらやること
- ✅ 公示送達用の不達セット(封筒・受領拒否・転送記録)を整理
- ✅ 期日管理を家族共有のカレンダーで可視化
- ✅ 主要資料(査定・写真・台帳)を同一フォルダで管理
特別代理人・選任申立との違い
特別代理人は、未成年相続人など利益相反があるときに、その子のために意思表示を代替する制度です。行方不明の代替とは目的が違います。混同しやすいので、要点を表で押さえます。
| 制度 | 目的 | 典型的な場面 | 権限の範囲 | カギとなる要件 |
|---|---|---|---|---|
| 不在者財産管理人 | 行方不明者の財産管理・処分の代替 | 相続人の一部が不明・連絡不能 | 管理行為は原則可、処分は許可 | 所在不明+手続支障の疎明 |
| 相続財産管理人 | 遺産全体の中立管理・換価・配当 | 相続人不明・不在/放棄で管理者なし | 一体管理、公告、配当(許可前提) | 管理者不在の遺産があること |
| 特別代理人 | 利益相反の解消(未成年など) | 親と子が相続で利害相反 | 事件限定で同意・和解等 | 利益相反+未成年等の存在 |
| 公示送達(手段) | 送達不能の解消 | 住所不明で書類が届かない | 送達みなしのみ | 探索尽力+所在不明の疎明 |
実務判断の指針
- 行方不明の一点突破なら不在者財産管理人。
- 遺産全体に管理者がいないなら相続財産管理人。
- 親子などの利益相反には特別代理人。
- どの制度でも送達が壁なら公示送達を重ねる。
この節を読んだらやること
- ✅ いまのボトルネックを「管理者不在/所在不明/利益相反/送達不能」に分類
- ✅ 制度の主語(誰のための何の代理か)を書き出す
- ✅ 次の申立書のタイトルと目的を一行で言えるか確認
タイムラインで理解する実務の進め方(90日・6か月・1年の節目)
「結局、いつ何をやれば間に合うのか」。相続人行方不明の案件ほど、段取りの遅れが雪だるま式に効いてきます。この章では0〜90日/3〜6か月/6〜12か月の3区間で、やることを時系列に落とし込みます。証拠化→申立→許可→実行→精算の流れを一気通貫で押さえましょう。
0〜90日:探索と証拠化/申立準備
最初の90日で勝負が決まります。やることは所在探索の証拠化と、家庭裁判所申立の準備。ここで資料が揃えば、その後の審理が短くなり、余計な往復が減ります。
やること(優先順)
- 相続関係の確定:出生からの戸籍一式、相続関係説明図を1枚で完成
- 住所履歴の追跡:住民票・附票・除票、不在住不在籍証明の取得
- 探索ログの作成:親族・勤務先・管理会社・ライフライン等への照会履歴(不達も保存)
- 財産目録の整備:不動産(登記事項・評価)、預貯金(残高・支店)、保険・証券
- 写真と数字の準備:空き家の劣化箇所、固定資産税・保険料の保存費用
- 申立書ドラフト:不在者財産管理人を主軸に、目的(保全・換価・配分)を一行で明記
- 税の初動:相続税10か月・準確定申告4か月の期限カレンダーを家族で共有
ミニ表(提出書類の完成度チェック)
| 区分 | 必須資料 | 完成度目安 |
|---|---|---|
| 相続関係 | 戸籍一式・説明図 | 漏れなし、続柄確認済み |
| 所在探索 | 附票・不達封筒・照会記録 | 時系列・証拠添付済み |
| 財産 | 登記事項・残高証明・評価 | 最新月で統一 |
次の一歩
- ✅ 申立書と証拠目録をセットで作成
- ✅ 予納金の概算見積りを管轄へ確認
- ✅ 税・固定資産税の自動支払と立替台帳を開始
3〜6か月:選任後の許可取得・資産保全
管理人選任後は二本立て。①管理・保全を止めない、②処分行為の許可を確実に取る。スピードを出したいなら、評価→許可→実行の順で並行します。
やること(時系列)
- 就任直後1〜2週:通帳・権利証・鍵の受領、残高照会、保険継続の確認
- 同時並行:不動産の複数査定(2〜3社)、近隣成約事例・路線価の収集
- 許可申請:売却・払戻し等は必要性(老朽化・税負担・危険)+価格相当性で説得
- 公示送達の準備:連絡不能者がいる手続は不達証拠を整えて期日を前倒し
- 管理行為:最小限の修繕・清掃、近隣クレームの窓口、代金の区分管理(供託・専用口座)
判断のコツ
- 売却優先か保全重視かを最初に決める(雨漏り・傾斜・空き家条例があるなら売却許可優先)
- 金融機関の相続手続は支店ルールが細かい。書式・押印要件を事前確認してから申請
次の一歩
- ✅ 査定書・写真・費用見積りを一式で許可申請に添付
- ✅ 払戻しは使途(税・保存費)を明記して申請
- ✅ 公示送達の掲示期間と期日を家族カレンダーに共有
6〜12か月:分割成立・登記・売却・税務完了
後半戦は成果物の回収です。許可が降りたら売却・払戻しを実行し、遺産分割(調停・審判)をまとめて、相続登記・税務を締め切ります。
やること(仕上げ)
- 売買契約〜決済:決済チェックリスト(身分証・登記関係・残置物)で漏れゼロ
- 代金の区分管理:管理人口座や供託で入出金の見える化、台帳と照合
- 遺産分割の確定:調停成立・審判確定の正本・確定証明を取得
- 相続登記:協議書または審判書を添付して司法書士と申請
- 相続税申告:売却損益・費用を反映し、10か月以内を厳守
- 精算・報告:管理人の計算書・報告書で終局。立替費用を保存費用として整理
仕上げのチェックリスト
- ✅ 売却代金は混在禁止(私費口座と完全分離)
- ✅ 裁判所への報告は証票添付で信頼度アップ
- ✅ 税理士・司法書士の最終突合(金額・地番・名義)
まとめのひとこと(星川)
- 前半90日で“証拠と設計図”を作る。中盤で許可を抜き、後半で回収と登記。このリズムを守るだけで、迷いは激減します。
不動産があるときの実務:空き家管理と売却可否
相続人が行方不明でも、空き家管理と固定資産税の対応は待ったなしです。ここでは、最低限の損害防止(修繕・保険・近隣対応)、費用の管理、そして売却タイミングの判断軸を実務の順でまとめます。星川が現場で使うチェックを、そのまま型にしました。
管理義務・損害防止(修繕・保険・近隣トラブル予防)
空き家は「放置コスト」が見えにくいだけで、雨漏り・倒木・漏水・不法侵入など、損害の芽は日々育ちます。管理=リスクの先回り。まずは“今日できる対策”から。
最低限の初動(到着順)
- ✅ 鍵・境界・火災保険の三点確認(合鍵の回収・破損箇所の写真・保険の継続)
- ✅ 通水停止・ブレーカー遮断・水回り封水で臭気逆流と漏水を予防
- ✅ 外構の危険除去(倒れそうな塀・樹木の剪定・郵便物の止め)
- ✅ 近隣への連絡先掲示(ポスト内カード/玄関裏側など目立ちすぎない場所)
- ✅ 残置物は“保存”扱いで勝手に処分しない(写真→目録→保管)
定期管理の目安(星川の簡易カレンダー)
| 頻度 | チェック項目 | 具体行動 | 記録化のコツ |
|---|---|---|---|
| 毎月 | 外観・雨樋・ポスト | 落葉清掃・郵便停止の再確認 | 同アングルで定点撮影 |
| 季節ごと | 屋根・バルコニー・通気 | 雨漏り跡確認・窓開け30分 | before/afterを並べ撮り |
| 年1回 | シロアリ・配管 | 点検口確認・床下簡易チェック | 見積書・写真を台帳に綴じる |
保険・契約の見直し
- ✅ 火災+施設賠償のセットを確認(他人にケガをさせた場合の補償)
- ✅ 電気は契約容量を落とす/停止、ガスは閉栓、水道は止水
- ✅ 修繕は緊急度>美観の順で。雨漏り・破損・倒壊リスクから着手
ひと言メモ:「写真・日付・領収書」=あなたの“盾”です。後日精算や説明の根拠になります。
差し迫る固定資産税・維持費への対処
固定資産税は相続人不明でも毎年発生。支払いを止めると延滞と信用リスクが積み上がります。ここはキャッシュ管理×証票管理で粛々と。
費用の見える化テンプレ
| 費目 | 月額/年額の目安 | 支払い方法 | 台帳の記録欄 |
|---|---|---|---|
| 固定資産税 | 年額(通知ベース) | 口座振替or納付書 | 期別・領収印の写し |
| 保険(火災・賠償) | 年額 | 年払/分割 | 証券番号・更新日 |
| 点検・清掃 | 月〜季節単位 | 請求書払 | 事業者・作業写真 |
| 光熱(最小契約) | 月額小 | 口座振替 | 停止/縮小の控え |
運用のコツ
- ✅ 立替台帳を作り、支払日・金額・領収書を一枚に綴じる
- ✅ 払戻し許可が取れたら、保存費用として精算の根拠に充当
- ✅ 維持費が重い空き家は、短期許可→売却で保有期間を縮めるのが定石
星川の合言葉:「払う・記す・返してもらう」——この順で迷いが消えます。
売却タイミングと価格下落リスクの見極め
悩みどころはここ。今売るか、整えてから売るか。判断は価格×期間×リスクの三点で“数式化”して決めます。
判断フレーム(シンプル版)
- 現況査定A(現状のまま売る)
- 修繕後査定B(最低限の手当て後に売る)
- 費用C(修繕・維持・税の合計/売却までの予想期間)
- 差益= B − A − C がプラスなら手当て後売却、マイナスなら現況売却が合理的
よくあるケースの考え方
- 雨漏り・構造劣化が顕著:買い手の融資が通りにくい→現況 or 解体前提でスピード重視
- 外観だけ傷んでいる:軽微修繕+清掃+測量で内見数が増え、Bが上がりやすい
- 再建築不可・狭小・極端な郊外:市場の母数が少ない→価格感の合意形成を先に(複数査定+近隣成約で許可を通す)
価格下落のリスク管理
- ✅ 売却までの“保有日数コスト”を月額で把握(税・保険・管理)
- ✅ 梅雨・台風前に屋根・樋の応急処置(事故=値下げ要因)
- ✅ 測量・越境有無を先に確認(不確定要素は買い手の値引きカード)
実行ステップ(最短ルート)
- ✅ 査定2〜3本を同条件で依頼→相場レンジを掴む
- ✅ 売却許可の申請準備(必要性と価格相当性を資料化)
- ✅ 内見前の最低限の整え(清掃・通気・雑草除去・写真の見栄え)
最後に星川から:“完全な正解”はありません。だからこそ、数字で比較→小さく試す→早く決める。この順で、価格の迷いは減ります。
70歳当事者の負担を減らす工夫:代理・委任・情報整理の型
「やらなきゃ」と分かっていても、移動・役所・電話だけで一日が終わります。ここでは、代理・委任・情報整理の仕組みを先に作り、当事者の負担を3割カットする実務の型をまとめます。星川が現場で使うテンプレをそのまま使ってください。
委任状・受任範囲の設計と進捗管理
委任は「とりあえず一枚」では足りません。受任範囲の明記と進捗の見える化で、依頼側も受任側も迷いません。
委任の設計ポイント
- 目的の一行定義:「相続手続(探索・申立・許可・登記)に関する一切の事務」
- 範囲の具体化:役所請求、金融機関照会、裁判所申立、見積取得、費用立替の上限
- 期限と更新:3〜6か月で区切り、延長時はチェックリストで再合意
- 身分証の扱い:写しの保管場所、閲覧権限、返却期限
委任の分担マトリクス(例)
| 役割 | 主担当 | 代行可否 | 期限 | 完了確認 |
|---|---|---|---|---|
| 戸籍・附票の取得 | 親族代表 | 可能 | 〇月〇日 | 写しを共有フォルダ |
| 探索ログ作成 | 受任者 | 不可 | 毎週更新 | 週次報告で確認 |
| 家の管理(鍵/点検) | 親族A | 代行可 | 月1回 | 写真3枚提出 |
| 申立書ドラフト | 受任者 | 不可 | 〇月〇日 | PDF回覧で承認 |
| 予納金の手当て | 親族代表 | 可能 | 期日前 | 振込控え保存 |
進捗管理のコツ
- ✅ 週1回・15分の定例(電話/オンライン)で「やった/やってない」をだけ報告
- ✅ タスクは粒度を小さく(「戸籍取得」ではなく「本籍地Aへ郵送請求」)
- ✅ 期限前日アラートを家族カレンダーで自動化
書類・連絡ログ・費用台帳のテンプレ活用
「探した」「払った」を証拠化するのが後で効きます。テンプレ3点セットで“書く手間”を最小化しましょう。
1)書類フォルダの構成(そのまま真似してください)
- 01_戸籍_附票(PDF写し+取得日)
- 02_探索ログ(Excel/Googleシート)
- 03_財産目録(不動産/預金/証券/保険)
- 04_申立関連(ドラフト/受理書/補正)
- 05_許可申請(査定・写真・相場資料)
- 06_費用台帳(領収書PDF/通帳写し)
- 07_報告書・精算(提出版/証票)
2)探索ログ(1行テンプレ)
| 日付 | 先方 | 方法 | 要点 | 結果 | 添付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/05 | 旧勤務先 | 書面 | 在籍/退職時期照会 | 回答保留 | 送付控え |
3)費用台帳(保存費用の精算に直結)
| 日付 | 費目 | 金額 | 支払方法 | 根拠(請求書/許可) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/01 | 固定資産税(第1期) | 35,000 | 口座振替 | 納付書写し | 立替 |
| 2025/05/18 | 屋根応急修繕 | 66,000 | 振込 | 見積・写真 | 雨漏り対策 |
運用のツボ
- ✅ ファイル名は「日付_内容_差分」で統一(例:2025-05-18_屋根修繕_請求書.pdf)
- ✅ 写真は同アングルで撮影し、前後比較を作る
- ✅ 台帳は月末締め→家族へPDF自動送付
家族間連絡のルール化(代表者・頻度・意思決定)
揉め事の多くは情報の非対称から生まれます。最初に代表者・頻度・決め方を決めて、余計な摩擦を防ぎます。
最小限のルール例
- 代表者1名+副代表1名(病欠・旅行に備える)
- 定例連絡:毎週/15分(アジェンダ固定:「進捗3件・決裁2件・次週タスク」)
- 決裁ルール:原則全員合意、ただし保存費用・安全対策は代表者の即時判断可
- 議事の残し方:グループメール/チャットで要点3行+資料リンク
- 感情の交通整理:要望は事実・数字に翻訳して合意形成(例:「値下げ反対」→「査定A〜Cの中央値との差」)
合意形成のショートカット
- ✅ 争点は選択肢×根拠×期限で提示(例:「現況売却/軽微修繕/解体前提」+査定+申請期限)
- ✅ 反対意見は代替案とセットで(「修繕なら費用〜万円、完成〜日」)
- ✅ 既決事項はロック(ファイル名に「確定」タグ、後は変更理由と期日を記録)
星川からひとこと
- 人は“曖昧”に疲れます。だから最初に枠を決める。枠が決まれば、書類は自動的に埋まります。迷ったら、「誰が/いつまでに/何を」の3つだけ決めましょう。
仮想成功事例:行方不明の兄がいるケースで遺産分割と売却を実現
「兄が行方不明で、家も口座も動かせない……」。そんな状態から不在者財産管理人→許可→売却→分割まで到達した仮想事例です。選択肢の比較→意思決定→数値の見える化の順で、70歳の当事者でも無理なく進められる道筋を示します。
選択肢の比較検討と意思決定プロセス
前提
- 当事者:70歳の長男(実家の管理を担う)
- 行方不明:次男(連絡断絶8年)
- 遺産の主軸:自宅(築35年・空き家)、預金2口座
比較と結論(星川の伴走メモ)
- 失踪宣告:確定すれば早いが、7年待ちが現実的でない。
- 不在者財産管理人:2〜6か月で動かせる見込み。売却許可を取れば現金化が可能。
- 相続財産管理人:相続人は判明しているため過剰。今回は不採用。
意思決定の手順
- ✅ 探索の証拠化(附票・照会ログ・不達封筒)
- ✅ 家庭裁判所へ申立(不在者財産管理人)
- ✅ 売却許可を先行取得(老朽化と固定資産税の負担増を理由)
- ✅ 代金の区分管理→調停で配分枠を固める
具体的なスケジュール・費用・結果(数値例)
全体像(12か月以内の収束を狙う)
| 月数 | マイルストーン | 主要タスク | 費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 0〜1か月 | 申立準備 | 戸籍連続取得・附票・探索ログ整備 | 取得実費 約1〜2万円 |
| 1〜3か月 | 管理人選任 | 審理対応・就任・通帳/鍵の受領 | 収入印紙/郵券 数千円 |
| 2〜4か月 | 売却許可 | 査定3社・相場資料作成・許可申請 | 査定0円〜、郵券数千円 |
| 4〜6か月 | 売買実行 | 内見整備・契約・決済・代金区分管理 | 片付/清掃 10〜20万円 |
| 5〜8か月 | 調停成立 | 配分割合の合意・確定書取得 | 印紙/郵券 数千円 |
| 8〜10か月 | 相続登記 | 司法書士申請・名義整理 | 登記費用 5〜10万円 |
| 10〜12か月 | 税務完了 | 相続税申告(必要時)・精算報告 | 税理士報酬等 10〜30万円 |
数値の内訳(例)
- 不動産:路線価・近隣成約から2,700〜2,900万円の相場帯
- 選択:現況売却(軽微清掃のみ)。修繕見積15万円は費用対効果▲で見送り
- 売却価格:2,800万円
- 諸費用(概算):仲介手数料約96万円、登記等10万円、清掃15万円
- 管理人関連:予納金30万円、報酬見込40万円(終局時裁判所決定)
- 結果:
- 代金2,800万円を管理人口座で区分
- 調停で「長男:次男=1/2ずつ」を確定(法定相続)
- 長男へ一時立替の保存費用(固定資産税・清掃)を先に精算
- 相続登記完了→税務申告まで12か月で収束
効果
- 固定資産税の将来負担を遮断
- 空き家リスク(漏水・倒壊)を早期に解消
- 現金化により医療・介護資金を確保
つまずきポイントと回避策
つまずき①:許可申請で「価格の相当性」説明が薄い
- 回避:査定2〜3本+近隣成約の写し+路線価で三点支持。内見写真も添付
つまずき②:金融機関の相続手続きが支店ごとに違う
- 回避:事前に必要書類一覧を取り寄せ、押印・委任形式まで確認。期日前に窓口プレチェック
つまずき③:家の残置物で決済が遅延
- 回避:売買契約前に残置物合意条項を入れるか、計量ごみ搬出の見積を契約書に添付
つまずき④:家族間の合意形成が停滞
- 回避:争点を「選択肢×根拠×期限」で提示。反対には代替案をセットで求める
つまずき⑤:管理人報酬・実費の精算で揉める
- 回避:立替台帳+証票でガラス張り運用。報酬は裁判所決定額を基準に
星川からのまとめ
- 結論ファースト:「今回は管理人→許可→現況売却が最短」。数字で腹落ちすれば、70歳の肩の荷は確実に軽くなります。迷ったら、“今月の一手”を一行で書き出してください。そこから次が決まります。
よくある質問(Q&A)
「相続人が行方不明のまま、何をどこまでやれば良いのか」。迷いやすいポイントを制度名の一言補足つきで整理します。星川が実務で頻出する質問に、結論→理由→次の一歩の順でお答えします。今日の不安を、ここでひとつずつ消していきましょう。
何年待てば失踪宣告できる?不在者財産管理人で代替できる?
結論:原則7年(普通失踪)。災害・事故などは1年(特別失踪)。ただし、待てない期間は不在者財産管理人で代替し、売却や払戻しは裁判所の許可で動かせます。
理由:失踪宣告は「死亡とみなす制度」。一方で不在者財産管理人は「本人が生きている前提で財産を守る代理」。
次の一歩:
- ✅ 7年に満たない→管理人選任+許可申請の準備へ
- ✅ 7年超え・災害等の心当たり→宣告申立の要件整理(最終消息の立証)
探索はどこまで必要?どの程度で“尽くした”といえる?
結論:公的資料+民間照会+不達証拠が時系列で揃い、反応ゼロまたは所在特定不能を示せれば、実務上「尽力」と評価されやすいです。
目安(チェック3点):
- ✅ 公的:戸籍連続・住民票/附票・不在住不在籍証明
- ✅ 民間:親族・旧勤務先・管理会社・ライフラインへの複数経路照会
- ✅ 形式証拠:不達封筒・受領拒否・メールヘッダー・捜索願の受理番号
コツ:同一先へは手段と時期を変えて2回以上。質問は事実のみ(最終連絡時期・退去日など)。ログは1行テンプレで。
売却代金はどう保管する?配当はいつ可能?
結論:売却や払戻しで得た金銭は、管理人の区分口座や供託で厳格に分けて保管。配当(分配)は、調停成立・審判確定など“根拠が確定”してから実施します。
運用の型:
- ✅ 代金受領:管理人名義の専用口座に入金(私費と混在禁止)
- ✅ 保管:通帳・入出金台帳・根拠資料を紐づけ管理
- ✅ 配当開始:①遺産分割調停成立または審判確定、②相続財産管理人事件なら配当手続の公告・確定後
注意:保存費用(固定資産税・応急修繕・保険)は相続財産の保存費用として、証票添付で先行精算が可能です。
途中で行方不明者が見つかったらどうなる?
結論:不在者財産管理人の職務は原則終了方向。以降は本人の意思確認のうえ、協議・登記・精算をやり直す(または続行)ことになります。
ケース別の流れ:
- ✅ 管理人選任中に発見:本人が連絡可能なら協議に復帰。未了の売却等は必要なら再許可や条件調整
- ✅ 失踪宣告確定後に生存判明:宣告の取消しや権利回復の調整が生じ得ます(登記や分配の再調整が必要な場合あり)
実務の備え: - ✅ 区分管理と書面化(台帳・契約書・許可書)で透明性をキープ
- ✅ 連絡再開後の本人確認手順(身分証・署名・印鑑証明)をチェックリスト化
まとめ:相続人行方不明でも止めないための最短ルート
「どこから動けばいいか分からない」。その迷いを断つには、順番と根拠を決めることです。まずは証拠化→裁判所ルート→許可→実行。当面の現金確保か、長期確定かで手段の主軸を選べば、今日から一歩進みます。星川が最後に道筋をもう一度、短く置いておきますね。
ケース別の使い分け指針(当面の現金化/長期見据え)
- 当面の現金化が最優先
- 不在者財産管理人+許可申請を主軸に。
- 先にやること:探索の証拠化→申立→複数査定→売却・払戻しの必要性を資料化。
- 現金は区分口座・供託で厳格管理、保存費用の精算を並走。
- 長期の法的確定を重視
- 失踪宣告(普通7年/特別1年)で死亡擬制を得て、以後の手続を軽くする。
- 先にやること:最終消息の立証、公告や証拠の準備、宣告後の登記・解約計画を先読み。
- 管理者が不在/相続人多数不明
- 相続財産管理人で一体管理・換価・配当。空き家や債務対応を中立処理。
- 書類が届かず止まる
- 公示送達で期日を動かす。不達封筒・照会履歴の束を用意。
- 迷ったら
- 判断軸は期間×費用×リスク(価格下落・事故・税期限)。
- 数字で比較し、小さく試す→早く決めるが正解に近道。
迷ったら「証拠化→申立→許可取得」の王道手順
- 証拠化
- 戸籍連続・附票・不在住不在籍+民間照会ログ+不達証拠を時系列で束ねる。
- 空き家は写真・見積・事故リスクを数字で表現。
- 申立(不在者財産管理人を軸に)
- 申立書に目的を一行(保全/換価/配分)で明記。
- 予納金と管轄は事前照会、補正ゼロで通す。
- 許可取得(処分行為)
- 必要性×価格相当性を複数査定・近隣成約・路線価で三点支持。
- 払戻しは使途(税・保存費)を明示、代金は区分管理。
- 実行・精算
- 売却・払戻し→調停または審判確定→相続登記→税務の順で一直線。
- すべて台帳・証票で見える化し、後日の発見・異議にも耐える運用に。
- 続けるための最小ルール
- 週1・15分の定例/代表者制/「誰が・いつまでに・何を」の3点固定。
- 迷ったら、この順番に戻る——順番が解決の9割です。