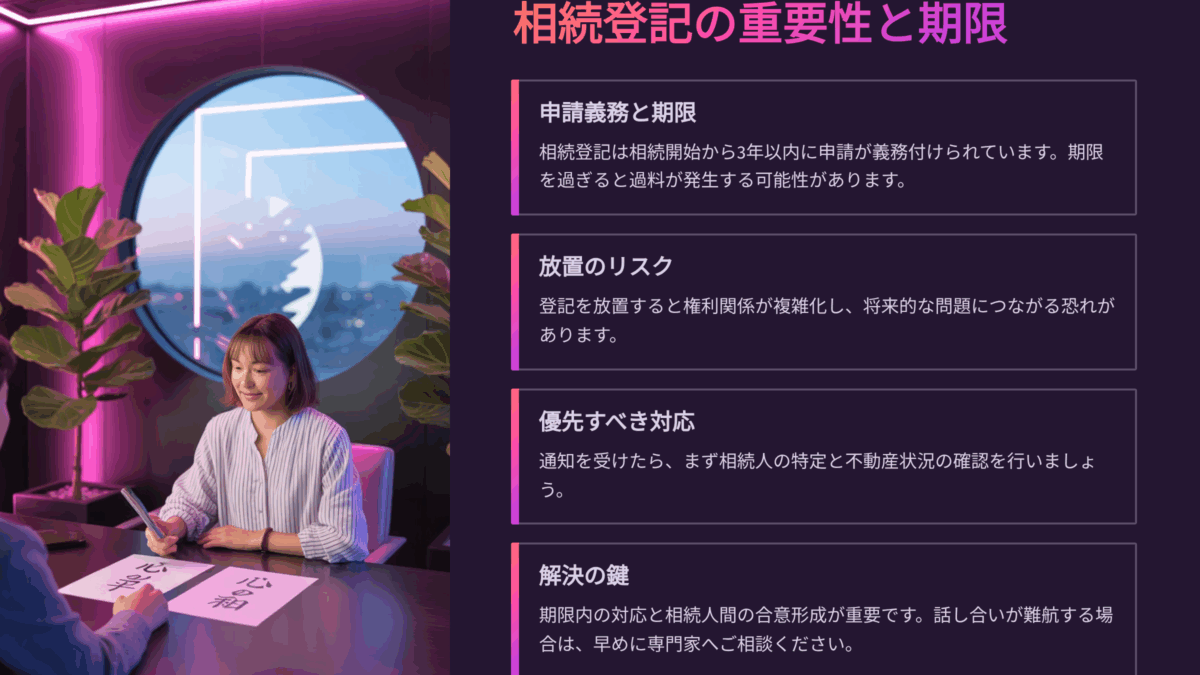相続登記を長年放置すると、ある日突然法務局から通知が届きます。慌てずに正しい対応を知ることが解決の第一歩です。目次を見て必要なところから読んでみてください。
法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたら
相続登記を長く放置してしまうと、ある日突然法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届くことがあります。
あなたも今、この通知を手にして戸惑っているかもしれませんね。
まず知っていただきたいのは、この通知はあなたを責めるものではなく、現状を整理して進めるきっかけだということです。
ここでは、なぜ通知が届くのか、その背景と法的根拠からお話しします。
通知が届く背景と法的根拠
この通知は、2024年4月から始まった相続登記の義務化制度と密接に関わっています。
これまで相続登記は任意でしたが、相続開始(亡くなられてから)3年以内に登記をしないと過料(罰金のようなもの)が科されるようになったんです。
法務局は、登記簿を見て長期間相続登記がされていない土地や建物を把握できます。
その中で、「持ち主が亡くなってから何十年も手続きが進んでいない」物件に対し、所有者の関係者へ通知を送ることがあります。
✅ ポイント
- 通知は「義務化されたからすぐ罰金」という意味ではない
- あくまで現状確認と手続き促進のための連絡
- 無視すると、将来的に売却・利用ができなくなる恐れあり
私の経験上、この通知を受けた方の多くが「なんで今になって?」と驚かれます。
でも裏を返せば、今はまだ自分で動ける段階だということ。
手遅れになる前に、一歩踏み出すタイミングなんです。
登記放置による現状のリスクとは
相続登記を放置していると、静かに問題が積み重なっていきます。
その多くは、表面化するまで気づきにくいのが怖いところです。
まず、時間が経つと相続人がどんどん増えてしまうという現象が起こります。
例えば、兄弟姉妹の一人が亡くなると、その人の子どもたち(甥や姪)が新たな相続人になります。
結果として、数年後には「話し合う人数が倍以上」になることも珍しくありません。
さらに、登記を放置している間に
- 土地を売ることができない
- 家のリフォームや賃貸契約ができない
- 固定資産税だけを延々と払い続ける
といった状態に陥ります。
場合によっては、誰かが滞納した税金のために差し押さえされるケースもあります。
「うちは大丈夫」と思っていた方でも、相続人の一人が知らない間に借金を抱えていた…という話は実際にありました。
私がこれまで関わった案件でも、20年以上放置していた結果、相続人が20人以上に膨らみ、手続きだけで2年かかった例があります。
正直、その間の精神的な負担は相当なものでした。
✅ まとめると
- 時間が経つほど、相続人が増えて調整が困難に
- 不動産の利用・売却ができない
- 思わぬ債務や差し押さえリスクがある
だからこそ、この通知が届いた今が「最後の整理のチャンス」だと、私は強く感じています。
通知を受けた後にまず確認すべきこと
通知が届いたら、まず落ち着いて、現状を正しく把握することが大切です。
焦って手続きを始める前に、「誰が相続人なのか」「どんな不動産が対象なのか」を整理しておくことで、無駄な動きや二度手間を防げます。
ここでは、最初に行うべき2つの確認ポイントをお伝えします。
「法定相続人情報」の取得と活用法
相続登記を進めるうえで、「誰が相続人なのか」を正確に把握することが第一歩です。
戸籍を集めれば調べられますが、これが意外と大変。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を全てそろえる必要があるため、役所を何度も回ることになります。
そこで活用できるのが、「法定相続情報一覧図」という制度です。
これは、法務局に必要な戸籍を提出して作成してもらう公的な一覧表で、相続人全員の名前と続柄が一目でわかります。
✅ この一覧図を作っておくメリット
- 何度も戸籍を提出しなくてもよくなる
- 銀行や不動産の手続きでもそのまま使える
- 相続人全員に同じ資料を配れるので、話し合いがスムーズになる
私がサポートした方も、この一覧図を先につくったことで「もう戸籍集めに振り回されなくて済んだ」とホッとされていました。
まずはこれを整えることで、全員が同じスタートラインに立てます。
不動産の特定と登記事項証明書の確認
次に行うべきは、対象となる不動産がどこで、どんな状態になっているのかを正確に把握することです。
通知に書かれている物件がすべてとは限らず、他にも未登記の不動産があるケースもあります。
そのため、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して確認します。
法務局やオンライン申請で取得でき、現在の名義人や土地の面積、地目などが分かります。
✅ 確認するポイント
- 名義人が亡くなった方のままになっていないか
- 権利関係(持分割合)が複雑になっていないか
- 地目や面積に誤りがないか
不動産を特定することで、「誰と誰が話し合う必要があるのか」「土地をどう分けるのか」といった具体的な計画が立てやすくなります。
特に、相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合は、この確認が後々のトラブル回避につながります。
選べる対応パターンと判断ポイント
通知を受け取った後は、「とにかく登記をしなければ」と思いがちですが、実は選べる道はいくつかあります。
相続登記を進めるのか、放棄を選ぶのか、期限を守るための動き方を整理することで、自分や家族にとって最適な方法を選びやすくなります。
ここでは、代表的な3つのパターンとその判断ポイントをお話しします。
相続登記を進めるメリットとステップ
相続登記を進める最大のメリットは、不動産の名義を明確にし、自由に活用できる状態にできることです。
名義があなたや家族に変われば、売却・賃貸・建て替えといった選択肢が一気に広がります。
登記完了までの基本ステップは次の通りです。
✅ 相続登記の流れ
- 法定相続人を確定(法定相続情報一覧図の作成)
- 不動産の特定(登記事項証明書を取得)
- 遺産分割協議(全員の合意が必要)
- 必要書類の収集(印鑑証明書・住民票など)
- 法務局で相続登記の申請
特に、遺産分割協議の合意形成が時間のかかる部分です。
早めに声をかけ合っておくことで、期限内にスムーズに手続きできます。
相続放棄を検討する場合の注意点と期限
相続登記をせず、相続放棄を選ぶという道もあります。
これは「不動産も含めて、一切の財産を受け取らない」という意思表示です。
借金や管理負担が大きい不動産の場合、この選択が有効なこともあります。
ただし、注意すべきなのは期限と範囲です。
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
そして一度放棄すると、プラスの財産も含めて全て受け取れなくなるため、事前に全体像を確認することが大切です。
私がサポートしたケースでは、「借金があると聞いたので放棄したけれど、実は価値のある土地もあった」という方がいました。
判断を急ぐ前に、専門家や家族と十分に話し合うことをおすすめします。
遅延時のペナルティ(過料制度)と対応期限
2024年4月から、相続登記は相続開始から3年以内に申請する義務ができました。
これを過ぎると、10万円以下の過料(行政罰)を科される可能性があります。
✅ 注意すべきポイント
- 過料は「刑罰」ではないが、支払義務が発生する
- 「知らなかった」では免除されない
- 3年以内に一度申請すればOK(途中で協議中でも申請可)
実務的には、3年の期限が近づく前に法定相続情報一覧図の作成や、仮の登記申請で期限を守る動きも可能です。
「時間が足りない」と思ったら、まずは法務局や司法書士に相談し、間に合わせる方法を探すことが大切です。
登記放置による将来的なリスクとは?
「今は急がなくてもいいか」と思って登記を後回しにすると、数年後、想像以上にややこしい状況になってしまうことがあります。
ここでは、私が実際に見てきた事例を交えながら、登記放置がもたらす3つの大きなリスクをお伝えします。
知っておくことで、後々の後悔や余計な出費を防ぐことができます。
相続人の増加による権利関係の複雑化
時間が経つほど、相続人はどんどん増えます。
兄弟姉妹が亡くなれば、その子ども(甥や姪)が新たな相続人になり、さらにその人たちが亡くなれば…と、「権利の枝分かれ」が続くのです。
例えば、最初は相続人が4人だった土地でも、20年放置すると20人以上に膨れ上がることがあります。
結果として、
- 遺産分割協議に全員の同意が必要
- 連絡が取れない相続人が出てくる
- 誰がどの持分を持っているか分からなくなる
という事態が起こります。
私が関わった案件でも、相続人の数が増えすぎて調整に2年以上かかり、その間は一切土地を動かせませんでした。
不動産の売却や活用が困難になるリスク
相続登記が終わっていない不動産は、基本的に売却も賃貸もできません。
また、担保に入れて融資を受けることも不可能です。
つまり、資産としての価値を活かせないまま固定資産税だけがかかる状態になります。
特に地方の空き家や農地は、放置すればするほど需要が減り、価値が下がっていきます。
結果的に、「もっと早く手続きしておけば良かった」という声を本当に多く聞きます。
✅ 売却・活用できないことによる影響
- 固定資産税の負担が続く
- 草刈りや修繕などの管理費用がかかる
- 放置により劣化・価値低下が進む
債権者による差し押さえ・管理責任などの思わぬ負担
さらに怖いのが、相続人の誰かが抱える借金や税金滞納が原因で、あなたの知らない間に不動産が差し押さえられる可能性です。
共有名義の不動産では、一部の持分だけでも差し押さえの対象になり得ます。
また、空き家や空き地を放置して近隣に迷惑をかけると、管理責任を問われることもあります。
台風で屋根が飛んだ、倒木で隣の家を傷つけた…そんな場合、修繕費や賠償責任が発生することも珍しくありません。
私が知っている事例では、登記を放置していた家が台風で一部崩れ、修繕費の分担で相続人同士が揉めに揉め、結局裁判にまで発展しました。
手間もお金も、想像以上にかかります。
ケース別対応の実務ポイント(兄弟間トラブル対策含む)
相続登記は「書類を出すだけ」と思われがちですが、実際は相続人同士の合意形成が一番の山場です。
特に兄弟姉妹間では、お金や思い出が絡んで感情的になりやすく、話が止まることもあります。
ここでは、私が現場で培った「スムーズに進めるための実務的な工夫」をお伝えします。
連絡をとる際の文面や進め方の工夫
相続人への連絡は、最初の一歩で印象が決まるといっても過言ではありません。
いきなり「登記しよう」「書類にハンコを」と迫ると、警戒心を持たれてしまいます。
✅ 連絡文面のポイント
- まずは現状共有(法務局から通知が届いたこと、登記放置の影響)
- 感情的な表現を避け、事実ベースで伝える
- 「急ぎではないけれど、早めに動く方がみんなにとって良い」と柔らかく促す
例えば、私がよく使う文面の一部はこんな感じです。
「法務局から登記に関するお知らせが届きました。
このままにすると将来困ることになる可能性があるので、一度話し合いの場を持ちたいです。
無理のない形で進められるように考えています。」
こうして「敵ではなく同じ方向を向く仲間」という雰囲気を作ることが大切です。
全相続人の同意取得と遺産分割協議の進め方
相続登記は、原則として全相続人の同意がなければ申請できません。
このため、遺産分割協議書に全員の署名と実印が必要になります。
進め方のコツは、
- 法定相続情報一覧図で全員を把握
- 個別に現状と必要性を説明
- 合意形成後に協議書案を作成
- 修正点があれば柔軟に対応
重要なのは、「一斉送信」や「全員集めて一度に話す」よりも、一人ずつ順番に合意を取り付ける方がスムーズな場合が多いということです。
特に最初の1〜2人が賛成してくれると、その後の合意率がぐっと上がります。
専門家(司法書士)に依頼すべきタイミングと判断基準
司法書士への依頼は、「もう自分たちだけでは難しい」と感じた段階がタイミングです。
特に以下のケースでは、早めの依頼が有効です。
✅ 依頼を検討すべき場面
- 相続人の人数が多い(5人以上)
- 連絡先が分からない相続人がいる
- 相続人の一部が海外在住
- 遺産分割協議で意見が割れている
- 書類の準備や法務局への申請が負担
司法書士は、戸籍集めから協議書作成、登記申請まで一括で代行できます。
「手間を減らしたい」「感情的なやり取りを避けたい」場合にも心強い存在です。
兄弟間の相続トラブルは、一度こじれると長引きやすいものです。
だからこそ、最初の連絡・説明・合意形成の流れを丁寧に作ることが、最短での解決につながります。
まとめ(次にすべき具体的アクション)
法務局からの通知は、驚きや不安を与えるかもしれません。
ですが、「まだ自分で動ける段階」だからこそ届いたサインだと受け止めてください。
放置すれば、相続人の増加や不動産価値の低下、思わぬ負担が待っています。
逆に、今動けばこれらのリスクを最小限に抑えることができます。
✅ 今すぐできる3つのアクション
- 法定相続情報一覧図を作成し、相続人を確定する
- 登記事項証明書を取得して、不動産の現状を把握する
- 相続人同士で連絡を取り合い、方針(登記か放棄か)を決める
この3つを押さえるだけで、手続きは半分以上進んだも同然です。
そして「期限が迫っている」「話が進まない」と感じたら、司法書士などの専門家に早めに相談してください。
一人で抱え込む必要はありません。あなたと同じような状況を乗り越えた人はたくさんいます。
私もこれまで何百件と相続登記に関わってきましたが、早く動き出した方ほど、時間もお金も節約でき、家族関係も穏やかに保てたと感じています。
次の一歩は、あなたの行動から始まります。