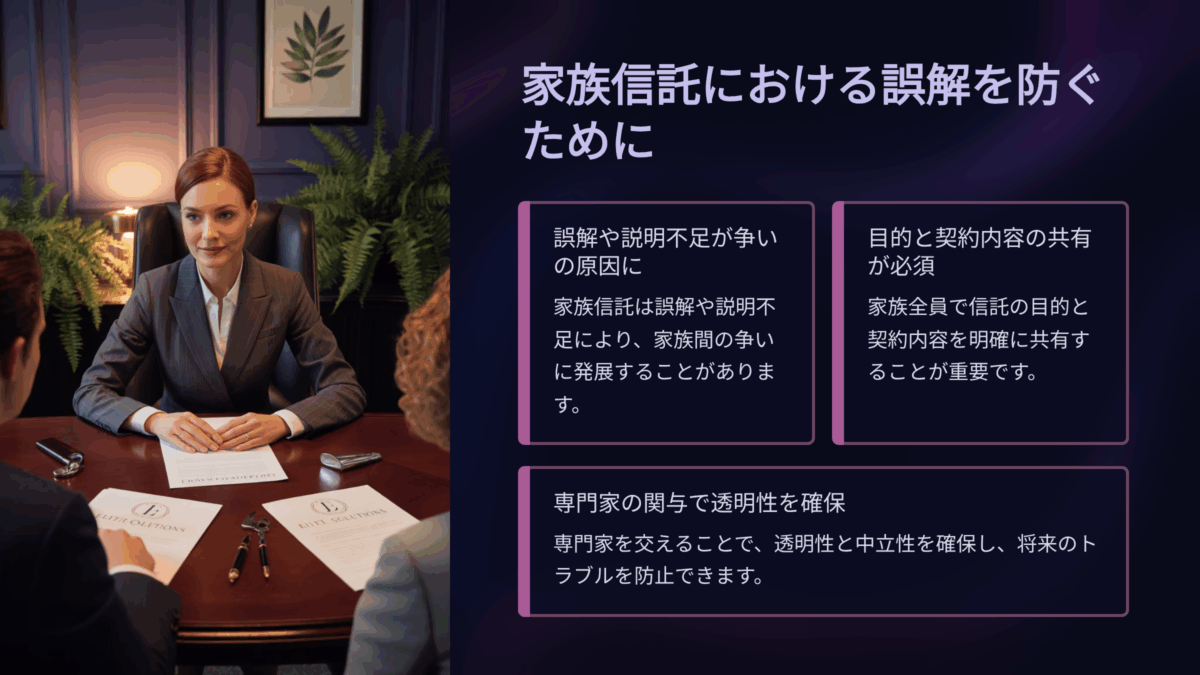家族信託は安心のための制度ですが、誤解や説明不足で争いに発展することもあります。実例と防止策をわかりやすく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
高齢者が家族信託を選ぶ背景とポイント
「家族信託って、良いって聞くけど、本当に自分に合うのか…?」そう感じる方は少なくありません。特に70歳を過ぎる頃からは、相続や認知症による財産管理の不安が現実味を帯びてきます。この章では、73歳という人生の段階で家族信託が検討される背景や、その選択のポイントを、実務で見てきた視点からお話しします。
家族信託とは?基本のしくみと目的
家族信託とは、自分の財産の管理や運用、処分を、信頼できる家族に託す仕組みのことです。
たとえば、将来自分の判断力が落ちたときに、口座の解約や不動産の売却が必要になっても、信託契約で任された家族が代わりに手続きを進められます。
✅ 家族信託の主な目的
- 認知症になっても財産の管理や売却が止まらないようにする
- 遺言書ではできない柔軟な財産承継の設計ができる
- 家族間での財産トラブルを予防する
ただ、制度の仕組みや権利関係をしっかり理解していないと、「財産を取られるのでは」という誤解や感情のすれ違いが起こることもあります。私の経験上、この“誤解”こそが、家族信託トラブルの火種になることが多いんです。
73歳という年齢で信託を選択する理由(相続・認知症対策などを含めて)
73歳前後で家族信託を選ばれる方には、いくつか共通する背景があります。
- 相続を見据えての準備
「自分の代で整理しておきたい」という想いが強くなる時期です。 - 健康や判断力への不安
医師からの健康診断結果や日常の物忘れをきっかけに、将来の備えを急ぐ方が増えます。 - 子ども世代への負担軽減
相続や財産管理の手間を子どもに背負わせたくないと考える親心があります。
実際に、私がご相談を受けた73歳の方は、「遺言だけじゃ足りない気がして…」とおっしゃっていました。遺言書は“亡くなった後”の効力ですが、家族信託は生きている間の管理と承継をカバーできる。この違いが、選択の決め手になることが多いです。
次の章では、この「信頼」が思わぬ形で「争い」に変わってしまう瞬間について、実例を交えてお話しします。
“信頼”が“争い”に変わる、その瞬間
家族信託は「家族の安心」を守るための制度です。ですが、少しの説明不足や思い込みが、信頼関係を一気に壊してしまうこともあります。ここでは、私が実務で見てきた“信託が争いに変わる瞬間”を、実際の相談事例をもとに解説します。
娘が激怒した具体的な誤解とは
73歳の女性が、自宅と預金を息子に受託者として託す契約を結びました。母としては「管理をお願いするだけ」という感覚でしたが、契約書を見た娘が一言。
「これ、息子に全部あげるってことやん!」
実は、契約の中で“受益者変更権”の説明が不十分だったことが原因でした。受益者(財産から利益を受ける人)を変えられる権利が息子に渡っていたため、娘は「自分が財産から外されるかもしれない」と不安になったのです。
✅ 誤解の背景
- 契約文が法律用語だらけで理解できなかった
- 家族全員への事前説明がなかった
- 信託内容を「遺言と同じ」と思い込んでいた
こうした誤解は、事前に全員で話し合い、契約内容をわかりやすく共有していれば防げた可能性が高いです。
信託トラブルに共通する「すれ違いの構図」
家族信託の争いは、内容の善し悪しよりも“伝え方”と“共有不足”が原因になることが多いです。私が関わった案件でも、ほぼ同じパターンで起きています。
- 親の思いと子の理解がズレる
親は「安心のため」、子は「財産の分配のため」と認識している。 - 契約書の中身が理解されていない
難しい条文の意味を誰も噛み砕いて説明していない。 - 第三者の目が入っていない
家族内だけで決めた結果、感情的な偏りが残る。
この“すれ違い”は、制度そのものではなく、家族間のコミュニケーション不足が根本原因です。だからこそ、契約前の「家族会議」と第三者の関与が欠かせないんです。
このあと、トラブルを防ぐための具体的なステップについてお伝えします。
トラブルを防ぐための基本ステップ
家族信託は、やり方さえ間違えなければとても心強い制度です。ただし、準備の過程での「ひと手間」を惜しむと、後々の争いの火種になることがあります。ここでは、実務で私が必ずお伝えしている、トラブル予防のための基本ステップをご紹介します。
事前に話し合う“透明性”の確保ポイント
信託の内容を決めるときは、契約当事者だけでなく将来関係する可能性のある家族全員に説明する場を持つことが重要です。
私がご提案する流れはこうです。
✅ 家族会議の進め方
- 契約の目的を先に共有する
「管理のためなのか、相続のためなのか」をはっきりさせる。 - 対象財産と管理方法を具体的に説明
不動産や預金など、どれをどう管理するのか。 - 決定までの過程を全員に見せる
「勝手に決められた」という感覚を防ぐ。
こうして透明性を確保しておくことで、「そんなつもりじゃなかった」という感情的な衝突を避けられます。話し合いの場には、できれば専門家も同席し、用語や手続きをその場で解説してもらうと安心です。
信託契約書の文言チェックで避けられる誤解
契約書は、専門用語の意味を理解せずにサインしてしまうのが一番危険です。たとえば「受益者変更権」「残余財産帰属権」など、法律特有の言葉が誤解を招くことがあります。
✅ 文言チェックのコツ
- 一文ごとに「これは誰の権利・義務なのか」を確認する
- わからない言葉は必ずその場で質問する
- 家族にも同じ説明を共有する
私の経験では、「条文の意味を家族が全員で理解できた案件」は、その後のトラブル発生率がぐっと下がります。契約書は形式ではなく、家族全員が納得できる“説明書”として仕上げることが何より大切です。
次の章では、こうした準備をどう実務に落とし込むか、具体的な対応策をご紹介します。
実際の悲劇を防ぐための対応策
家族信託のトラブルは、「契約の中身が悪かった」よりも進め方が悪かったことが原因で起こるケースが多いです。ここでは、私が現場で実際に行っている“争いを防ぐための進め方”をお伝えします。準備段階でこれを押さえておくことで、後々の火種を大幅に減らせます。
第三者専門家(司法書士・税理士)を交えた進め方
家族内だけで信託を決めると、どうしても感情や立場に偏りが出ます。だからこそ、中立の立場に立てる専門家を間に入れることが大事です。
✅ 専門家を交えるメリット
- 法律や税務の観点から契約内容を多角的にチェックできる
- 家族間で説明が難しい部分を第三者が噛み砕いて説明できる
- 将来の税金や不動産手続きまで見通して設計できる
私の現場感覚では、司法書士と税理士の2名体制で関わった案件は、契約後の“予期せぬ問題”がほぼゼロでした。
感情的な対立を“対話”に変えるコミュニケーション法
家族信託は、制度の正確さだけでなく家族の感情ケアも同じくらい重要です。特に、兄弟姉妹など複数の相続人候補がいる場合、感情のもつれが制度以上に複雑さを増します。
私が意識しているポイントは3つです。
- 感情を否定せずに受け止める
「そんなこと言わないで」ではなく、「そう感じるんですね」とまず共感する。 - 制度説明の前に背景を聞く
不安や不信感がどこから来ているのかを掘り下げる。 - 合意形成は“結論ありき”にしない
時間をかけても、全員が納得する形を目指す。
こうしたステップを踏むことで、険悪な空気が少しずつ“対話”に変わります。
家族信託は、契約書を作るだけでなく、家族の関係性を守るプロセスでもあるんです。
次の章では、家族信託にまつわるよくある疑問と、その誤解を解くポイントをお話しします。
Q&A:よくある疑問・誤解とその対処
家族信託を検討するとき、多くの方が共通して抱く不安や疑問があります。ここでは、実際の相談現場でよく受ける質問を取り上げ、その背景と正しい理解のポイントをお伝えします。
「信託=資産を取られる」が誤解な理由
「家族信託って、受託者に財産を全部渡すってことやろ?そしたら取られてしまうやん…」という声をよく聞きます。
結論から言うと、信託は“所有権の名義”が移るだけで、受託者が勝手に使えるわけではありません。
✅ 誤解が生まれる背景
- 契約書上「所有者」が受託者になるため、財産を譲ったと勘違いする
- 「名義変更=贈与」というイメージが先行してしまう
- 受益者という“利益を受け取る人”の存在が理解されていない
信託では、あくまで契約書に沿って財産が管理され、受益者の利益のためだけに使われます。もし受託者が勝手に処分すれば、それは契約違反であり、法的な責任を問われます。
認知症になった後も安心して管理し続けられるのか?
「契約しても、認知症になったら全部止まるんじゃないの?」という不安も多いです。
家族信託の大きな特徴は、認知症になっても財産の管理や売却が継続できることです。
通常、本人が認知症になると銀行口座の凍結や不動産売却の制限がかかります。しかし信託では、受託者が契約に基づき管理を続けるため、
- 医療費や介護費の支払い
- 必要な資産の売却や運用
なども滞りなく行えます。
私の経験でも、契約後に認知症が進んだ方のケースで、受託者がスムーズに介護費用を捻出できた事例は珍しくありません。
つまり、正しく設計された信託は、将来の生活資金や介護資金の確保にも大きく役立つんです。
このあとのまとめでは、家族信託を“信頼を守る制度”として活かすための本質を整理します。
まとめ:信頼を守る家族信託のあるべき姿
家族信託は、家族の安心と未来の暮らしを守るための強力な仕組みです。しかし、その力を発揮できるかどうかは、契約内容そのものよりも、家族間の理解と合意のプロセスにかかっています。
私がこれまでの現場で感じてきた“信頼を守る信託”のポイントは、次の3つです。
✅ 目的を明確にすること
「なぜ信託をするのか」を家族全員が同じ言葉で説明できる状態にする。
✅ 全員で理解すること
契約書の内容や専門用語は、家族会議で共有し、疑問はその場で解消する。
✅ 第三者を交えて進めること
司法書士や税理士など、中立の立場の専門家を入れて感情の偏りを防ぐ。
家族信託は“契約”であると同時に、“家族の関係性を未来へつなぐためのプロジェクト”です。
制度を上手に使えば、将来の不安が「安心」に変わります。逆に、説明不足や思い込みがあれば、「信頼」が「争い」に変わることもあります。
あなたのご家族にとって、信託が争いを避けるための橋となるのか、それとも溝を深めるきっかけになるのかは、今日の準備で決まります。
まずは一度、家族全員で本音を話し合う時間を持ってみてください。それが、信頼を守る第一歩になります。