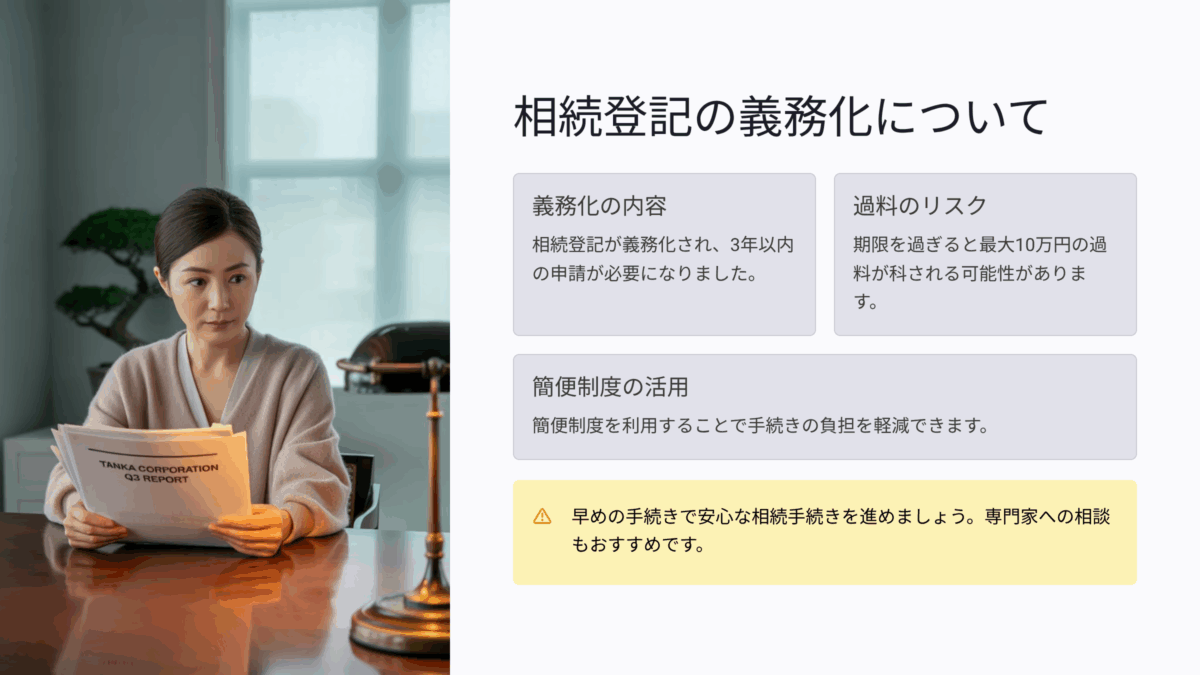相続登記の義務化って何をすればいいの?と不安な方へ。いつまでに、どんな手続きを、どう進めればいいかをわかりやすく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
相続登記義務化とは何か【制度の概要】
「相続登記の義務化」という言葉、最近ニュースなどで耳にするようになったけれど…正直、ピンとこないという方も多いのではないでしょうか。
でも実はこれ、相続した土地や建物の登記を「やらなければいけない制度」として、2024年4月から始まったばかりの重要な変更なんです。
この記事では、私たち“めーぷる岡山中央店”の立場から、制度の背景と内容を、できるだけかみくだいてお伝えしますね。
義務化の背景:所有者不明土地対策と社会的な課題
「親が亡くなったけれど、家や土地の名義を変えずにそのままにしている」というケース、実は全国にたくさんあります。
これまでは、相続登記をしていなくても罰則がなかったため、「いつかやろう」と後回しになってしまう人も多かったのが現実です。
しかしこの“登記されない土地”、いざ売ったり貸したりしようとしたときに、手続きが非常に面倒になったり、場合によっては使えなくなったりすることもあります。
こうした問題が全国的に広がっており、結果として「所有者が分からない土地」が増え、災害対策や公共事業の妨げになることもありました。
このような社会的課題を解決するために、「相続登記の義務化」という新しいルールが導入されたのです。
✅【できること】
・親の名義のままの不動産がないか、一度チェックしてみましょう
・相続登記をしていない場合、手続きを急ぐ必要があります
制度施行日と遡及適用の対象範囲
この相続登記の義務化制度は、2024年4月1日から施行されました。
ポイントは、これからの相続だけでなく、過去の相続にも遡って適用されるという点です。
つまり、「うちはもう10年前に親が亡くなっているから関係ない」とは言えません。
2024年4月の時点で登記がされていない場合、その日から3年以内に登記を完了させる義務があるのです。
| 制度概要 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2024年4月1日 |
| 義務の内容 | 不動産を相続した場合、3年以内に登記を行うことが法律で義務付けられる |
| 対象 | 施行日より前の相続も対象(ただし2024年4月1日を起点に3年以内) |
| 違反した場合 | 正当な理由がなく義務を果たさないと、10万円以下の過料が科される可能性あり |
制度としては非常にシンプルですが、これまで「やらなくても困らなかった」ことが「やらないと罰則がある」ルールへと変わったというのが大きなポイントです。
✅【次の一歩】
・相続した不動産が登記されているか法務局で確認を
・自分で難しい場合は、司法書士や専門業者に相談をおすすめします
義務化により“何をしなければならないか”(手続き・期限)
相続登記が義務化されたとはいえ、「具体的に自分は何をしなければいけないのか?」が分かりづらいという声をよくいただきます。
この章では、どのような場面で、どのような期限までに手続きをすべきか、具体的にお伝えします。特に期限の起算点(いつから数えるのか)は見落としやすいポイントですので、しっかり押さえておきましょう。
相続または遺贈で不動産を取得したことを「知った日」から3年以内に登記申請する義務
新しいルールでは、土地や建物を相続や遺贈(遺言などによる譲渡)で取得した人は、そのことを「知った日」から3年以内に登記を申請しなければならないとされています。
ここで言う「知った日」とは、一般的には相続が発生した日=亡くなった日と考えられます。
ただし、遺言書が後から見つかったり、法定相続人ではない人が遺贈を受けた場合などは、内容を把握した日が起算点になることもあります。
✅【できること】
・親族が亡くなったら、相続不動産の有無をすぐに確認
・相続登記が必要な場合、3年以内の手続きを意識しましょう
遺産分割協議成立後の登記:成立日から3年以内
相続人同士で話し合って、不動産の引き継ぎ先を決める「遺産分割協議」。
この協議がすぐに成立すれば問題ありませんが、長期間まとまらない場合も少なくありません。
義務化制度では、遺産分割協議が成立した日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
つまり、相続開始から時間が経っていたとしても、話し合いが終わったタイミングから期限が始まるというわけです。
✅【次の一歩】
・協議がまとまったら、できるだけ早く登記の準備を
・登記名義人を決めたら、司法書士に相談してスムーズに手続きを
過去の相続(登記未了)のケースの期限:2024年4月1日以前の相続でも猶予あり
ここが一番ややこしいポイントかもしれません。
「だいぶ前に相続が終わっているけれど、登記はまだしていない」という方も対象になります。
例えば、親が10年前に亡くなっているのに、不動産の名義がそのまま…というケース。
この場合でも、2024年4月1日時点で登記が未了であれば、そこから3年以内=2027年3月31日までに申請が必要です。
| 相続時期 | 登記期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降の相続 | 相続を知った日から3年以内 |
| 遺産分割協議で名義が決まった場合 | 協議成立から3年以内 |
| 2024年4月1日より前の相続(登記未了) | 2027年3月31日までに申請 |
✅【チェックポイント】
・過去の相続でも、登記が終わっていなければ対象になります
・今すぐ登記する必要はありませんが、「3年以内」の猶予があると認識を
関連記事:岡山市内で評判の良い遺品整理業者一覧
書類・調査・準備すべきこと
「登記をしなければいけないのは分かった。でも、何から手をつければいいのか分からない…」
多くの方がこの段階で止まってしまいます。
実際には、登記よりも前に“そろえておくべき書類や情報”があります。
ここでは、私たち“めーぷる岡山中央店”が普段ご相談を受ける中で、必要になることが多い準備項目を整理してご紹介しますね。
相続人を確定するための戸籍・除籍・原戸籍の取得
まず必要になるのは、誰が相続人なのかを明確にすることです。
そのためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍一式をそろえる必要があります。
さらに、相続人にあたる人(子、配偶者、兄弟姉妹など)の現在の戸籍謄本も必要になります。
✅【ここで必要な書類】
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 除籍謄本・改製原戸籍
- 相続人全員の現在戸籍謄本
これらの取得は、本籍地の役所ごとに申請する必要があるため、複数の自治体をまたぐケースも少なくありません。
「何を、どこから、どうやって?」が分からない場合は、専門家に依頼するのも一つの方法です。
不動産を特定する:登記事項証明書・法務局・固定資産税台帳などで所有不動産を調べる
次に必要なのは、相続対象となる不動産の範囲を正確に把握することです。
被相続人がどこに、どんな土地や建物を持っていたかは、次のような資料で調べることができます。
| 方法 | 確認できること |
|---|---|
| 登記事項証明書(法務局) | 土地・建物の所有者や権利関係を確認 |
| 固定資産税納税通知書 | 所有している不動産の所在地・評価額 |
| 名寄帳(市区町村役場) | 同一市区町村内の不動産を一覧で確認 |
✅【ここでできること】
・手元にある固定資産税の書類を確認してみましょう
・不動産の正確な所在地や筆数を、法務局で調査することも可能です
遺産分割協議書、遺言書など相続方法に応じた書類準備
不動産を誰が相続するか決まっている場合でも、登記のためには「それを証明する書類」が必要になります。
遺言書があるならその内容に従い、ない場合は相続人全員による「遺産分割協議書」が求められます。
| 状況 | 必要書類 |
|---|---|
| 遺言書がある | 公正証書遺言、または家庭裁判所の検認済み自筆遺言書 |
| 遺言書がない | 相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書 |
✅【次の一歩】
・遺言の有無を家族間で確認しておく
・協議書を作成する際は、司法書士や行政書士に相談するとスムーズです
簡便制度の利用:義務化対応のための工夫
「相続登記が義務になったとはいえ、家族で話し合いが進まない…」「戸籍を取り寄せるのが大変そう…」
そう感じる方も多いのではないでしょうか。
そんな負担を少しでも減らすために、義務化に対応するための“簡便な制度”がいくつか用意されています。
この章では、知っておくと便利な3つの制度をご紹介しますね。
相続人申告登記制度:話がまとまらないときの“とりあえず申告”の手続き
相続人の間で話がつかず、誰が登記するか決まらない…。そんなときに使えるのが、「相続人申告登記制度」です。
この制度では、不動産を相続した事実があることを“申告だけ”で登記記録に反映できるため、とりあえず義務を果たすことが可能になります。
登記名義の変更は後回しでも、3年の期限内に申告すれば過料を免れるという仕組みです。
✅【使える場面】
・相続人が複数いて、協議がまとまっていない
・登記の準備が整っていないが、とりあえず期限を守りたい
戸籍の広域交付制度:戸籍の取得を簡単にする制度
相続手続きでは、本籍地の市区町村ごとに戸籍を請求する必要があり、これが大きな負担でした。
しかし2024年からは、「戸籍の広域交付制度」が始まり、どこの自治体でも全国の戸籍が取得可能になります。
これにより、複数の役所に申請する手間が大幅に軽減され、相続人の確定や手続きがしやすくなります。
✅【便利ポイント】
・現在地の役所で全国の戸籍が一括で取得できる
・時間や交通費の節約に
所有不動産記録証明制度(仮称):法務局で不動産所有状況を証明する仕組み
被相続人がどこに不動産を持っていたのか分からない――。
そんなときに役立つのが、現在整備中の「所有不動産記録証明制度(仮称)」です。
この制度では、被相続人の名義になっている不動産を、全国一括で調べることができるようになります。
現在は、法務局に問い合わせる形で、ある程度の調査が可能です。
✅【将来的にできること】
・一度の申請で全国の不動産名義を確認
・不動産の漏れなく、正確な相続手続きが可能に
関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方
期限を過ぎたらどうなるか・罰則と正当な理由
「3年以内に登記しなければいけない」とは聞いたけれど、万が一間に合わなかったらどうなるのか…?
この疑問、とてもよく聞かれます。
相続登記の義務化にともない、正当な理由なく登記を怠った場合には“罰則”が科される可能性があります。
でも一方で、やむを得ない事情があれば免除されることもあるので、その判断基準をしっかり知っておきましょう。
過料(最大10万円)になるケースと流れ
相続登記を期限内に行わなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
ただし、自動的に罰金が発生するわけではなく、法務局が事情を確認し、悪質と判断された場合に限られるのがポイントです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 相続または遺贈で不動産を取得した人 |
| 罰則 | 10万円以下の過料(行政処分) |
| 判断基準 | 故意・放置・正当な理由の有無などを総合的に判断 |
| 手続きの流れ | 法務局から通知 → 意見提出 → 必要に応じて過料 |
✅【知っておくべきこと】
・過料は「罰金」ではなく「行政処分」なので前科にはなりません
・登記を放置していた期間や、対応の意思があるかが重視されます
正当な理由として認められる例/認められない例
すべての“遅れ”が罰則の対象になるわけではありません。
法務局が「それなら仕方ない」と判断する“正当な理由”があれば、過料は科されません。
✅【正当な理由として認められる可能性がある例】
- 相続人の死亡や重病、認知症などで手続きが困難だった
- 相続人が遠方に複数おり、協議や連絡に長期間を要した
- 不動産の存在を把握しておらず、最近になって判明した
- 地震や災害などで役所が長期休業していた
✅【正当な理由にならない例】
- 忙しかったから
- 登記のやり方が分からなかった
- 費用がかかるので後回しにしていた
- 他の家族がやると思っていた
こうした「うっかり放置」は、悪質と見なされやすいため注意が必要です。
✅【次の一歩】
・少しでも不安がある方は、今すぐ不動産の状況を確認しておきましょう
・「正当な理由」に該当するかどうか不安な場合は、司法書士など専門家へ相談を
関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識
簡便制度の利用:義務化対応のための工夫
「相続登記の義務化って、ハードルが高そう…」
そんな不安の声に応えるかたちで、最近では手続きの負担を軽くする“簡便制度”が整いつつあります。
「話し合いが進まない」「戸籍集めが大変」「不動産がどこにあるか分からない」――こうした場面で役立つ制度を、私たち“めーぷる岡山中央店”の視点からご紹介しますね。
相続人申告登記制度:話がまとまらないときの“とりあえず申告”の手続き
家族間で遺産分割の話がまとまらない…。そんなときに使えるのが、相続人申告登記制度です。
この制度では、相続が発生したことだけを法務局に申告しておけば、登記義務を果たしたことになるという仕組みです。
これにより、分割協議や名義変更を急ぐ必要はなくなり、“まず期限を守る”という目的が達成できます。
✅【ポイント】
- 申告するだけで義務履行と見なされる
- 協議が長引く場合の“時間稼ぎ”にもなる
- あくまで仮の記録なので、後に正式な登記が必要
戸籍の広域交付制度:戸籍の取得を簡単にする制度
これまでの戸籍取得は、「本籍地ごとに役所を回らなければいけない」という面倒さがありました。
しかし戸籍の広域交付制度によって、1つの市役所で全国の戸籍がまとめて取得できるようになっています。
遠方の役所に郵送申請する手間も減り、必要な戸籍が一気にそろうため、相続手続きの第一歩がぐんとラクになります。
✅【活用シーン】
- 被相続人の戸籍が複数の市町村にまたがっている
- 忙しくて、あちこちに申請する余裕がない
所有不動産記録証明制度(仮称):法務局で不動産所有状況を証明する仕組み
「親が不動産を持っていたかどうか分からない」「他県に物件があるかもしれない」
そんなときに役立つのが、今後の導入が予定されている所有不動産記録証明制度(仮称)です。
これは、被相続人が全国に持っていた不動産の情報を、一括で調べられる証明書として発行される予定の制度です。
まだ正式にはスタートしていませんが、一部の法務局ではすでに名寄帳の調査や不動産照会サービスを活用したサポートが可能です。
✅【できること】
- 不動産の漏れや見落としを防げる
- 相続登記前の調査を効率化できる
関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方
期限を過ぎたらどうなるか・罰則と正当な理由
「うっかり期限を過ぎてしまったら、どうなるの?」
この質問、本当によくいただきます。
相続登記の義務化は、守らなければ“行政罰”の対象になる可能性があるルールです。
でも、すぐに罰則というわけではなく、きちんと事情を説明できれば、免除されるケースもあります。
この章では、「過料」と「正当な理由」について分かりやすく整理しますね。
過料(最大10万円)になるケースと流れ
相続登記の申請を正当な理由なく3年以内に行わなかった場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
ただし、自動的にペナルティが発生するのではなく、以下のような流れで判断されます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 義務違反の確認 | 法務局が期限を過ぎた登記の有無を調査 |
| ② 意見聴取 | 相続人に事情の確認や説明の機会が与えられる |
| ③ 判断 | 正当な理由がないと判断されれば、過料通知へ |
| ④ 支払い | 最大10万円の過料(罰金とは異なり前科はつかない)を支払う義務が発生 |
✅【知っておくべきこと】
・過料は「刑罰」ではなく「行政罰」なので、記録が残るわけではありません
・申告や説明の余地はあるため、放置せず早めに相談を
正当な理由として認められる例/認められない例
「やむを得ない事情があるなら罰則は免除される」――これは事実です。
でも、どこまでが“正当”と認められるのか、その判断基準が気になるところですよね。
✅【正当な理由として認められる可能性がある例】
- 相続人の死亡や入院などで手続きができなかった
- 認知症などで意思判断能力に問題があった
- 被相続人の不動産があることを最近まで知らなかった
- 地震・災害などで法務局や役所が長期間閉庁していた
✅【正当な理由として認められない例】
- 「忙しくてできなかった」
- 「費用がかかるから様子を見ていた」
- 「誰かがやってくれると思っていた」
- 「よくわからないから放置していた」
こうした“うっかり”や“なんとなく”では、過料の対象になる可能性が高まります。
✅【今できること】
・少しでも不安があれば、まずは不動産の登記状況を確認
・登記が必要か判断がつかない場合は、専門家に相談を
関連記事:遺品整理を安く済ませるための完全ガイド
義務化後の実務上の注意点・トラブル回避
「手続きさえすれば大丈夫」――そう思っていると、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。
実際の現場では、相続人の数や関係性、名義変更のスピード、費用や税務の見積もりなど、細かい点で悩まれる方が多いです。
この章では、相続登記の義務化を“実務としてうまく進めるための視点”をお伝えしますね。
相続人が多数、所在不明者がいる場合の対処法
相続人が兄弟姉妹や甥姪にまで広がっていたり、連絡が取れない相続人がいたりするケースは珍しくありません。
こうしたときは、通常の協議や登記ができない状態になります。
このような場合には、以下のような手続きが検討されます。
| 状況 | 対処法 |
|---|---|
| 相続人が多数で意見がまとまらない | 調停・審判による解決(家庭裁判所) |
| 所在不明者がいる | 不在者財産管理人の選任申立て(家庭裁判所) |
| 相続放棄者の確認が必要 | 放棄届の提出記録などを確認する |
✅【できること】
・全相続人と確実に連絡を取るため、早めに戸籍を集めておく
・所在不明者がいる場合、家庭裁判所への相談を検討
名義変更を速くするコツ(司法書士活用など)
相続登記を自力で行うことも可能ですが、慣れていない方にとっては戸籍の取得、書類作成、法務局への提出などで手間と時間がかかるのが現実です。
✅【スムーズに進めるためのコツ】
- 司法書士に依頼することで、最短1〜2週間で完了することも可能
- 書類の不備による差し戻しリスクを回避できる
- 協議書作成や戸籍収集も一括して任せられることが多い
費用は発生しますが、時間と安心感を買う選択肢として十分に検討の価値があります。
✅【おすすめの流れ】
- 相続人の戸籍を集める
- 不動産の内容を調べる(固定資産税通知・登記事項証明書)
- 司法書士などの専門家に相談
費用・税務・手続きの負担の見積もり
相続登記は義務であっても、「いくらかかるのか」が分からないと不安ですよね。
実際に必要となるのは、登録免許税や専門家への報酬、戸籍の取得費用などです。
| 項目 | 目安金額(例) |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産評価額×0.4%(最低1,000円) |
| 戸籍・書類取得費用 | 1,000〜5,000円前後(通数による) |
| 司法書士報酬 | 5万円〜10万円程度(内容によって異なる) |
税務面では、相続税の申告が必要なケースもあるため、不動産の評価額や相続財産の総額の確認が大切です。
専門家に一度まとめて見積もりを依頼しておくと、後々の安心につながります。
✅【次の一歩】
・費用の概算を知りたいときは、不動産の固定資産評価額を調べてみましょう
・司法書士や税理士の“無料相談”を活用するのもおすすめです