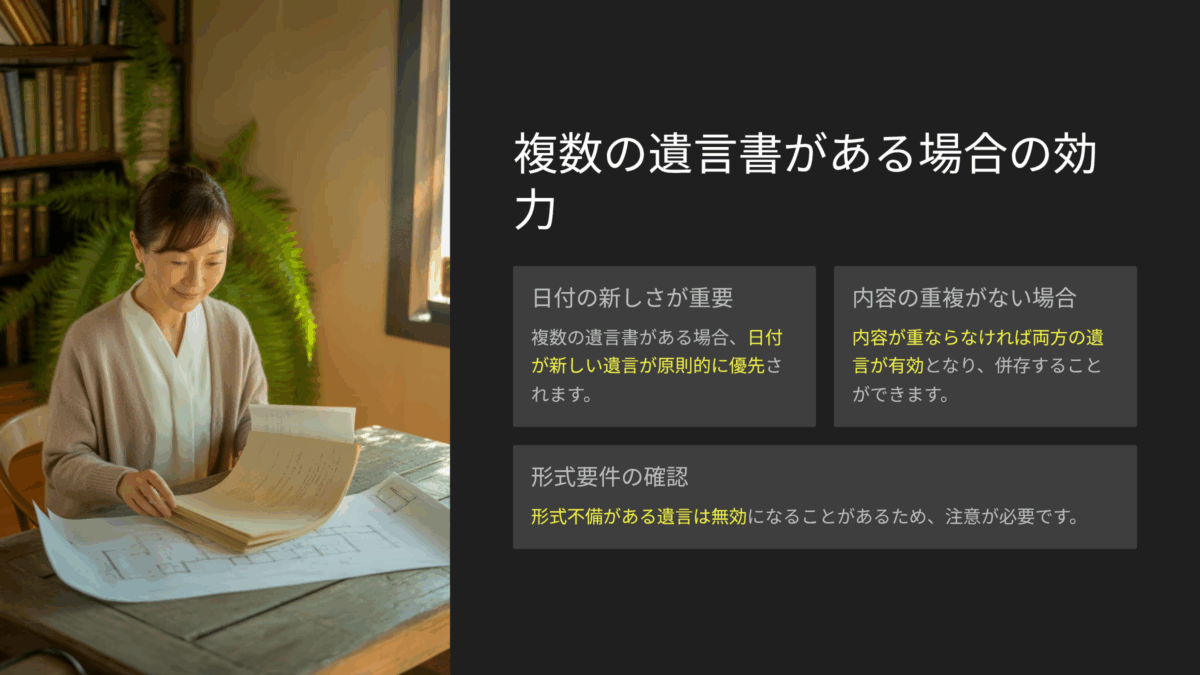遺言が複数出てきたとき、どれが有効なのか判断に迷う方は少なくありません。遺言の優先順位や見極め方を、具体例とともにわかりやすく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
複数の遺言が見つかったとき、どちらが有効になる?【法律の基本ルール】
「2通以上の遺言書が見つかったら、どれを信じればいいの?」
そんな疑問を抱く方は少なくありません。特に、自筆証書遺言(本人が手書きで書いた遺言)と、公正証書遺言(公証人立会いのもとで作成された遺言)が混在していた場合などは、判断に迷ってしまいますよね。
私たち“めーぷる岡山中央店”でも、実際に「親の遺言が2通出てきたんです…」というご相談を受けることがあります。この記事では、複数の遺言書が見つかったときに、どちらが有効なのかという法律の基本ルールと、その確認方法についてわかりやすく整理しますね。
民法に定められた遺言の撤回と優先順位
遺言は、一度書いたら絶対に変更できないものではありません。
民法では「遺言の撤回は自由」と定められており、あとから作られた遺言が前の遺言に「内容的に矛盾している部分」がある場合、その部分だけが自動的に撤回されたものとみなされます。
つまり、全体が無効になるわけではなく、新しい遺言と矛盾していない箇所は古い遺言でも有効。
この「抵触部分のみ撤回される」という仕組みは、遺言者の最終的な意思を尊重するための考え方です。
【ポイント整理】
- 遺言は何度でも書き直せる(撤回可能)
- 内容が重なっていた場合、新しい遺言の記載が優先される
- 矛盾しない部分は、古い遺言も有効なまま
「一番新しい遺言=全部有効」と単純に考えてしまうのは早計です。中身を丁寧に比較することが必要です。
「抵触する部分のみ撤回とみなされる」仕組みとは?
ここが少し難しいところですが、例を使ってみましょう。
たとえば、
- 【古い遺言】「長男に土地を、次男に預貯金を相続させる」
- 【新しい遺言】「長男に預貯金をすべて相続させる」
この場合、「預貯金を次男に」という古い内容は撤回されたとみなされますが、「土地を長男に」という記述は新しい遺言と矛盾しないため、そのまま有効となります。
このように、新旧の内容を照らし合わせて「抵触する部分だけが上書きされる」という考え方が法律の基本です。
つまり、新しい遺言があるからといって、古い遺言のすべてが無効になるとは限らないということ。
意外と見落としがちなポイントです。
✅ できること
- 複数の遺言がある場合は、弁護士や司法書士など専門家に全文をチェックしてもらう
- 内容の違いや、どこが抵触しているかを慎重に比較しましょう
有効な遺言の判定ポイント:日付・内容・方式の確認
どちらの遺言が有効かを見極めるには、以下の3つがカギになります。
| 判定ポイント | チェック内容 |
|---|---|
| 日付 | より新しい遺言が原則的に優先 |
| 内容 | 両者に矛盾がないかを確認(抵触部分の判定) |
| 方式 | 法律で定められた形式(自筆・公正・秘密)が守られているか |
とくに注意したいのは、「日付が書かれていない遺言」。
この場合、どちらが新しいのか判断できず、無効とされるリスクもあるため、慎重に扱う必要があります。
また、公正証書遺言のように公証役場で作成・保管されていた場合は、形式の面でも信頼性が高く、有効性を否定されにくいという特長があります。
✅ 次の一歩
- 見つかった遺言の「日付」「署名」「押印」の有無を確認
- 公正証書遺言なら、公証役場での履歴確認も可能
- 不安があれば、家庭裁判所での「検認」手続きで確認を取りましょう
遺言の優先順位を判断する3つのステップ
「どれが一番“効力がある遺言”なのかがわからない」
そんなふうに迷われる方、実はとても多いんです。
特に、複数の遺言が見つかったときは、見た目だけで判断せず、法律に照らして順序立てて確認することが大切になります。
この章では、遺言の有効性や優先順位を見極めるための3つのステップをご紹介しますね。
ステップ① 遺言の日付を確認する
最初に見るべきは「作成された日付」です。
遺言はあとから書いたものほど、優先されるのが原則。
民法でも、新しい遺言が古い遺言と矛盾する場合、後の遺言が有効と定められています。
ただし、単純に「新しい=すべて有効」ではない点に注意が必要です。
どこが重なっていて、どこが新しく書き換えられたのかを見極める必要があります。
✅チェックポイント
- 遺言の日付が明記されているか
- 「平成」や「令和」などの元号で迷ったら西暦に変換して比較を
日付のない遺言は、無効と判断される可能性もあるので慎重に扱いましょう。
ステップ② 内容に矛盾や抵触があるかを見極める
次に確認したいのは、「内容の重なり」です。
前の遺言と後の遺言に、同じ財産について異なる指示が書かれていないかを比べてみましょう。
たとえば…
- 【旧遺言】長女に不動産、長男に預貯金
- 【新遺言】長男に不動産を相続させる
この場合、不動産については新しい遺言が優先されますが、預貯金については新遺言に記載がないため、旧遺言の内容が生きることになります。
このように、内容が「抵触」している部分だけが撤回されたとみなされ、それ以外は併存するというのが基本の考え方です。
✅ポイント整理
- 内容が「上書き」されている部分=新しい遺言が優先
- 重なっていない部分=古い遺言のまま有効
複数の遺言があっても、一方をまるごと無効にするのではなく、部分的に組み合わせて判断されることが多いです。
ステップ③ 法律上の形式や要件を満たしているか確認
最後に確認すべきは、遺言そのものが法律のルールを満たしているかどうかです。
たとえ内容や日付が問題なさそうでも、形式が不備だと無効になってしまう可能性があります。
特に注意したいのは「自筆証書遺言」。
自分で書いた遺言は、以下の条件を満たさないと認められません。
【自筆証書遺言の主な要件】
- 本人が全文を自筆で書いていること(財産目録は例外)
- 日付・署名・押印があること
- 書き直しがある場合、訂正方法が正しいこと
一方、公正証書遺言は公証人立会いのもとで作成されるため、形式面での信頼性が高く、原則として無効になりにくいというメリットがあります。
✅チェックリスト
- 署名・押印・日付の有無
- 法的に定められた方式(自筆・公正・秘密証書)を守っているか
- 内容が第三者によって確認された記録があるか(公正証書なら確実)
「どれが正式か迷う…」という場合は、家庭裁判所での検認や専門家の確認を受けるのが安心です。
関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方
ケース別:どの遺言が有効になる?【具体例で解説】
「結局、うちの場合はどの遺言が有効なの?」
そう感じた方のために、ここでは実際によくある3つのケースに分けて、どの遺言が優先されるのかを具体的に整理していきます。
私たち“めーぷる岡山中央店”でも、こうしたご相談を受けるたびに「判断の軸」をご一緒に確認しています。
法的なルールだけでなく、現実的な対応のイメージを持っていただける内容です。
ケース1:遺言の全体が変更されていた場合
【例】
- 【旧遺言】長男に土地、長女に預金、次男に株式を相続させる
- 【新遺言】妻にすべての財産を相続させる
このように、新しい遺言で財産全体の配分が根本から変わっている場合は、
新しい遺言の内容が全面的に優先されることになります。
特に、「妻にすべてを相続させる」という包括的な記述は、それ以前の個別指定と抵触するため、旧遺言は事実上無効になります。
✅ポイント
- 「すべてを相続」と明記されていれば、それ以前の個別指定は撤回扱い
- 全体変更型の遺言は、新しいものがそのまま有効と理解するのが基本
ケース2:財産ごとに異なる相続人が指定されていた場合
【例】
- 【旧遺言】長男に不動産、次男に預金
- 【新遺言】長女に株式を相続させる
この場合は、新しい遺言に旧遺言の内容と重なる部分がないため、
両方の遺言が併存する形で、それぞれ有効になります。
つまり、不動産・預金・株式それぞれの財産について、どの遺言に記載されているかで判断されるということです。
✅ポイント
- 抵触しない部分は両方の遺言が有効
- 財産の種類や記載の有無に注意して確認を
このようなケースでは、一見すると「新しい遺言があるから古いものは無効」と思いがちですが、内容をきちんと読み込むことで、すべての遺言が意味を持つこともあると理解しておきましょう。
ケース3:一部の内容だけが変更されていた場合
【例】
- 【旧遺言】長女に自宅、次男に預金、長男に車を相続
- 【新遺言】長女に「預金」を相続と変更
このような場合、預金の部分だけが抵触しているため、そこだけが新しい内容に置き換わることになります。
他の部分、つまり自宅や車に関する指定は新遺言に書かれていないので、旧遺言の記載がそのまま生きるという構造です。
✅ポイント
- 一部だけ変更された場合は、変更部分のみが上書きされる
- 抵触していない内容は、古い遺言でも引き続き有効
つまり、「一部変更」は最も複雑で注意が必要なパターンです。
どこが変更され、どこが残っているのかを冷静に読み取る力が問われます。
関連記事:岡山エリアの遺品整理業者選びに役立つ情報
遺言が後から出てきたときの対処法と注意点
「もう手続きが始まっていたのに、あとから別の遺言が見つかった」
そんな状況に直面すると、誰しも不安になりますよね。
実際、私たち“めーぷる岡山中央店”でも、手続きの途中で「別の遺言が見つかった」とご相談を受けるケースは少なくありません。
ここでは、新たな遺言が発見されたときにどう動けばよいのか、その影響と注意点を具体的に解説します。
新たな遺言が発見された場合の対応フロー
遺言が後から見つかった場合、まずは冷静に状況を整理することが最優先です。
以下のようなステップで対応するとスムーズです。
✅対応フロー
- 遺言の形式を確認する(自筆/公正/秘密証書)
- 作成日を調べ、他の遺言とどちらが新しいか確認
- 内容に抵触や変更点があるかを見比べる
- 必要に応じて、家庭裁判所で「検認」手続きを行う(自筆証書遺言の場合)
- 専門家に相談し、執行の中止・見直しを判断する
遺言は最新の意思が尊重されるのが基本ルール。
そのため、新しい遺言が有効であれば、それに基づいて相続の内容が変わることもあり得ます。
執行中に出てきた遺言は無効になる?
すでに相続の手続きが始まっていた場合、
「いま執行している遺言はどうなるの?」と不安に思う方も多いはず。
結論から言うと、新たに発見された遺言が有効であれば、現在進行中の内容は見直される可能性が高いです。
ただし、その時点での執行内容すべてが自動的に無効になるわけではありません。
✅注意点
- すでに執行済みの部分(遺産分割・登記など)を元に戻すには、相続人間の話し合いや裁判が必要になることも
- 新たな遺言が形式不備や疑義のあるものなら、無効とされる場合もある
つまり、新しい遺言が「有効かつ内容が抵触している」場合にのみ、執行の見直しが必要になると考えてよいでしょう。
遺言の有効性を争いたいときの対処法
「この遺言、どうしてもおかしいと思う…」
そんなときは、ただ不満を抱えるのではなく、法的に“無効”を主張する手段があります。
代表的なのが「遺言無効確認の訴え」。
これは、家庭裁判所に申し立てて、遺言の有効性を裁判で判断してもらう手続きです。
✅無効の主張でよくある例
- 遺言者に認知症など判断能力の低下があった
- 書かれた日付が不明確または存在しない
- 署名や押印が本人のものではない疑い
- 第三者による偽造・強要の可能性がある
こうした場合でも、無効と認められるには証拠が必要です。
医師の診断書や筆跡鑑定、証人の証言などが必要となるケースもあります。
✅できること
- 不安な場合は、早めに相続に詳しい弁護士に相談
- 自分ひとりで判断せず、中立的な専門家の意見をもらうことが大切
ケース別:どの遺言が有効になる?【具体例で解説】
「複数の遺言が出てきたけど、結局どれを信じればいいの?」
そんなとき、判断のヒントになるのが「どう書かれていたか」という具体的な中身です。
私たち“めーぷる岡山中央店”にも、「父の遺言が2通見つかった」「一部だけ違う内容だった」など、さまざまなご相談が寄せられます。
ここでは、よくある3つのケースに分けて、どの遺言が有効になるのかを具体的に解説します。
ケース1:遺言の全体が変更されていた場合
【例】
- 旧遺言:「自宅は長男に、預金は長女に」
- 新遺言:「すべての財産を妻に相続させる」
このように、新しい遺言が全体の内容を大きく書き換えている場合は、
原則として新しい遺言が全面的に有効になります。
前の遺言と抵触している部分(自宅や預金の相続先)もすべて撤回されたとみなされます。
✅ポイント
- 「すべての財産」と包括的に書かれていれば、古い遺言の大部分は無効に
- 明確に内容が切り替わっていると判断しやすいケースです
この場合、最終的な意思を尊重して、最新の遺言に基づいた手続きを行うのが基本です。
ケース2:財産ごとに異なる相続人が指定されていた場合
【例】
- 旧遺言:「自宅は長男に、預金は次男に」
- 新遺言:「株式は長女に相続させる」
このケースでは、それぞれの遺言で扱われている財産が異なるため、両方の遺言が有効になります。
つまり、「自宅」「預金」「株式」について、それぞれ有効な遺言が存在するという構図です。
✅ポイント
- 重複や矛盾がなければ、両方の遺言は併存する
- 内容ごとに切り分けて考えることが重要です
このような場合、「古いから無効」と単純に切り捨てないことが大切。
すべての遺言の内容を精査してから判断することが望ましいです。
ケース3:一部の内容だけが変更されていた場合
【例】
- 旧遺言:「自宅は長男、預金は次男、車は長女に」
- 新遺言:「預金は長女に相続させる」
このようなケースでは、新旧の遺言が部分的に抵触しているため、
抵触する「預金」の部分だけが新しい内容に上書きされます。
他の財産(自宅や車)に関する旧遺言は、新遺言と矛盾がないため、そのまま有効です。
✅ポイント
- 内容が重複している部分だけが撤回とみなされる
- それ以外の部分は引き続き旧遺言が有効
このパターンは非常に多く、見落とされがちな古い遺言が生きてくるケースでもあります。
特に財産の種類が多いご家庭では、一部変更型の遺言が複数残ることが珍しくありません。
関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識
遺言が後から出てきたときの対処法と注意点
「遺産分割の話が進んでいたのに、新しい遺言が出てきた…」
そんなとき、慌ててしまうのも無理はありません。
でも実際には、こうしたケースは珍しくないんです。
私たち“めーぷる岡山中央店”にも、「もう手続きが終わりそうだったのに、別の遺言が見つかった」というご相談がたびたび寄せられます。
ここでは、あとから遺言が見つかったときにどう対応すればよいのか、実務に沿った流れでお伝えしますね。
新たな遺言が発見された場合の対応フロー
新しい遺言が出てきたときは、すぐに「この遺言が有効かどうか」を確認する必要があります。
ただ焦って全体をやり直すのではなく、段階的に確認・手続きするのがポイントです。
✅対応フロー
- 新たな遺言の「日付」「署名」「方式」を確認
- 既存の遺言と内容が重複・矛盾しているかを比較
- 家庭裁判所で検認手続き(自筆証書遺言の場合)を行う
- 専門家の意見をもとに、必要に応じて執行の見直しを検討
特に重要なのは、「日付」と「抵触するかどうか」です。
新しい遺言が正式であれば、原則としてその内容が優先されます。
執行中に出てきた遺言は無効になる?
「じゃあ、今進めてる遺言の手続きって、全部無効になるの?」
そんな心配をされる方も多いですが、すぐに“すべて無効”にはなりません。
ポイントは、新しく見つかった遺言が「法的に有効」で「内容が抵触しているか」という2点。
この両方に当てはまる場合、すでに進めていた内容の一部または全部を見直す必要があります。
ただし、
- すでに名義変更などが完了している場合
- 遺産分割協議書に基づき分割されている場合
こうしたケースでは、話し合いのやり直しや家庭裁判所での調停が必要になる可能性も出てきます。
✅ここに注意
- 執行途中でも「抵触がなければ」元の遺言も有効なまま
- 財産の引き渡しが終わっていても、新たな遺言が優先されるケースはある
つまり、「無効になるかどうか」はケースバイケース。
状況に応じて法的な整理が必要になるのです。
遺言の有効性を争いたいときの対処法
「この遺言、どうしてもおかしい」
そんな違和感がある場合、法的に遺言の有効性を争うことも可能です。
代表的な方法は「遺言無効確認の訴え」。
これは家庭裁判所に対して、その遺言が有効かどうかを法的に判断してもらう手続きです。
✅よくある無効主張の理由
- 遺言を書いたとき、認知症などで判断能力がなかった
- 署名・押印が本人のものではない(筆跡鑑定の対象になることも)
- 内容が極端に不自然、または誰かに強要されて書かれた可能性がある
ただし、無効を主張するには明確な証拠が必要です。
診断書や介護記録、専門家による筆跡鑑定などが求められるケースもあります。
✅対処のポイント
- まずは冷静に遺言の内容と背景を整理
- 少しでも不安を感じたら、早めに弁護士など専門家に相談を
関連記事:遺品整理を安く済ませるための完全ガイド
よくある質問Q&A:遺言が複数あるときの対応
複数の遺言が見つかったとき、どれが有効なのか、どう対処すればよいのか…。
実際にご相談を受けていても、「ネットで調べてもいまいち分からなかった」とおっしゃる方が多いんです。
この章では、そんな疑問をスッキリ解消するために、よくある質問をQ&A形式でまとめてお答えしますね。
古い遺言でも有効になることはある?
はい、古い遺言であっても「内容が新しい遺言と抵触していなければ」有効とされます。
遺言は、あとから書かれたものが常にすべてを上書きするわけではなく、部分的な変更であれば、変更された箇所以外の内容は引き続き有効になるんです。
✅ポイント
- 古い遺言=無効ではない
- 内容に矛盾がなければ、両方の遺言が共に有効になることもある
つまり、「日付が新しい=全とっかえ」ではなく、内容ごとの読み取りが大切なんですね。
公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらが優先される?
優先順位は「方式」ではなく「作成日と内容」で決まります。
公正証書遺言の方が形式的にしっかりしていて無効になりにくい、というメリットはありますが、
自筆証書遺言でも法律の要件を満たしていれば、十分に有効な遺言です。
✅判断の軸
- 日付が新しい遺言が原則的に優先
- 形式(公正証書・自筆証書)ではなく、法的要件と内容の整合性が重要
ただし、自筆証書遺言は形式ミスで無効になるリスクも高いため、確認は慎重に行いましょう。
遺言の有効性を判断する専門家は誰?
遺言の内容が有効かどうか、疑問がある場合は、家庭裁判所か、相続に詳しい専門家に相談するのが確実です。
特に自筆証書遺言の場合、開封前に家庭裁判所での「検認」手続きが必要ですし、
内容に争いがある場合は、「遺言無効確認訴訟」といった裁判での判断を求めることになります。
✅相談先の例
- 家庭裁判所(検認・調停)
- 弁護士(遺言の有効性判断、無効訴訟の代理)
- 司法書士・行政書士(形式の確認、相続登記の相談)
誰に相談するか迷うときは、まずは地元の法律相談窓口や市区町村の無料相談を利用するのもおすすめです。
関連記事:岡山市内で評判の良い遺品整理業者一覧