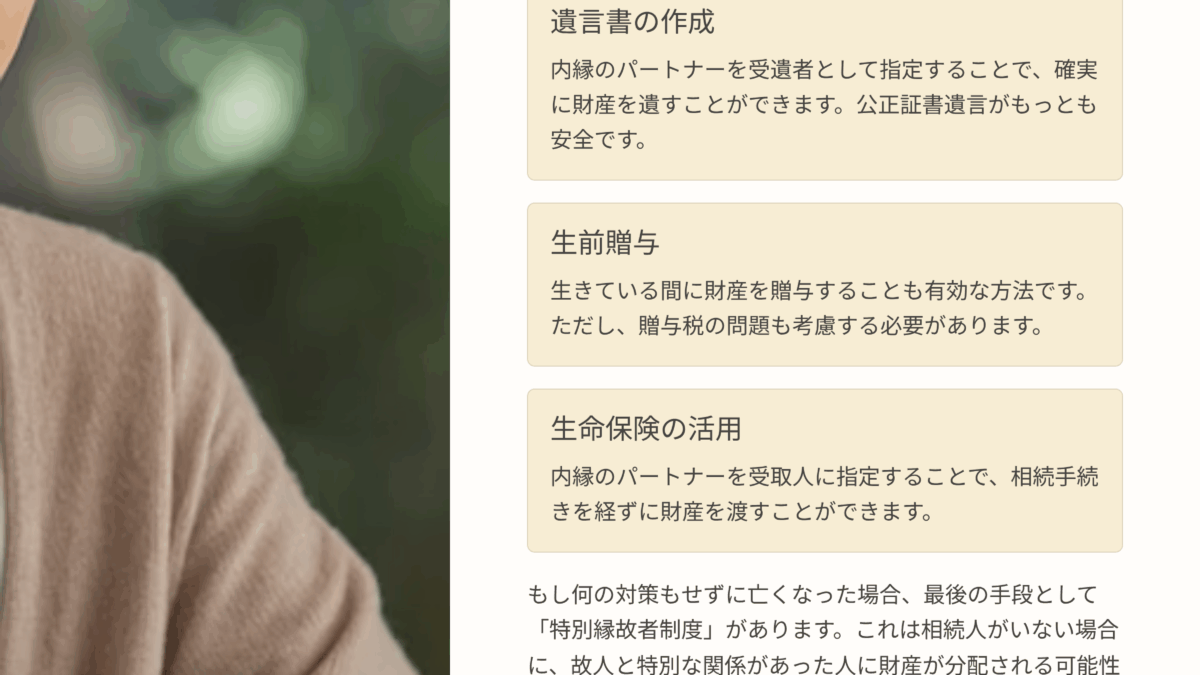内縁の妻(夫)には相続権があるのか?事実婚で暮らすパートナーに財産を遺すにはどうしたらいいのか。そんな疑問に法律と実務の視点でお答えします。目次を見て必要なところから読んでみてください。
内縁の妻(夫)に相続権はある?法律上の相続人として認められるのか
「内縁の妻(夫)にも、きちんと財産を残してあげたい」
そんなお気持ちを持っている方にとって、「法律上の相続権があるのかどうか」は大きな関心ごとではないでしょうか。
特に事実婚や再婚を避けて暮らしている場合、「内縁関係のままで大丈夫?」と不安を感じる方も多くいらっしゃいます。
この記事では、内縁の配偶者に相続権があるのか、そして財産を遺すためにできることを、法律の視点からわかりやすく整理してお伝えします。
法定相続人とは?民法が定める相続の基本構造
「相続のしくみ、そもそもどうなってるの?」
そんな疑問を感じたとき、まず押さえておきたいのが「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」という仕組みです。
法定相続人とは、民法で定められた“相続できる人”のこと。基本的には、次のような順位で決まっています。
| 相続順位 | 該当者 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子ども・孫など直系卑属 | 子が死亡していれば孫に相続権が移る |
| 第2順位 | 父母・祖父母など直系尊属 | 第1順位がいない場合に限る |
| 第3順位 | 兄弟姉妹・甥姪 | 第1・第2順位がいない場合のみ |
| 配偶者 | 常に相続人 | 上記の順位と同時に相続する立場 |
この「配偶者」に含まれるのは、戸籍上の“婚姻届を提出した”夫婦のみです。
つまり、内縁の妻(夫)はここには含まれません。
✅ 内縁関係にあるだけでは、相続権が自動的に発生しないというのが、法律の基本スタンスです。
「長年連れ添ったのに、相続できないなんて…」と戸惑う方も多いのが現実です。
でも、ここであきらめるのは早いんです。
後ほど、「どうすれば財産を残せるか」もご紹介しますね。
内縁の配偶者は法定相続人になれない:事実婚の限界
「事実婚でも、世間的には夫婦同然だと思っていた」
実際、病院の同意書や公共の手続きでは、内縁の関係が認められるケースも増えてきました。
けれども相続に関しては、法律が非常にシビアです。
民法では、法定相続人=戸籍上の親族に限られるため、内縁の妻や夫には相続権がありません。
たとえ一緒に暮らして30年、生活費も一緒にして、子どものように可愛がっていたとしても、
戸籍に名前がなければ「相続人」ではないのです。
✅ よくある誤解
- 「一緒に住んでいたら自動的に相続人になる」は誤解
- 「扶養していたから相続できる」は民法上認められない
- 「内縁関係を証明すれば相続できる」→基本的には不可
つまり、“夫婦同然の生活”と“相続の権利”は別問題として扱われているのが、今の日本の法律なんですね。
「これでは不公平では?」と感じるのも当然です。
ただ、それをカバーする方法も、ちゃんと用意されています。
次の章では、内縁の配偶者に財産を残したいとき、どんな対策ができるのかを一緒に見ていきましょう。
関連記事:遺品整理費用を節約する方法と業者選びのポイント内縁の配偶者に財産を残す方法とは?実務的な手段の整理
「この人に残したい」と思っても、法律だけでは守りきれないのが内縁関係の難しさです。
でもご安心ください。法定相続人になれなくても、財産を渡す方法はいくつもあります。
大切なのは、「何もしなければゼロ」という現実をきちんと知って、“今できる準備”を始めること。
ここでは、実際に使える4つの方法をご紹介します。
方法① 遺言書による「遺贈」:確実に想いを伝えるための手段
内縁の配偶者に財産を遺したいとき、もっとも確実な手段が「遺言書(いごんしょ)」の作成です。
遺言書には「○○に△△を遺贈する」という記載ができ、これにより戸籍に関係なく財産を受け取ることが可能になります。
✅遺言書のポイント
- 自筆証書遺言:自分で書くが、形式不備による無効リスクあり
- 公正証書遺言:公証人が作成。確実性が高くおすすめ
「財産を誰にどれだけ残すか」だけでなく、「なぜその人に残すのか」という想いも一緒に記せるのが遺言の良いところ。
特に長年連れ添った内縁のパートナーにとっては、その言葉が何よりの支えになるかもしれません。
方法② 生前贈与:関係があるうちに財産を分ける
遺言以外の方法として、生前贈与(せいぜんぞうよ)も有効です。
これは、生きているうちに財産を移しておく方法で、「いつ・どれだけ・何を」渡すかを自由に決められます。
ただし注意点もあります。
✅生前贈与の注意点
- 年間110万円を超えると贈与税が発生
- 贈与契約書を作成し、証拠を残すことが重要
不動産や預金、車など、贈与できる対象は多岐にわたりますが、計画的に行うことが肝心です。
税務署とのトラブルを避けるためにも、専門家のアドバイスを受けると安心です。
方法③ 生命保険の受取人指定:戸籍外でも有効な対策
あまり知られていないですが、生命保険は“相続財産ではない”扱いになります。
つまり、戸籍上の関係がなくても、受取人に指定すれば確実に財産を遺すことができるのです。
✅生命保険を活用するメリット
- 受取人を「内縁の妻・夫」にできる
- 相続トラブルに巻き込まれにくい
- 現金での支払いなので、生活資金としてすぐ使える
生命保険は、「万が一のときの安心を確保する」手段として非常に有効です。
加入時には、保険会社に「受取人の記載方法」を確認しておくとスムーズです。
方法④ 特別縁故者としての財産分与:相続人不在時の法的措置
もし亡くなった方に法定相続人がいない場合、内縁の配偶者が「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」として財産の分与を受けられる可能性があります。
これは、亡くなった後に家庭裁判所へ申立てを行う手続きです。
✅特別縁故者として認められる条件
- 被相続人と生計をともにしていた実績
- 介護や支援をしていたことが証明できる
- 裁判所の判断により一部または全部の財産が分与される
ただしこの制度は、あくまで“相続人が誰もいない”ことが前提です。
相続人が一人でもいれば、特別縁故者にはなれません。
また、申立てから分与までは数ヶ月〜1年かかることも。
「最後の手段」として知っておくとよいですが、できれば事前の対策(遺言など)をしておく方が現実的です。
関連記事:岡山で遺品整理を依頼するなら知っておきたい業者情報「特別縁故者」になるために必要な手続きと注意点
「もし遺言もなく、相続人もいなかったら…」
そんなときに唯一、内縁の配偶者が財産を受け取れる可能性があるのが“特別縁故者”という制度です。
ただし、これは誰でも認められるわけではなく、制度の趣旨や条件を理解した上で正しく申立てを行う必要があります。
この章では、特別縁故者になるための基本的な流れと注意すべきポイントを整理します。
特別縁故者とは?制度の趣旨と法的根拠
特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、亡くなった方に相続人がいない場合に、
その人と特に縁が深かった方が、残された財産を受け取れる制度において認められる立場です。
この制度は、民法第958条の3に基づいています。
趣旨としては、財産が国に帰属される前に、
「故人の生活を支えていた人」や「葬儀を執り行った人」など、実質的に近しい関係にあった方へ配慮するために設けられています。
✅特別縁故者になりうる例
- 長年同居していた内縁の妻・夫
- 献身的に介護していた親族以外の人
- 葬儀や遺品整理などを手配した知人
形式よりも実態重視で判断されるのがこの制度の特徴です。
手続きの流れ:家庭裁判所への申し立て方法
特別縁故者として認められるには、家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。
流れとしては以下のとおりです。
✅特別縁故者の申立ての流れ
- 相続財産管理人の選任(家庭裁判所が行う)
- 官報による公告と債権者の申出期間(最低6ヶ月)
- 相続人がいないことの確認
- 特別縁故者からの申立て(※公告期間後3ヶ月以内)
- 家庭裁判所の審査と判断
- 認定されれば、相続財産の一部または全部の分与
申立てには、関係性を示す証拠資料(同居の証明、生活費の共有、介護の記録など)が重要です。
また、申立て期間を過ぎると分与されない可能性があるため、注意が必要です。
法定相続人がいる場合の制限と現実的リスク
ここで、ひとつ押さえておきたい落とし穴があります。
それは、「相続人が一人でもいると、特別縁故者としての分与はできない」という点です。
たとえば…
- 疎遠な兄弟が1人でも生きていればNG
- 戸籍上だけの子どもがいれば対象外
つまり、形式上の相続人が存在するだけで、内縁の配偶者には一切財産が渡らないこともあり得るのです。
また、たとえ相続人が不在だったとしても、
- 手続きに時間がかかる(半年〜1年以上)
- 必ず認定されるとは限らない
- 家庭裁判所の裁量による部分が大きい
というリスクもあります。
このように、「特別縁故者」という制度は、
最終手段ではあるけれど、確実な保証ではないということを理解しておく必要があります。
✅だからこそ、「遺言」や「生命保険」のように、
“本人の意思でコントロールできる対策”を先に講じておくことが、安心につながるのです。
関連記事:遺品整理の料金相場と依頼前に知っておきたいこと内縁関係での同居・借家の居住権はどうなる?
「相続権がないのは分かった。でも、住んでいた家からも出て行かないといけないの?」
これは、実際のご相談でも非常に多い不安の声です。特に賃貸住宅で暮らしていた場合、亡くなった方が契約者だと、内縁の配偶者が“住み続けられるのか”が問題になります。
この章では、住まいに関する権利の保護と、内縁関係でも受けられる可能性のある公的な支援制度について解説します。
賃借権の承継:住まいを守る実例と法的ポイント
まず、住まいの話から。
被相続人(亡くなった方)が賃貸契約者だった場合、内縁の妻(夫)がそのまま住み続けられるのか――
答えは「状況によって異なります」が、一定の条件を満たせば賃借権(ちんしゃくけん)を“承継できる”可能性があります。
✅居住を継続するためのポイント
- 内縁の配偶者が同居していた事実
- 家賃の支払い実績(事実上の共同生活)
- 契約者死亡後も、賃貸人(大家)との話し合いで承継が認められるケースあり
法的には、借地借家法第36条で「一定の同居人には、賃借権の承継が認められることがある」とされています。
ただし、これは自動的ではありません。大家との協議が必要になるため、関係性や住居歴を記録として残しておくことがとても大切です。
✅住まいを守るために今できること
- 契約書に内縁の配偶者の名前を「連名記載」しておく
- 領収書や振込記録などを保存
- 生前に家主と話をしておく
「住む場所を失う」という不安は大きいものですが、正しく備えれば避けられるケースも多いのです。
遺族年金やその他の公的手当:受給要件と条件
続いて、生活面の支えとなる遺族年金やその他の公的制度について。
実は、これも内縁関係であっても一定条件を満たせば、支給される可能性があるんです。
✅受給が可能な公的制度(一例)
| 制度名 | 内縁配偶者の対象可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 原則対象外 | 子のある配偶者が中心 |
| 遺族厚生年金 | 条件付きで対象可 | 5年以上の内縁関係など |
| 労災遺族補償年金 | 条件付きで対象可 | 同居・扶養実績あり |
| 健康保険の葬祭料 | 多くのケースで支給可 | 同居実績が重視される |
※制度によって細かい条件が異なるため、事前確認が必須です。
特に「遺族厚生年金」は、内縁配偶者でも認められた事例が実際にあります。
ポイントとなるのは次の3点。
✅認定されるためのチェックポイント
- 5年以上の同居実績があるか
- 被保険者と生計を一にしていたか
- 第三者による証明(親族や大家など)があるか
役所や年金事務所に相談すれば、個別ケースに応じた対応をしてくれることもあります。
✅まずはできること
- 同居を証明できる書類をまとめておく
- 預金通帳や生活費の共有記録を保管
- 保険証や公共料金の名義に工夫を
「相続権がないから、何も支援を受けられない」と思い込まず、
使える制度があるかどうか、早めに調べておくことが大切です。
関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方まとめ:内縁の配偶者に財産を遺すには“事前準備”が鍵
「内縁関係のままで、大切な人にちゃんと財産を遺せるだろうか」
この記事を通して、そうした不安や疑問に向き合ってこられたと思います。
結論から言えば、“内縁”という立場のままでは、自動的に財産を受け取ることはできません。
けれども、今からでもできる“備え”は確かにあります。
最後に、日常生活の中でできる対策と、実際に行動へ移すためのステップを一緒に確認していきましょう。
日常的にできる最善の相続対策を整理
財産を遺す準備というと、「弁護士に頼まないと無理そう」「難しい手続きが多そう」と身構えてしまいがちです。
でも、まずは小さな一歩から始めてみることが大切です。
✅今日からできる相続対策のポイント
- 生活費や口座の記録を残す(通帳や家計簿の保管)
- 住居の契約を見直す(内縁配偶者名義での契約や連名記載)
- 保険や年金の受取人情報を確認(内縁配偶者に変更できるか検討)
- 関係性を第三者にも見える形にしておく(同居の証明や写真など)
こうした記録は、いざというときの“関係性を証明する武器”になります。
財産そのものの準備だけでなく、「日々の暮らしの中で証拠を整えておくこと」が何よりの備えです。
遺言や贈与の検討ポイントと実践へのステップ
では、具体的に財産を渡すために必要な「遺言」や「贈与」のステップはどうすればよいのでしょうか。
ここでは、現実的に動き出すための道筋をまとめておきます。
✅財産を遺すための実践ステップ
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 財産の棚卸し | 預金・不動産・保険などを把握する |
| 2 | 誰に何を遺したいかを明確にする | 口約束ではなく、書面で残す準備を |
| 3 | 遺言書の作成を検討 | 公正証書遺言が安心。公証人に相談可 |
| 4 | 贈与を活用するか判断 | 税負担や時期を見ながら無理のない形で |
| 5 | 専門家への相談 | 司法書士や行政書士に相談するのも選択肢 |
とくに遺言書については、「そのうち書こう」と思って先延ばしにしがちですが、
元気なうちにしか書けないという点を忘れてはいけません。
また、気持ちを“言葉で残す”ことは、残された人への大きな愛情にもなります。
✅「法律では守ってくれないけれど、自分の意志で守る」
内縁の配偶者に財産を残すためには、この視点がとても大切です。
不安なまま過ごすよりも、「今できること」から動いてみませんか?
私たち“めーぷる岡山中央店”は、そんな“一歩目”に寄り添える存在でありたいと思っています。
関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方