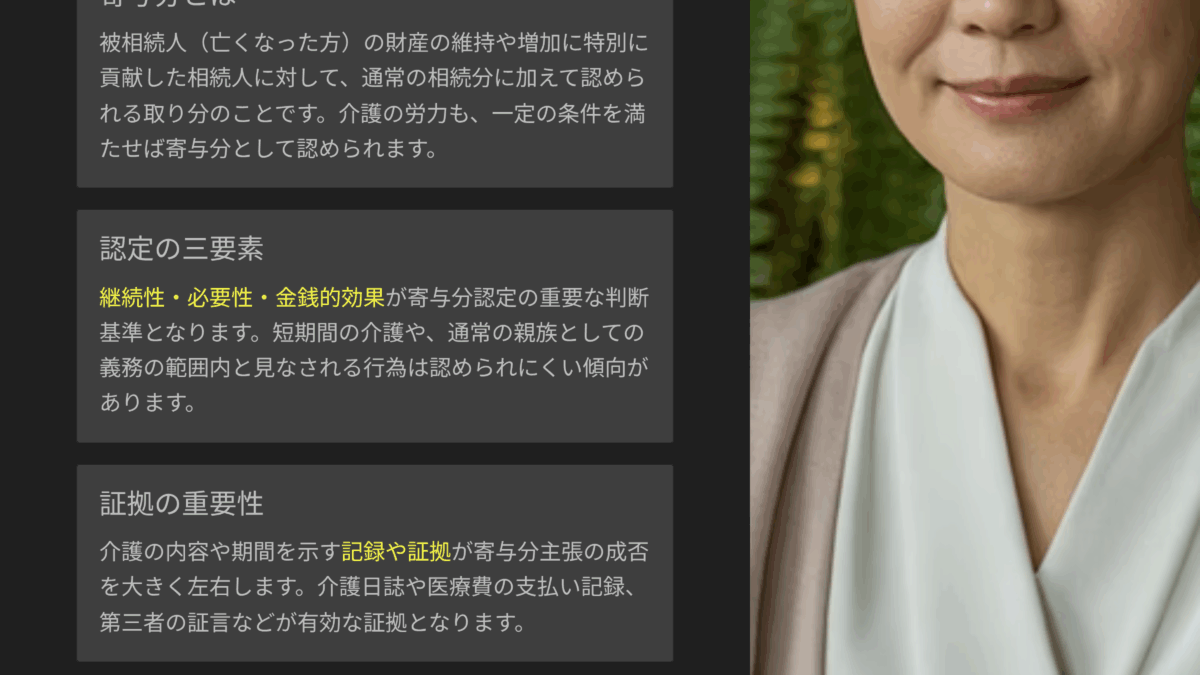「親の介護をがんばったのに、相続では何も評価されないの?」
そんな疑問やモヤモヤを感じたことがある方へ。
介護した子どもが相続で多めにもらえる可能性がある制度について、わかりやすく解説します。
目次を見て必要なところから読んでみてください。
介護をした子どもは相続で多めにもらえるのか?【疑問への基本回答】
親の介護を長年担ってきた子どもが、いざ相続の場面になって「他の兄弟と同じ取り分なのは納得いかない」と感じるのは、決して珍しいことではありません。では、介護した分だけ相続を多くもらうことはできるのでしょうか? 今回は、そんな素朴で切実な疑問に、法律の観点からお答えします。
「寄与分」とは?介護に対する法律上の評価基準
「親の介護を長年してきたのに、相続の話になったら兄弟で均等に分けるって言われた」
めーぷる岡山中央店にも、そんな声がよく届きます。
実は、介護という貢献が相続に反映される制度が、民法にはちゃんとあります。それが「寄与分(きよぶん)」です。
寄与分とは、「被相続人(亡くなった方)の財産が増えたり、減らずに済んだのは、この相続人のおかげだ」と認められた場合、その貢献度に応じて相続分を多めに加算できるという仕組みです。
たとえば…
✅ 同居して毎日介護をしていた
✅ 訪問介護サービスのように食事や排せつの世話を続けていた
✅ 親が施設に入らず済んだことで、費用負担を大きく減らした
このようなケースでは「寄与分」が認められる可能性があります。
ただし、すべての介護が自動的に評価されるわけではありません。継続性や必要性、そして経済的効果があったかどうかが重要になります。
次の一歩としては、日々の介護内容を記録に残すこと。誰がどの程度負担したのか、後から証明できるようにすることが、相続の場で「寄与分」を主張するための第一歩です。
関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識寄与分(特別寄与分)制度の基礎知識
介護をした子どもが「相続で多めにもらえるのか?」を理解するには、まず寄与分と特別寄与分の仕組みを知る必要があります。法律上の位置づけを知っておくことで、実際の相続の場面でどこまで主張できるのかが見えてきます。ここではその基本を整理します。
法定寄与分と特別寄与分の違い
寄与分には、大きく分けて2つの考え方があります。
- 法定寄与分
相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した人が対象になります。例えば、長男が親の介護を続けていた場合などです。 - 特別寄与分
2019年の民法改正で新設された制度です。相続人ではない立場(例えば長男の妻)が介護を担った場合でも、一定の要件を満たせば金銭請求ができるようになりました。
この違いをまとめると次のようになります。
| 制度 | 対象者 | 主張できる内容 |
|---|---|---|
| 法定寄与分 | 相続人(子や配偶者など) | 相続分を増やしてもらう |
| 特別寄与分 | 相続人以外(嫁、婿など) | 金銭での支払いを請求できる |
相続の場で「介護の貢献が報われる仕組み」が、以前よりも広がっているのが特徴です。
対象になる介護行為とは?具体例と要件
では、どんな介護が寄与分の対象になるのでしょうか。ポイントは通常の扶養義務の範囲を超えているかどうかです。
✅ 日常的・継続的な介護(食事、排せつ、入浴の介助など)
✅ 長期間にわたり無償で行った世話や看護
✅ 親を施設に入れずに済ませたことで、経済的に大きな効果があったケース
一方で、たまに顔を出して手伝った程度では「特別な寄与」とは認められにくいのが現実です。
つまり、寄与分を主張するには、どれくらい継続的に、どれくらい親の生活に影響を与えたかを示すことが欠かせません。日記や介護記録、医療費や生活費の支出状況を残しておくことが、後々の証拠となります。
次の一歩として、日々の介護を「当たり前」として流さず、記録と証拠を残す習慣を持つことが大切です。
関連記事:岡山エリアの遺品整理業者選びに役立つ情報寄与分を認めてもらうための手続きと計算方法
介護を理由に相続で多めにもらいたいと思っても、寄与分は自動的に反映されるものではありません。相続人同士で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で正式に手続きを進める必要があります。ここではその流れと、介護の貢献をどのようにお金に換算するのかを解説します。
寄与分の申立て場所・方法:家庭裁判所とは?
寄与分を主張するには、まず相続人同士で遺産分割協議を行います。協議で合意が得られれば、寄与分はそのまま分割内容に反映できます。
しかし、意見が食い違うことも多いため、その場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」や「審判」を申し立てることになります。
✅ 申立て先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
✅ 必要書類としては、戸籍謄本・遺産の目録・介護の記録など
✅ 家庭裁判所が寄与分の有無や金額を判断
裁判所に持ち込むとなると「大ごと」に感じる方もいますが、公平に評価してもらう唯一の手段でもあります。
介護の対価を「金額」で評価するには?計算の考え方と注意点
寄与分を認めてもらうには、介護の貢献を金額で評価する必要があります。代表的な計算方法は次の通りです。
- 代替費用方式
介護サービスを外部に依頼した場合にかかる費用を基準に計算。たとえば訪問介護の時給×介護時間。 - 現実の支出方式
実際にかかった医療費や生活費を立て替えた場合、その金額を寄与分として主張。 - 特別の事情方式
親が施設に入らず済んだことで財産が減らなかった、など経済的効果を加味して算出。
ただし注意点として、寄与分は「感情」ではなく証拠や数値で示すことが必須です。領収書や介護記録がないと、裁判所に認められにくくなります。
次の一歩としては、介護にかかった時間や金銭を具体的に数値化して記録に残すこと。これが後々の相続で大きな力になります。
関連記事:遺品整理の料金相場と依頼前に知っておきたいこと寄与分が認められるポイントと減額リスク
介護を理由に相続で多めに受け取りたいと考えても、寄与分が必ず認められるとは限りません。家庭裁判所は客観的な基準に基づいて判断するため、どのような介護なら評価されるのか、逆にどんな場合に減額や否認されるのかを理解しておくことが大切です。
継続性・必要性・効果が鍵:家庭裁判所が見る評価基準
寄与分を判断する際、家庭裁判所が特に重視するのは以下の3つの観点です。
✅ 継続性:長期間にわたり安定して介護を行っていたか
✅ 必要性:その介護がなければ、施設費用や看護サービスが不可欠だったか
✅ 効果:介護によって財産の減少を防いだ、生活を大きく支えたなどの実益があったか
一時的な手伝いや短期間の介護では「特別な寄与」とまでは認められにくくなります。逆に、数年単位で生活の中心となる介護を担ったケースでは評価が高まりやすいといえます。
過剰請求や他の相続人とのトラブルを避けるための対策
寄与分を主張する際に注意したいのは、過剰な請求はかえって信頼を損ねるという点です。相続人同士の関係が悪化し、調停や審判が長引く原因にもなりかねません。
トラブルを避けるための具体的な工夫としては:
- 介護の内容を冷静に数値化(時間・回数・費用)
- 第三者の証言や記録を確保(訪問看護師やケアマネの記録)
- 相続人全員での事前共有(不透明さをなくすことが信頼につながる)
つまり、寄与分を主張するなら「誠実さ」と「透明性」が欠かせません。証拠に基づいて合理的に説明できれば、他の相続人からの理解も得やすくなります。
次の一歩として、介護を担った証拠を整理しつつ、感情ではなく事実で伝える準備をしておきましょう。
関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方成功事例から学ぶ、介護による寄与分認定のポイント
寄与分は制度として存在していても、実際に認められるかどうかはケースバイケースです。ここでは、イメージしやすい仮想事例を通じて「成功するポイント」と「失敗してしまう落とし穴」を整理します。自分の状況に重ねて考えてみることが大切です。
仮想ケース:親の自宅介護で寄与分が認められた例
ある長女は、要介護となった母親を10年以上にわたり自宅で介護しました。毎日の食事や入浴介助に加え、夜間の見守りも行い、施設に入れる必要がなかったため、母の預貯金は大きく減らずに残りました。
長女は遺産分割協議で寄与分を主張しましたが、兄弟の合意が得られず、家庭裁判所に調停を申し立て。介護日誌・ケアマネジャーの記録・医療費の支払い明細を証拠として提出しました。
結果、裁判所は「母の生活を長期間支え、財産の減少を防いだ」と評価し、法定相続分に加えて数百万円の寄与分を認める判断をしました。
このケースから分かるのは、
✅ 長期間にわたる継続的な介護
✅ 財産維持への明確な効果
✅ 客観的証拠の存在
この3つが揃えば、寄与分が認められやすいということです。
失敗ケース:必要書類が不十分で認定されなかった例と原因
一方で、長男が「自分も介護をしていた」と主張したケースもありました。母親の通院付き添いや買い物の手伝いは確かに行っていたのですが、具体的な記録や証拠がなく、期間も断続的でした。
提出できたのは「時々通った」という本人の証言だけ。介護サービスを利用した領収書や日々の記録も残っていなかったため、裁判所は「通常の扶養義務の範囲内」と判断し、寄与分は認められませんでした。
つまり、寄与分を主張するうえでの落とし穴は、
✅ 記録を残さず「やったつもり」で終わってしまうこと
✅ 継続性や経済効果を示す客観的証拠が不足していること
次の一歩としては、介護に関わる支出・行為を小まめに記録して証拠化すること。それが、後々の相続で「認められる介護」へとつながります。
関連記事:遺品整理費用を節約する方法と業者選びのポイントまとめ:介護した子どもが相続で多くもらうには?
介護をした子どもが相続で報われるためには、寄与分という制度を正しく理解し、準備を重ねておくことが不可欠です。感情論だけではなく、証拠や数値をそろえて冷静に説明することが、相続の場で評価につながります。最後に、寄与分を有利に進めるためのポイントを整理します。
ポイント整理:寄与分で「多めにもらう」ために必要な準備
寄与分を認めてもらうには、以下の準備が効果的です。
✅ 介護の記録を残す(日記・介護時間のメモ・支出の領収書)
✅ 第三者の証言を確保(ケアマネジャー、訪問看護師の記録など)
✅ 経済的効果を明確化(施設費用を抑えた、生活費を肩代わりしたなど)
✅ 冷静で合理的な説明(「大変だったから」ではなく「財産を維持できたから」)
この準備があるかないかで、寄与分が認められる可能性は大きく変わります。
早めの相談が肝心:専門家への相談・記録の重要性
寄与分の主張は、一人で抱え込むと証拠不足や説明不足で不利になりがちです。だからこそ、早めに専門家へ相談することが重要です。
さらに、介護が始まった段階から「記録を残す」という意識を持つことが、将来の相続を左右します。相続のときに慌てて集めるのではなく、日々の積み重ねが一番の備えになるのです。
めーぷる岡山中央店でも、「介護をしたのに相続で報われなかった」という声を何度も耳にします。だからこそ、今のうちに準備することが“未来の安心”につながるのです。
関連記事:遺品整理を安く済ませるための完全ガイド