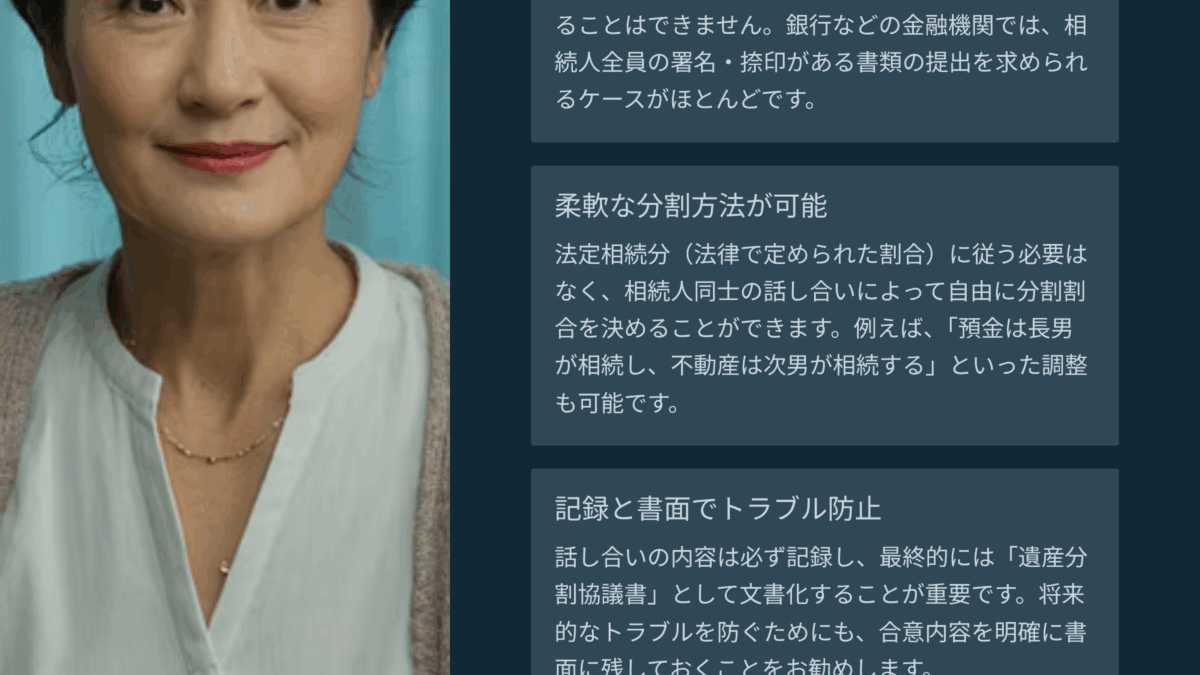親の預金を兄弟でどう分ければいいのか…悩んでいませんか?トラブルを防ぎ、納得して進めるための実務的なルールと注意点をわかりやすく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
預金を兄弟で分けるときの基本ルールとは
「親の預金、兄弟でどう分けたらいいのか分からない」「揉めたくないけど、何を基準にすればいいの?」
そんな風に感じている方へ。
私たち“めーぷる岡山中央店”では、遺産分割にまつわるお悩み相談を日々お受けしています。
この記事では、相続預金を兄弟で分ける際のルールと注意点について、実務に即して整理していきますね。
相続における法定相続分──預金にも適用される基本の考え方
相続が発生すると、まず登場するのが「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」という考え方です。
これは法律で定められた遺産の分け方の目安で、遺言がない場合に基準とされます。預金ももちろん、この対象になります。
たとえば親が亡くなって、相続人が子ども3人だった場合、法定相続分はそれぞれ1/3ずつです。
ただし、法定相続分は「自動的に振り込まれる金額」ではありません。
あくまでこれは“目安”であり、実際にどう分けるかは、次に紹介する「遺産分割協議」で決まるのです。
✅ 法定相続分はスタート地点。実際の配分は“話し合い次第”という点に注意しましょう。
遺産分割協議の必要性とその進め方
預金を兄弟で分けるには、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)という手続きが必要です。
これは、相続人全員で「どう分けるか」を話し合い、合意に至るためのもの。
協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、それをもとに金融機関に払い戻しを申請します。
話し合いでは、以下のような観点がよく出てきます。
- 誰が親の介護をしていたか
- 生前に贈与(援助)を受けた兄弟がいるか
- 他の遺産とのバランスをどう取るか
預金は現金なので「平等に分けやすい」と思われがちですが、実際には感情や背景の差が表れやすい資産です。
全員が納得できるよう、お互いの状況に耳を傾ける姿勢がとても大切です。
✅ 協議は“法律”より“納得感”が重要。焦らず、1つ1つ確認しながら進めましょう。
関連記事:遺品整理費用節約の秘訣とおすすめ手順
兄弟間での預金分割の具体的パターンとポイント
「できるだけ揉めたくない」「でも、うちの場合はどう分けるのが一番いいんだろう」
そんな声を、相続の現場ではよく耳にします。
預金の分け方にはいくつかの典型的なパターンがあり、それぞれにメリット・注意点があります。
ここでは、兄弟間での現実的な分け方とその工夫について、具体例を交えてご紹介します。
預金額を単純に按分する方法とその注意点
いちばんシンプルなのが、預金を法定相続分で按分(あんぶん)する方法です。
たとえば預金が900万円で、相続人が3人なら、それぞれ300万円ずつに分ける形です。
✅この方法のメリット:
- 手続きが早く終わる
- 分かりやすく、公平感がある
ただし、以下のような場面では注意が必要です。
- 他に遺産がある場合(不動産や車など)
- 一部の相続人が生前に資金援助を受けていた場合
- 誰かが預金を先に引き出していた場合
こうした背景があると、「同じ金額なのに不公平」と感じるきっかけになります。
単純按分をする場合でも、まずは全体像を共有してから進めるのがおすすめです。
特定口座優先での分け方(例:亡くなった親が指定口座を持つケース)
複数の銀行口座がある場合、「この口座は◯◯が管理していた」「年金はこの口座に入っていた」など、性格の違いが出てきます。
そこでよくあるのが、特定の口座単位で分ける方法です。
たとえば、
- 長男はゆうちょの口座(200万円)
- 次男は地銀の口座(300万円)
- 三男はネット銀行の口座(400万円)
というように分けていきます。
この方法のメリットは、
- 各自が手続きを個別に進めやすい
- 銀行とのやりとりが簡略化できる
ただし、金額に偏りが出やすいため、差額の調整や話し合いが必要になります。
不公平感を減らすために、他の財産や介護の実績などを加味して話すのがポイントです。
一部現金・一部口座の組み合わせで配慮するポイント
預金が複数口座にまたがっていたり、相続人の希望がバラバラな場合は、「一部は現金」「一部は特定口座」というように組み合わせて分けるケースもあります。
たとえば、
- Aさん:定期預金口座+20万円の現金
- Bさん:普通預金口座+10万円の現金
- Cさん:現金90万円のみ
このように柔軟に設計することで、「自分に合った形で受け取りたい」という要望にも応えやすくなります。
✅この方法で大切なのは:
- 相手の事情(遠方に住んでいる、手続きが苦手など)に配慮すること
- 預金の内訳や差額調整を紙に書き出して、全員で確認すること
感情的な対立を避けるためには、「誰が得したか」ではなく「みんなが納得できるか」を重視する視点が欠かせません。
関連記事:岡山市のおすすめ遺品整理業者まとめ
預金分割時にありがちなトラブルとその防止策
「きちんと話し合ったつもりだったのに、あとから揉めてしまった…」
相続でよくあるトラブルのひとつが、預金の分け方に関する食い違いです。
特に兄弟間では、感情や過去の経緯が絡み合うため、想像以上に複雑になりがち。
この章では、よくある3つのトラブル事例と、その防ぎ方を整理してお伝えします。
口座の把握漏れによる争いを未然に防ぐ方法
「そんな口座があるなんて聞いていない」
相続の場でこうした発言が出ると、場の空気が一気に緊張します。
これは、被相続人(亡くなった方)の銀行口座を正確に把握していなかったことが原因です。
特にネット銀行や地方の信用金庫など、家族に知られていない口座が見落とされることがよくあります。
✅未然に防ぐためのチェックポイント:
- 通帳やキャッシュカードの保管場所を丁寧に確認する
- 郵便物(取引明細や通知)を1〜2か月ほど保管・精査する
- 相続人全員で情報を共有しながら調査を進める
また、銀行に「残高証明書」や「取引履歴」を請求するのも有効です。
とくに不正な引き出しが疑われる場合は、記録をもとに確認していきましょう。
贈与税や贈与扱いにならないための配慮点
「相続なのに、贈与税がかかったらどうしよう」
こんな不安も、実際の現場ではよく聞かれます。
基本的に、相続によって預金を受け取る場合は「贈与税」ではなく「相続税」の対象です。
ですが、協議前に一部の相続人が勝手に引き出した場合や、本来の取り分以上に受け取った場合は、贈与とみなされるリスクも出てきます。
✅贈与扱いを避けるためのポイント:
- 協議が整う前に預金を引き出さない(緊急時は記録を残す)
- 金額の偏りがある場合は、他の遺産で調整するか、文書で同意を取る
- 相続税申告時には、税理士などの専門家に確認する
「よかれと思って渡した」ことが、後で問題になることも。
親切心こそ、慎重に行動することが大切です。
手続きの記録化と合意書の重要性
「言った・言わない」で揉めないために、
話し合いの記録を“形”にして残すことが最も確実な予防策です。
具体的には、
- 遺産分割協議書の作成(全員の署名・押印付き)
- メールやLINEなどでのやりとりも保存しておく
- 書面で金額や内訳を共有し、誤解が生まれないようにする
協議書があることで、後から何か問題が起きたときにも「こう決めていた」という証拠になります。
銀行や法務局への手続きにも必須なので、早めに準備しておくのが安心です。
✅「話す」だけでなく「書く」。それが信頼関係を守る一歩です。
兄弟間での公平感を保つための実務的な工夫
「不満はないけど、なんとなくモヤモヤが残る」
預金の分け方でよくあるのが、数字の公平さと心の納得感が一致しないケースです。
兄弟それぞれの立場や感じ方に配慮することが、トラブルを避ける鍵になります。
ここでは、実際に私たちの現場でも効果的だった工夫を紹介しますね。
家族会議で共有する情報と配慮すべき心理的側面
相続の前提として、「情報の透明性」は非常に大切です。
どの口座にいくらあるのか、どんな出費があったのか。こうした情報を全員にオープンにするだけで、信頼感はぐっと高まります。
ただ、預金の話になると、「親の介護をした・していない」「あのとき援助をもらった」など、感情面の記憶が出てきやすくなります。
だからこそ、家族会議では数字と一緒に、それぞれの想いや状況にも耳を傾けることが欠かせません。
✅家族会議で心がけたいこと:
- 情報は全員に同時に開示する
- 気持ちのすれ違いには「否定せずに受け止める」姿勢を
- 感情的になりそうなときは、一度時間を置く勇気も大事
相続は、“正解”より“納得感”を目指すべき時間です。
第三者(専門家)を交えた中立的な分割の進め方
「話し合っても平行線になってしまう…」
そんなときこそ、専門家という“第三の視点”が力を発揮します。
たとえば、
- 司法書士や行政書士による遺産分割協議書の作成支援
- 税理士による税金面でのアドバイス
- 相続診断士やファイナンシャルプランナーの中立的な意見
第三者が入ることで、感情ではなく“事実と手続き”をもとに整理ができるため、話し合いもスムーズになります。
また、専門家は「家庭内の事情を知らないからこそ」、偏りなくアドバイスできます。
相談は早ければ早いほど、選択肢も広がりますよ。
✅「話がまとまらない」は、誰のせいでもありません。外の力を借りることも、大切な一歩です。
小口口座や預金額が少額な場合の簡易的対応
もし相続する預金が少額(数万円〜数十万円)で、金融機関も複数にまたがっている場合、
無理に分け合うよりも、1人が代表して受け取る方法が実務的です。
たとえば、
- 銀行の解約手続きは1人が行い
- 現金で他の兄弟に分ける(もちろん協議書は必須)
この方法なら、煩雑な手続きや郵送のやり取りを減らせます。
ただし、「少額だから」「面倒だから」といって口頭だけで済ませるのはNG。
あとでトラブルにならないよう、きちんと合意内容を紙に残しておきましょう。
✅簡易的でも、“丁寧さ”と“記録”は忘れずに。小さな金額ほど気を遣うのが、家族の思いやりです。
預金分割に関するよくある質問Q&A
預金を兄弟で分けるにあたって、具体的な疑問や「これってどうなるの?」という不安を抱える方は少なくありません。
ここでは、実際のご相談でも頻出する3つの質問を取り上げて、できるだけ分かりやすくお答えしていきます。
ちょっとした疑問が、大きな誤解やトラブルの種にならないよう、しっかり押さえておきましょう。
預金を兄弟でどう分けるか、協議しなかった場合はどうなる?
遺産分割協議をせずに、誰かが勝手に預金を引き出した場合──
これは非常に大きなトラブルの火種になります。
法的には、預金も遺産の一部として「相続人全員の共有財産」とみなされます。
したがって、1人だけの判断で動かすことはできません。
協議をしないまま引き出すと、
- 他の相続人から「不当利得(ふとうりとく)」として返還を求められる
- 相続手続きが進まなくなる
- 銀行が払い戻しを拒否するケースも
特に最近は、金融機関も慎重になっており、遺産分割協議書の提出を求められることが増えています。
何よりも大切なのは、「全員の合意」です。
✅協議は「形式」ではなく「信頼」を守るためのプロセス。必ず経てから動きましょう。
片方に多く渡したい場合、贈与か相続かどう判断する?
「長男には多めに渡したい」「次女が親の介護をしてくれたから多くしたい」
そう思う気持ち、よく分かります。実際にそうした調整はよく行われています。
このようなケースでは、「遺産分割協議での合意に基づく」限り、贈与ではなく相続扱いになります。
ただし、以下のような条件が重要です。
- 他の相続人が明確に同意していること(文書で)
- 実際の取り分と、協議書の記載内容が一致していること
- 一部の相続人だけが事前に受け取っていないこと
もし協議書がなく、証拠もない状態で一部に多く渡すと、税務署から「贈与では?」と疑われる可能性も。
その場合、贈与税(最高55%)の対象になるリスクがあります。
✅特別な分け方をしたいときこそ、「きちんと話し合い、書面に残す」ことがポイントです。
預金引き出しのタイミングや相続税申告への影響は?
預金を引き出すタイミングは、相続税の申告と密接に関係しています。
原則として、相続税の申告は「相続開始(=亡くなった日)から10か月以内」に行う必要があります。
このとき、「相続開始時点の預金残高」が基準になります。
注意すべきは、
- 相続前に引き出された分(いわゆる“使途不明金”)
- 相続人が個人的に使用していた預金
- 誰かが勝手に引き出してしまった預金
こうした部分があると、「実際よりも遺産が少ない」と判断され、申告漏れや追徴課税の原因になります。
✅対策としては:
- 通帳の履歴をチェックし、相続開始前後の動きを明確にする
- 不明な引き出しについては、理由をメモや記録に残しておく
- 税理士に相談して、正確な評価額を出す
「いつ引き出したか」が、そのまま税金に直結することもあるので、タイミングには慎重になりましょう。
関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識
##(必要に応じて)まとめ:兄弟で預金を分ける際の実践チェックリスト
相続預金の分割は、単にお金を分けるだけではなく、家族の信頼関係や過去の思い出とも向き合う機会でもあります。
「トラブルなく」「納得して」分けるために、事前に押さえておきたいポイントを実務視点のチェックリストにまとめました。
話し合いの前に、ぜひ一度ご確認ください。
✅ 預金分割のための実践チェックリスト
| チェック項目 | 内容 | メモ欄 |
|---|---|---|
| 預金口座の把握 | すべての金融機関と口座をリストアップ済みか | 例:通帳・キャッシュカード・郵便物など |
| 法定相続人の確認 | 誰が相続人か明確か(戸籍の取り寄せ済み) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要 |
| 相続分の目安共有 | 法定相続分について全員で認識できているか | 例:子ども3人→1/3ずつ |
| 話し合いの記録 | 話し合いの内容をメモ・録音しているか | 協議書作成の準備にもなる |
| 協議書の作成 | 分割方法が合意され、協議書を作成したか | 金融機関への提出書類にもなる |
| 引き出しのルール | 預金の引き出しは協議後に行っているか | 事前に出金するとトラブルのもと |
| 第三者の活用 | 中立的な専門家に相談済みか | 司法書士・税理士・行政書士など |
チェックがすべて埋まっていれば、預金相続の“落とし穴”は回避できています。
反対に、いくつか未確認の項目がある場合は、今のうちに整理しておくのがおすすめです。
「うちは大丈夫」と思っていても、いざというときに一番揉めやすいのが“預金”です。
気になることがあれば、早めに準備・確認しておくと安心ですよ。
関連記事:岡山エリアの遺品整理業者選びに役立つ情報