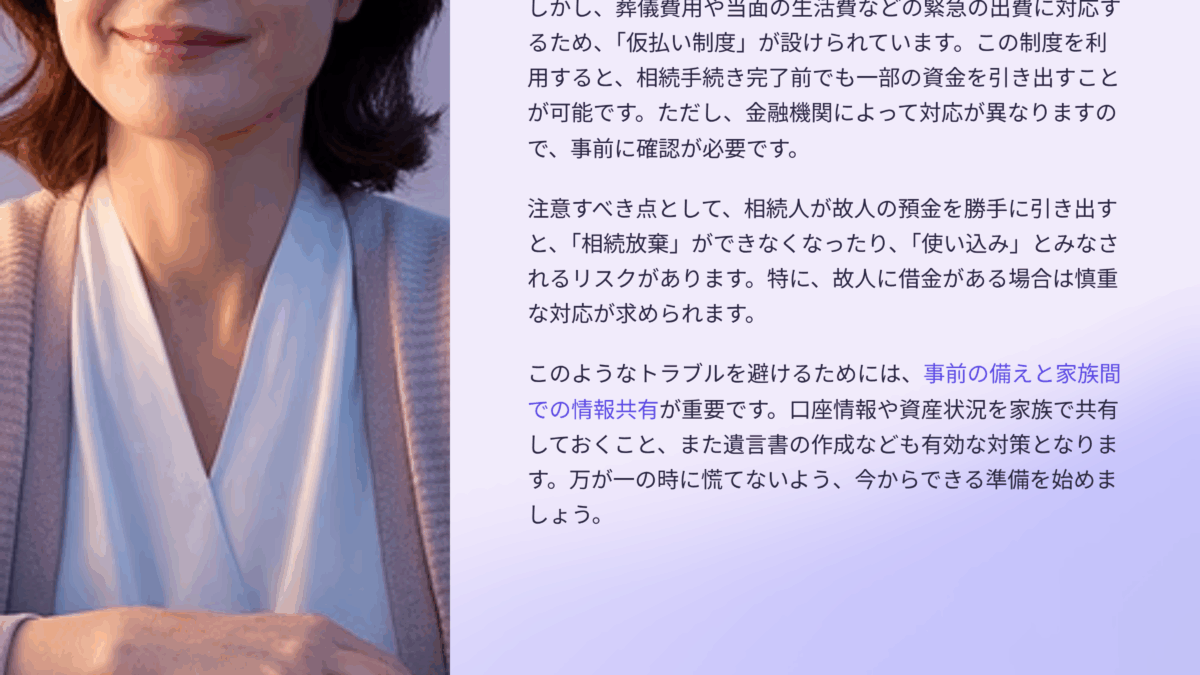口座が凍結されてしまうと、葬儀費用や生活費が出せず慌ててしまう方が少なくありません。
制度を正しく知れば、困ったときにも冷静に対応できます。
目次を見て必要なところから読んでみてください。
相続発生後に口座が凍結されるタイミングとその影響
「亡くなったあと、銀行口座ってどうなるの?」
そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
葬儀や初七日、日常の手続きに追われる中で、「預金が使えない」という現実に直面して慌てるケースは少なくありません。
この記事では、相続発生後に口座が凍結されるタイミングと、その影響についての実務的なポイントを分かりやすく解説します。
凍結が開始されるタイミング(死亡届・銀行への連絡のタイミング)
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の銀行口座は原則として凍結(使用停止)されます。
でも、いつ凍結されるのか——これは多くの方が混乱するポイントです。
✅ 凍結のきっかけとなるのは「銀行への死亡連絡」です。
戸籍が整っていなくても、銀行に「○○が亡くなりました」と連絡すれば、その時点で預金は動かせなくなります。
つまり、死亡届の提出=凍結ではないということ。
ここで注意したいのは、銀行側が被相続人の死亡を「知ってしまった」段階で凍結が行われる点です。
口座を持っていた銀行に直接連絡するほか、新聞のお悔やみ欄やSNSなどで知った場合も、内部で確認が取れ次第、凍結に入ることがあります。
身近な例として、実際にこんな相談がありました。
「父が亡くなった翌日に、長年使っていた口座に葬儀費用を下ろしに行ったら、すでに凍結されていて…。ATMも使えず、本当に焦りました」
こうしたトラブルを防ぐには、「どのタイミングで、どこに、どう伝えるか」を意識する必要があります。
口座凍結後に起こる影響:入出金・振替・自動引落の停止
口座が凍結されると、次のようなことが起こります。
✅ 入出金がすべて停止
✅ クレジットカードや公共料金の引き落としもNG
✅ ネットバンキングやATMも使えない
たとえば、携帯電話や電気代、保険料の引き落としがストップすると、未払い扱いになってしまう可能性もあります。
一時的に家族が立て替えるなどの対応が必要になるケースも。
また、残された配偶者が同じ口座に生活費をまとめていた場合、急に資金が使えなくなって困ることも少なくありません。
「共働きで生活費は夫の口座から引き落としていたが、亡くなった瞬間に全部止まり、支払いができず慌てた」というお話もありました。
凍結=一時的な資金ストップと理解しておくことが重要です。
では、どう備えればいいのか?
次の一歩として、生活費の分散管理や、別口座への一部移動などの対策が考えられます。
不測の事態に備えるには、家族内での情報共有も欠かせません。
関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方
葬儀費用や生活費に充てたい…凍結口座から引き出せるの?
「凍結された口座にお金はあるのに、葬儀費用や当面の生活費が足りない」
相続手続きが終わるまで、ずっと我慢しないといけないのでしょうか?
そんなときに役立つのが、「仮払い制度」と呼ばれる仕組みです。
この記事では、実際に凍結口座からお金を引き出す方法と、知っておきたい注意点を詳しくお伝えします。
仮払い制度(遺産分割前の預貯金払戻し制度)の概要
凍結された口座からお金を引き出す手段の一つが、「仮払い制度」です。
正式名称は「遺産分割前の預貯金払戻し制度」と言い、2019年の法改正で導入されました。
この制度では、遺産分割が終わる前でも、一定の条件下で預貯金を引き出すことが可能です。
対象となるのは、亡くなった方の口座にある「普通預金」や「定期預金」など。
銀行に申請することで、相続人が自分の法定相続分の範囲内で一定額を受け取ることができます。
たとえば、葬儀費用の支払い、四十九日までの生活費、公共料金の立て替えなど、急を要する支出には非常に助かる制度です。
ただし、相続人のうちの一人だけで申請可能ですが、他の相続人に内緒で使うことはできません。
後々のトラブルを避けるためにも、申請前に家族間でしっかり話し合いましょう。
引き出せる金額と上限(預金残高×1/3×法定相続分、金融機関ごと150万円)
この制度には、明確な上限額のルールがあります。
計算式は以下の通りです。
✅ 引き出せる上限額=口座残高 × 1/3 × 法定相続分
さらに、1つの金融機関ごとに上限150万円までという制限があります。
たとえば、亡くなった方の口座に300万円の預金があった場合で、相続人が2人いるなら:
- 法定相続分は1/2
- 計算式:300万円 × 1/3 × 1/2 = 50万円が上限
たとえ法定相続分が多くても、「1/3ルール」と「150万円上限」のどちらか小さい方が適用されるので注意しましょう。
なお、複数の銀行に口座がある場合は、それぞれの金融機関で別々に上限が設定されます。
必要書類と申請手続きの流れ
実際に引き出すには、各金融機関ごとに指定された手続きが必要です。
一般的な申請の流れと必要書類を、以下にまとめました。
✅ 必要書類(例)
- 被相続人の死亡が確認できる書類(戸籍謄本など)
- 相続人全員が確認できる戸籍関係書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 金融機関所定の払戻請求書
- 残高証明書(必要な場合あり)
✅ 申請の流れ
- 金融機関の窓口または電話で相談
- 必要書類を確認し、準備
- 書類を提出し、審査を経て入金(通常1〜2週間)
申請者1人でできる制度ですが、やはり事前に家族と共有し、書類の整理も丁寧に進めることがトラブル防止のカギです。
「うちはまだ早いかな」と感じている方こそ、元気なうちに話し合っておくことが、後々の負担をぐっと減らしてくれます。
関連記事:岡山市内で評判の良い遺品整理業者一覧
仮払い制度利用時の注意点とリスク
「仮払い制度があるなら、とりあえず引き出せばいいのでは?」
そう思う方もいらっしゃるかもしれません。
でも実は、この制度には思わぬ落とし穴や相続全体に影響するリスクがあるのです。
ここでは、制度を利用する前に知っておくべき注意点を、実務の視点から整理してお伝えします。
引き出した金額は「遺産取得」とみなされるリスク
仮払い制度でお金を引き出すと、その行為自体が「遺産の取得」=財産を受け取ったとみなされる可能性があります。
つまり、もしあとで他の相続人と「遺産分割協議」で話し合いをするとき、
「あなたはもうその分をもらってるから、他はもらえないよね?」と言われることも。
たとえば…
「私は葬儀費用で50万円仮払いしただけなのに、他の相続人から“もうそれで済んだこと”と言われて困ってます」
というようなご相談も、実際に寄せられています。
✅ 仮払いは“仮”のはずでも、実際は“もらったもの”として扱われる可能性がある
だからこそ、使い道が正当なものであることを示す証拠が必要になるのです。
相続放棄や単純承認への影響(使い込みの扱い)
仮払い制度を使ってお金を引き出した場合、相続放棄との関係にも注意が必要です。
相続には、以下の3つの選択肢があります。
- 単純承認(すべての財産を引き継ぐ)
- 限定承認(プラスの財産の範囲で引き継ぐ)
- 相続放棄(まったく引き継がない)
このうち、相続放棄をする予定の人が仮払いでお金を引き出すと、放棄が認められなくなることもあるのです。
なぜなら、すでに財産を使ってしまった=「相続する意思がある」と判断されてしまうから。
これは「単純承認」という扱いに切り替わってしまう可能性があります。
また、正当な理由がなく引き出した場合、他の相続人から「使い込み」だと指摘されるリスクもあるため要注意です。
証拠としての領収書保存・相続人間での説明の重要性
仮払いをめぐるトラブルの多くは、「お金を何に使ったかが不明瞭」なことで生じています。
だからこそ、領収書や支払い明細、通帳の写しなどの証拠をしっかり残しておくことが大切です。
✅ 証拠として保管すべきものの例
- 葬儀会社の請求書と領収書
- 火葬料やお布施の支払い記録
- 引き落とし用に一時立て替えた生活費の明細
- 支払いに使った銀行口座の記録
また、できれば他の相続人に「何にいくら使ったか」を説明し、理解を得ておくことが望ましいです。
特に兄弟姉妹など、もともと距離がある関係性では、事前の共有が信頼関係を保つカギになります。
「揉めないために、証拠を残す」——
これは家族を守る、とても実務的な配慮なんです。
仮払いでは足りない場合や手続きできない場合の選択肢
「仮払い制度では上限があるし、手続きも意外と時間がかかる」
そう感じた方もいるかもしれません。
実際、葬儀や初期費用だけで済まないケースや、家族間の事情で手続きが進まないこともよくあります。
そんなときのために、仮払い制度以外の現実的な対処法を2つご紹介します。
急ぎの遺産分割協議の実施と銀行への提出書類
仮払い制度では足りない、あるいは手続きが進まない場合、最も確実なのは「遺産分割協議」を早めに行うことです。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、正式な合意書(遺産分割協議書)を作ること。
これを銀行に提出すれば、凍結された口座の預金を正式に引き出すことができます。
✅ 必要な書類は以下の通りです:
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(実印を押印したもの)
- 引き出し希望者の本人確認書類
銀行によっては、これに加えて「相続関係説明図(家系図のようなもの)」を求められることもあります。
もちろん、すべての相続人が協力的とは限らず、協議が難航することもあるかもしれません。
でも、最終的に全員の合意が得られれば、預金のすべてを自由に使えるようになります。
現金がすぐに必要な場合は、協議を「先に済ませる」という選択肢も視野に入れてみてください。
家庭裁判所への仮処分申立て:手続きの流れと現実的な対応時間
「協議が整うまで待てない」「一部の相続人と連絡が取れない」
そんな場合には、家庭裁判所に仮処分の申立てを行う方法もあります。
これは、特定の目的(葬儀費用や急な生活資金など)のために、一時的に預金を動かせるよう裁判所に許可を求める手続きです。
✅ 仮処分申立ての流れ:
- 家庭裁判所に申立書を提出(申立人は相続人)
- 裁判所が審査(必要に応じて事情聴取)
- 許可が出れば、金融機関に対して仮処分命令が発行
- 銀行の手続きにより引き出しが可能に
ただし、申立てから実際の引き出しまでに2〜4週間程度かかるのが一般的です。
また、書類の作成や事情説明に手間がかかるため、司法書士や弁護士など専門家のサポートがあると安心です。
この方法は、「緊急性が高く、かつ他の手段が使えない」ケースに向いています。
誰かが反対している場合でも、中立な第三者(裁判所)が判断してくれるため、公平性を保ちつつ、必要なお金を確保できる可能性があります。
✅ポイントまとめ:
| 対応策 | 特徴 | 所要時間 | 必要な協力 |
|---|---|---|---|
| 仮払い制度 | 少額なら迅速対応可 | 1〜2週間 | 単独申請OK(書類整備要) |
| 遺産分割協議 | 正式な相続処理が可能 | 数日〜数週間 | 相続人全員の合意が必要 |
| 仮処分申立て | 裁判所の許可で一時的に引き出し可能 | 2〜4週間 | 書類整備・理由の説明が必要 |
それぞれの方法にメリット・デメリットがあります。
状況や家族構成によって「最適な選択」は変わってきますので、迷ったら早めに専門家へ相談することも一つの手段です。
関連記事:遺品整理費用節約の秘訣とおすすめ手順
相続手続きが完了した後の預金引き出し
「遺産分割も終わったし、ようやく預金を引き出せる」
そう思っていても、いざ銀行に行くと「書類が足りません」と言われるケースが意外と多いのです。
この章では、相続手続きが完了した後の正しい引き出し手順と、必要書類についての実務的なポイントをわかりやすくご説明します。
遺産分割協議書または遺言書がある場合の正規引き出しプロセス
相続手続きが完了し、誰がどの財産を相続するかが確定すると、凍結されていた口座から正式に預金を引き出す手続きが可能になります。
その際、銀行が求めるのは、次のいずれかです。
- 遺産分割協議書:相続人全員の署名・実印入りの書類
- 公正証書遺言や自筆証書遺言(家庭裁判所の検認済み)
これらの書類が整っていれば、預金を取得する相続人が単独で引き出しの手続きができます。
つまり、「正式に決まった分配方法に沿って、相続人本人が引き出す」ことになるわけですね。
銀行側は、法的に問題がないことを確認してからでないと動けないため、書類の整備は慎重に行う必要があります。
手続きに時間をかけないためにも、分割協議や遺言の内容は、明確かつ具体的に記されていることが大切です。
手続きに必要な書類(戸籍謄本・印鑑証明・相続関係図など)
預金を正式に引き出すには、次のような書類を準備する必要があります。
✅ 必要書類一覧(一般的なケース)
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| 戸籍謄本(被相続人) | 出生から死亡までのつながりが分かるもの |
| 戸籍謄本(相続人) | 全員分が必要。続柄を証明するため |
| 印鑑証明書(相続人全員分) | 遺産分割協議書に実印を押している場合 |
| 遺産分割協議書または遺言書 | 相続人間での合意内容を記載 |
| 相続関係説明図 | 家族構成を図で示す資料(手書き可) |
| 被相続人の預金通帳・届出印 | 金融機関によっては印鑑が必要な場合も |
| 申請者の本人確認書類 | 運転免許証などの公的身分証明書 |
これらの書類を一式揃えて、金融機関の窓口に提出すれば、審査を経て預金の払戻しが実行されます。
手続きには通常1〜2週間前後かかることが多く、混雑状況や書類の不備によってはさらに時間がかかることもあります。
「あと一歩」の段階でつまずかないよう、事前に銀行の公式サイトや窓口で必要書類の最新情報を確認することが大切です。
関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方
事前対策として考えたい選択肢
「凍結されてからでは遅い。何か事前にできることはないの?」
そう感じた方へ。実は、相続発生前に備えておけることは意外と多いのです。
この章では、万が一に備えて“今からできる対策”を2つの視点からご紹介します。
葬儀費用や生活費の確保に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
生前に葬儀費用を準備する方法:生命保険・葬儀保険・互助会・信託
相続が発生した直後、もっとも必要になるのが「すぐ使える現金」です。
でも、預金は凍結されていてすぐに使えない…というのが現実。
そこで活用したいのが、以下のような生前準備の仕組みです。
✅ 代表的な方法一覧
| 方法 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 生命保険 | 指定した受取人に直接支払われる | 凍結されずにすぐ現金化できる |
| 葬儀保険 | 葬儀費用専用の保険。掛け捨て型が多い | 保険金の使い道が明確。安価なプランも |
| 互助会 | 葬儀会社との事前契約で費用を積み立て | プラン選定や式場予約がスムーズに |
| 家族信託 | 家族に財産管理を託す契約 | 認知症対策にもなり、柔軟な資産活用が可能 |
なかでも生命保険は、死亡後すぐに保険金を受け取れるため、最初の出費に備える手段として非常に優秀です。
受取人が家族であれば、他の相続人の同意を得ずに受け取れるという安心感もあります。
「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」——
そんな思いがある方には、保険や信託を組み合わせた事前対策をおすすめしています。
凍結リスク回避に向けた家族との事前共有・カード管理の心得
もう一つ大切なのが、家族内での情報共有とお金の使い方の工夫です。
相続人が複数いる場合、「誰がどの口座のことを知っているのか」が不明だと、
いざという時にお金を引き出せず、葬儀費用が立てられない・生活費が止まるという状況に陥ります。
✅ 事前に共有しておきたいポイント
- どの銀行にどの名義の口座があるか
- キャッシュカードの保管場所
- 通帳と印鑑がどこにあるか
- パスワードやネットバンキング情報の管理方法
特に最近は、ネットバンキングだけで管理している高齢者も増えており、「家族が一切把握していない」ということも少なくありません。
さらに、キャッシュカードを使った引き出しも、死亡後に行うと“使い込み”と疑われる可能性があるため注意が必要です。
だからこそ、生前のうちに“信頼できる家族に情報を共有しておく”ことが、最もシンプルで有効な対策になります。
また、いざという時のために、生活費だけは別の口座で管理しておく、共同名義口座を検討するなどの手段もあります。
「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに、できることから始めてみてください。
ほんの少しの備えが、あとから大きな安心につながります。
関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識
実務的な流れとまとめ:凍結口座の扱いと支出対応の優先順
ここまで読んで、「何をどこから始めればいいか分からなくなった…」という方もいらっしゃるかもしれません。
最後に、凍結口座の扱いに関する全体の流れを整理し、支出対応の優先順位を実務的な視点でまとめておきます。
迷ったときに立ち戻れるよう、確認用の早見表と相談先の情報も一緒にご紹介しますね。
項目ごとの対応早見表(緊急度・手続き時間・利用制度)
まずは、よくある支出項目と、それに対する現実的な対処方法を整理しておきましょう。
✅ 凍結口座に関する支出対応早見表
| 支出内容 | 緊急度 | 利用可能な制度・手段 | 手続き時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 葬儀費用 | 高 | 仮払い制度、生命保険 | 1〜2週間程度 |
| 生活費 | 高 | 別口座の準備、仮払い制度 | 即日〜1週間程度 |
| 医療費の清算 | 中 | 仮払い制度、立替払い | 1〜2週間程度 |
| 遺品整理・清掃費用 | 中 | 遺産分割後に清算 | 数週間〜1ヶ月 |
| 不動産や車の名義変更費用 | 低 | 遺産分割後の正式手続き | 1ヶ月以上 |
| 事業用資金 | 高 | 家庭裁判所への仮処分申立て | 2〜4週間程度 |
支出内容によって、「今すぐに動くべきこと」と「後からでも間に合うこと」が分かれます。
最初の混乱期には、葬儀や生活に関わる出費を優先し、それ以外は手続きと相談を並行して進めるのが現実的です。
相談のおすすめ先(税理士・司法書士・弁護士など)
相続や預金の引き出しについては、自分ひとりで対応しようとせず、早めに専門家に相談することが何よりも大切です。
それぞれの専門家の役割を、以下に整理しました。
✅ 相続手続きにおける主な相談先と得意分野
| 専門家 | 得意な分野 | 相談タイミング |
|---|---|---|
| 税理士 | 相続税の計算、節税対策 | 遺産評価・税務申告前 |
| 司法書士 | 登記、遺産分割協議書の作成 | 不動産・預金の名義変更時 |
| 弁護士 | 相続トラブル対応、調停 | 相続人間で争いがあるとき |
| 行政書士 | 書類作成、遺言・公正証書サポート | 相続開始前から可 |
「誰に何を聞けばいいか分からない…」というときは、まず司法書士や行政書士への相談から始めるとハードルが低く、動きやすくなります。
また、地元の銀行や市役所、包括支援センターでも初期的な相談窓口を設けていることがあります。
「ちょっと聞いてみたい」という段階でも、遠慮せず一歩踏み出してみてください。
私たち“めーぷる岡山中央店”でも、初回無料の相談受付を行っております。
「どう進めればいいか分からない」と感じたら、お気軽にお声がけくださいね。