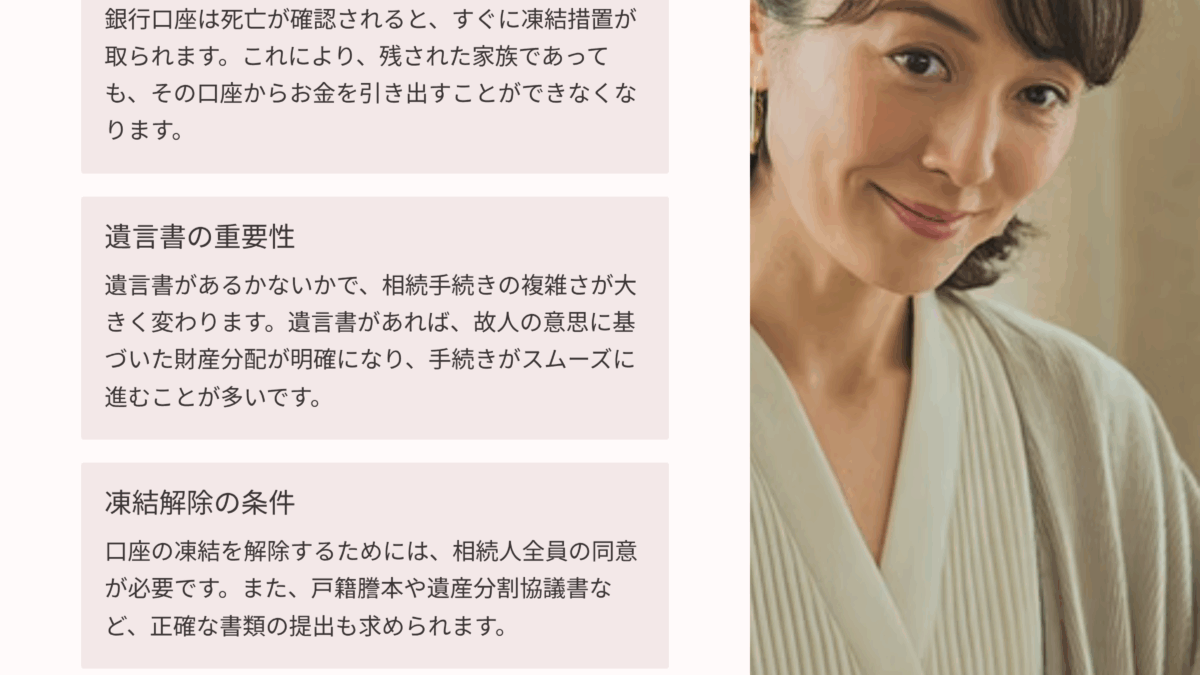親が亡くなったとき、銀行口座はどうなるのか?引き出しは?手続きは?初めての相続に不安を感じている方へ、流れと注意点をやさしく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
親が亡くなったら銀行口座はどうなる?相続開始時に知っておくべき基礎知識
「親が亡くなったとき、銀行口座ってどうなるの?」
そんな疑問を抱いたまま、手続きができずに時間だけが過ぎてしまっている方も多いのではないでしょうか。
実際、口座が使えなくなるタイミングや、何を準備すればいいかを知らないまま動くと、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
ここでは、相続が始まった瞬間からの銀行口座の扱いについて、わかりやすく整理してお伝えしますね。
相続開始のタイミングと銀行口座の扱いの基本
相続は、「人が亡くなった瞬間」から始まります。
これは法律上の話で、死亡届を出していなくても、亡くなった事実があればその時点で相続は発生します。
そして、親が亡くなったことが銀行に知られると、その時点で銀行口座は凍結されます。
「まだ手続きしてないのに、もう使えなくなるの?」と驚かれる方も多いですが、これは遺産分割前に勝手な引き出しを防ぐための措置なんです。
✅ 銀行が死亡の事実を知る主なきっかけ
- 家族からの届け出
- 死亡届の提出による自治体からの通知
- 他の相続人からの連絡
なお、銀行に知られなければ口座はそのままの状態ですが、故人の口座から勝手に引き出すことは「遺産の使い込み」とみなされる恐れがあるので注意が必要です。
遺言書があるかどうか、相続人が誰かが確定していないうちは、口座を動かせないのが原則。
まずは、亡くなった事実をしっかり受け止めつつ、冷静に相続人同士で話し合いを始めることが大切です。
✅最初にできること
- 通帳・キャッシュカードを保管しておく
- 口座からの自動引き落としを確認する(家賃や公共料金など)
- 金融機関に連絡する前に、相続人全員で情報を共有しておく
口座が「凍結」される仕組みとその意味
「口座が凍結される」とは、預金の引き出しや振込など、あらゆる取引ができなくなる状態のことをいいます。
銀行が故人の死亡を把握した瞬間から、機械的に処理が始まるため、例外は基本的にありません。
✅ 凍結されるとどうなる?
| 内容 | 凍結前 | 凍結後 |
|---|---|---|
| ATM利用 | 可能 | 不可 |
| 振込・引き落とし | 通常通り | 全て停止 |
| ローン返済 | 自動引落不可 | 別途手続きが必要 |
| 公共料金の支払い | 口座から引落可能 | 基本的に停止 |
たとえば、電気代や携帯代などの引き落としが止まってしまうと、支払いの遅延に繋がるケースもあります。
このため、凍結前に生活費など必要な資金を移しておくという対応が現実的にとられることもありますが、これはあくまで相続人全員の同意があることが前提です。
とはいえ、「そんなこと、親が亡くなった直後に冷静に判断できるわけない…」と思われるのも当然。
だからこそ、事前に話し合っておくことが、残された家族の助けになるんです。
✅ 次にできること
- 銀行口座の名義人が亡くなった場合のルールを家族で共有しておく
- 「いざというとき」に慌てないため、必要な書類や手続きを前もって整理しておく
- 司法書士や専門家に早めに相談することで、スムーズな対応が可能になります
銀行口座が凍結される対象と時期
「すべての銀行口座が一斉に凍結されるわけではない」
これ、実はあまり知られていないポイントです。
「うちは関係ない」「家族名義だから大丈夫」と思っていたら、思わぬところで資金が動かせなくなり、支払いが滞る…そんな事態も現実に起きています。
ここでは、どの口座が凍結の対象になるのか、そして実際に凍結されるタイミングについて整理してお伝えします。
どのような口座が凍結対象になるのか
凍結されるのは、亡くなった方が名義人となっている銀行口座すべてです。
個人口座はもちろん、名義が個人のものであれば定期預金、普通預金、貯蓄預金、当座預金、外貨預金など、種類を問わず凍結されます。
✅ 凍結対象の例
- 親名義の普通預金口座
- 親の定期預金や満期保険金の受取口座
- 自営業で使用していた屋号付きの個人口座
- クレジットカードの引き落とし口座
- 公共料金の自動引き落とし口座
一方、共同名義口座(※日本ではほとんど存在しない)や、法人名義の口座は原則として凍結対象にはなりません。
ただし、たとえば「実際は親が使っていたが、口座名義は子のもの」といったケースでは、使い込みや名義預金として相続税の課税対象になることもあるため、注意が必要です。
このように、「誰の名義か」が凍結の可否を左右します。
「通帳に名前があるだけでは不十分で、実際の使い方が問われる」という点も理解しておきたいところですね。
✅ できること
- 家族名義で使っている口座があれば、誰の財産として扱われるかを明確にしておく
- 名義人が高齢の場合、事前に信頼できる相続人と共有しておく
- 生活費や支払い口座を分けておくと、万一のときに混乱を防げます
凍結の開始タイミングと銀行ごとの対応の違い
「凍結はいつから始まるのか?」というのも、よくある疑問です。
結論から言うと、銀行が名義人の死亡を知った時点で即時凍結されます。
つまり、「亡くなったその日に銀行が知れば、その日のうちに凍結される」ことも十分あり得るというわけです。
✅ 凍結の流れ(一般的な例)
- 相続人が銀行に連絡(死亡届・戸籍などを提出)
- 銀行内部で確認・審査
- 口座凍結(出金・振込不可)
ただし、銀行によって多少対応に違いがあるのも事実。
一部の金融機関では、死亡届を提出しない限り凍結されないこともありますが、他の相続人が先に届け出てしまえば、そこで止まることになります。
たとえば…
- A銀行:死亡を電話で伝えただけで即凍結
- B信用金庫:書類提出後に正式凍結
- Cネット銀行:オンライン通知のみで即反映
このように対応が異なるため、複数の口座を持っていた場合は、それぞれの銀行ごとに確認することが重要です。
✅ 次にできること
- 銀行ごとの相続窓口を早めに調べておく
- 凍結を避ける目的での「名義変更」はリスクがあるため、安易にしない
- 複数の相続人で連携して、同時に手続きを進めることでトラブルを防げます
関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方
口座凍結中にできること・できないこと
「親の口座が凍結されたら、何もできなくなるの?」
そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実際には、できること・できないことが明確に分かれているため、正しく理解することが大切です。
生活費の確保や緊急対応にも関わる大事な部分なので、ここでは実務目線で整理してお伝えします。
引き出しや振込、公共料金の支払いは可能か?
基本的に、口座が凍結されたあとは、すべての取引ができなくなります。
それまで普通に使えていたATMも、キャッシュカードも、使えなくなるというのが現実です。
✅ 凍結後にできなくなること
- ATMからの現金引き出し
- インターネットバンキングのログイン・操作
- 振込・自動送金
- 公共料金・ローンなどの自動引き落とし
- クレジットカードの決済引き落とし
つまり、「親の口座をそのまま生活費や支払いに使っていた」場合、大きな影響が出る可能性があります。
特に気をつけたいのは、公共料金や家賃などの自動引き落とし。
知らずに滞納してしまうと、信用情報に傷がついたり、契約の継続に影響することもあるため、早めの対応が必要です。
✅ 確認しておくべきチェックポイント
- 故人名義の口座から引き落とされている支払いはあるか
- 子や配偶者の名義に支払いを変更できるか
- 緊急時の支払い手段は他にあるか(現金、他口座など)
生活費の引き出しや緊急時の対応策
「じゃあ、急に現金が必要になったらどうすればいいの?」
という不安に対しては、いくつかの選択肢があります。
まず、基本的には凍結された口座から相続人の判断で自由に引き出すことはできません。
これは「勝手な遺産の処分」とみなされ、後々トラブルの火種になることが多いからです。
ただし、例外的に対応できるケースもあります。
✅ 緊急時の対応方法(例外的に可能な場合)
| 状況 | 対応策 |
|---|---|
| 葬儀費用が必要 | 銀行に「葬儀費用の支払い申請」を行うことで、一部引き出しが認められることがある |
| 遺族の生活費が逼迫 | 相続人全員の同意があれば、仮払い制度を使って一定額の引き出しが可能 |
| 公共料金が滞納 | 利用者変更を行い、別口座からの支払いに切り替える |
「預金の仮払い制度」(※令和元年から施行)は、相続人が銀行に申請し、一定額までの預金を引き出せる制度です。
ただし、すべての銀行が同じように対応しているわけではないため、事前に相談して確認しておくことが重要です。
✅ 次にできること
- 緊急時に備え、口座の仮払い制度について調べておく
- 葬儀費用や初期費用を誰がどう負担するかを家族で話し合っておく
- 相続開始前から、生活費用の備えを別途用意しておくことも大切です
凍結解除のための手続きフロー
「凍結された口座、どうやって解除すればいいの?」
そんな疑問を持ったとき、まず思い浮かぶのは「銀行に行けば何とかなるのでは?」という考えかもしれません。
でも実際は、銀行口座の凍結解除には法的な手続きと正確な書類が必要です。
この章では、遺言書の有無による違いと、具体的な手順について分かりやすく整理してお伝えします。
遺言書がある場合の手続きステップ
まず、有効な遺言書がある場合は、相続手続きが比較的スムーズに進みます。
ただし、遺言書の「形式」によって進め方が変わる点には注意が必要です。
✅ 遺言書の種類と手続きの違い
| 種類 | 特徴 | 凍結解除までの流れ |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が手書きで作成 | 家庭裁判所で「検認」が必要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成・保管 | 検認不要ですぐに使用可 |
たとえば、公正証書遺言がある場合は、相続人単独でも口座の凍結解除が可能です。
内容に「○○銀行の預金を長男に相続させる」など、具体的な記載があれば、銀行側もスムーズに対応できます。
✅ 次にできること
- 遺言書の保管場所を把握しておく(公正証書なら公証役場に記録あり)
- 家族間で遺言の存在を確認し合っておく
- 公正証書遺言を活用することで、将来の相続手続きが大幅に楽になります
遺言書がない場合:相続人全員の同意や調停手続き
一方で、遺言書がない場合は、相続人全員による「遺産分割協議」が必要です。
この協議がまとまって初めて、銀行は預金の払戻しに応じてくれます。
✅ 凍結解除の手順(遺言書なし)
- 相続人全員を確定(戸籍等で確認)
- 遺産分割協議を行い、「誰がどの財産を相続するか」を決定
- 遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印
- 銀行に協議書と必要書類を提出して、預金の引き出し手続きへ
もし、相続人の中に行方不明者がいる、同意が得られないなどの場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
ここで時間がかかると、生活費や支払いの工面が難しくなることもあるため、早めに準備することが大切です。
✅ 次にできること
- 相続人全員が誰かを確認し、連絡を取り合う
- 協議が難しい場合は、早めに専門家に相談
- 調停に移る際も、資料や背景をきちんと整理して臨む
必要書類一覧(死亡届、相続人関係図、戸籍謄本など)
銀行で口座の凍結解除を進めるには、複数の公的書類を正確にそろえる必要があります。
手続きの流れは銀行ごとに多少異なりますが、以下の書類が一般的に求められます。
✅ よく求められる書類一覧
| 書類名 | 内容 | 発行元・注意点 |
|---|---|---|
| 被相続人の死亡届 | 死亡の事実を示す | 市区町村役場(死亡届提出後に除籍謄本として取得可) |
| 戸籍謄本・除籍謄本 | 相続人の確定に必要 | 被相続人の出生から死亡までの一連が必要 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 続柄の確認用 | 全相続人分を取得 |
| 遺産分割協議書 | 誰が預金を相続するか記載 | 全員の署名・実印が必要 |
| 印鑑証明書 | 遺産分割協議書の裏付け | 発行後3か月以内が有効期限の目安 |
| 銀行所定の申請書 | 凍結解除申請用 | 各銀行で用意されている書類 |
このほかにも、口座番号や通帳の原本、キャッシュカード、本人確認書類なども求められる場合があります。
✅ 次にできること
- 事前に各金融機関の「相続専用窓口」に問い合わせて、必要書類を確認しておく
- 書類の取得には時間がかかることもあるので、優先順位を決めて動く
- 書類の準備に不安があれば、行政書士や司法書士に依頼するのも選択肢です
関連記事:遺品整理費用節約の秘訣とおすすめ手順
銀行以外の預金・金融資産への影響
「親の口座が凍結されるのは銀行だけじゃない?」
そう思っている方、実は少なくありません。
でも実際には、証券口座や保険など、銀行以外の金融資産にも相続の影響はしっかり及びます。
この章では、見落としやすい資産の扱いについて、具体的にお伝えしていきますね。
証券口座・投資信託の扱いは?
まず、証券会社にある株式や投資信託などの資産も、相続財産のひとつとして扱われます。
親が亡くなったことを証券会社が知った時点で、証券口座も「凍結」されるのが基本です。
✅ 証券口座の凍結による影響
- 株式や投資信託の「売買」が一切できなくなる
- 配当金や分配金の受け取りも一時的に保留
- 損失が出ても確定申告などの処理は別対応が必要
たとえば、相場が大きく動いたとき、「今すぐ売りたい」と思っても、凍結中は何も手が出せないというのが実情です。
そのため、証券口座を持っているかどうか、事前に家族で共有しておくことがとても大切になります。
凍結解除の手続きも銀行と似ていて、戸籍謄本や相続人全員の同意書、証券会社所定の書類などが必要です。
しかも証券会社によっては、資産の評価額によって手続き方法が異なる場合もあるため、早めの問い合わせをおすすめします。
✅ 次にできること
- 証券会社名や口座番号を家族で共有しておく
- 株式や投信の残高が分かる書類(取引報告書など)を保管
- 相続手続きのための「資産目録」づくりを始めておくと安心です
貯蓄型保険や定期預金の取扱いの違い
一方で、生命保険や定期預金など、いわゆる「預けて増やす資産」についても、それぞれ異なる扱いがあります。
✅ 各金融資産の相続時の扱い
| 資産種類 | 凍結の有無 | 手続き方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定期預金 | 凍結される | 銀行の相続手続きが必要 | 満期日でも自動解約されない場合あり |
| 貯蓄型保険(終身・養老など) | 凍結されない(受取人指定あり) | 受取人が直接請求 | 「受取人」がいる保険は相続財産に含まれない |
| 学資保険・年金保険 | 内容による | 契約者死亡で解約や移行手続きが必要 | 契約形態を確認する必要あり |
特にポイントとなるのが、保険契約の「受取人」が誰かという点です。
たとえば、死亡保険金の受取人が配偶者であれば、その分は相続財産とはみなされず、直接配偶者が受け取ることができます。
これは「生命保険は受取人固有の財産」という法律上の考え方に基づいています。
その一方で、受取人が故人自身だった場合(満期金など)は相続財産に含まれ、相続手続きが必要になるため、契約内容の確認は必須です。
✅ 次にできること
- 保険証券や定期預金の契約書を確認し、保管場所を家族で共有
- 保険の「契約者」「被保険者」「受取人」を明確にしておく
- 不明な場合は、保険会社や銀行に直接確認し、リスト化しておく
関連記事:岡山市のおすすめ遺品整理業者まとめ
よくあるトラブルとその回避方法
「手続きがスムーズに進めば…」そう思っていても、現実には相続にまつわるトラブルが起こるケースは少なくありません。
特に銀行口座の凍結解除や預金の分配をめぐる争いは、家族間の信頼関係にヒビを入れてしまうことも。
この章では、実際によくあるトラブルの事例と、その回避策を事前に知っておくことで、冷静に対応できるヒントをお伝えします。
相続人間のトラブル例と事前対処法
「自分の兄弟とは仲が良いから大丈夫」
そう信じていた方ほど、“お金の問題”で関係が悪化する現実を受け止められずに戸惑ってしまうことがあります。
✅ よくあるトラブル例
- 1人の相続人が、口座凍結前に勝手に預金を引き出していた
- 遺産分割協議書への署名を拒否し、手続きがストップ
- 同居していた子が「自分が一番世話した」と主張して全額を求める
- 相続人が遠方にいて連絡が取れず、話し合いが進まない
こうしたトラブルの多くは、情報の共有不足と手続きへの無理解から生まれます。
「なんとなく」で進めるのではなく、事前に家族で確認し合うことが、最大の防止策になります。
✅ トラブルを避けるためにできること
- 口座残高や金融資産を家族で共有しておく
- 相続人全員で集まり、初期の段階で方針を話し合う
- 内容が不明瞭な出金履歴などは、記録として保管しておく
- 感情的な対立を避けるため、第三者(司法書士など)に仲介を依頼する
「お金がからむと、誰でも冷静ではいられなくなる」
そんな前提で、あらかじめ準備しておくことが、家族関係を守ることにもつながります。
銀行が問い合わせてくる典型的なケースと対応ポイント
銀行もまた、相続手続きにおいては“中立的な第三者”として動いています。
そのため、相続人や提出書類に疑問点があると、確認のための問い合わせが入ることがあります。
✅ 銀行からの問い合わせで多いケース
- 戸籍の記載に不備がある(例:抜けている期間がある)
- 協議書の記載内容があいまいで、分配対象が不明
- 印鑑証明の有効期限が過ぎている
- 「相続人代表者」とされている人が、書類上の根拠を提示できない
- 複数の銀行で手続きがずれている(情報の整合性がとれない)
こうした連絡が入ると、手続きが一時中断してしまうことが多く、対応に時間がかかってしまうことも。
だからこそ、事前の準備と“確認済み書類”の整理が重要になります。
✅ 問い合わせをスムーズに処理するためのポイント
- 戸籍や印鑑証明は最新のものを用意し、発行日を控えておく
- 「相続人関係図」を手書きでもよいので作成し、共有しておく
- 銀行ごとの申請書類は事前に取り寄せ、必要事項をメモしておく
- 手続き中は、代表者1名が窓口になると混乱を防げます
また、書類の読み方や書き方に不安がある場合は、金融機関の相続相談窓口や、行政書士に事前に確認してもらうのも効果的です。
関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方
相続手続きの効率化に役立つ実用ツール・専門家の活用
「相続って、こんなに面倒なの?」
そう感じる方が多いのは当然です。
銀行だけでなく、役所、法務局、税務署と、やること・出す書類がとにかく多い…。
ここでは、相続の煩雑な手続きを少しでも効率化するための実用的なツールや、専門家の活用方法についてご紹介します。
銀行手続きをスムーズにするためのチェックリスト
銀行口座の凍結解除には、ひとつでも不備があると、手続きが止まってしまうという特徴があります。
だからこそ、必要書類を一覧化し、漏れなく準備することが成功のカギになります。
✅ 相続銀行手続き チェックリスト(基本編)
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 遺言書(ある場合)または遺産分割協議書
- 協議書に記載された各相続人の署名・実印押印
- 銀行所定の「預金等相続手続き依頼書」
- 通帳・キャッシュカードなどの原本
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
さらに、以下のような「自分用リスト」を作成しておくと便利です。
✅ マイ手続き管理シート(作成例)
| 銀行名 | 支店名 | 口座番号 | 手続き進捗 | 担当者名(わかれば) |
|---|---|---|---|---|
| ○○銀行 | 岡山支店 | 普通1234567 | 書類提出済み | 田中さん(電話対応) |
| △△信用金庫 | 中央支店 | 定期8765432 | 書類準備中 | 未確認 |
こうしておけば、複数の金融機関とのやりとりが同時進行でも、頭の中が整理されます。
✅ 次にできること
- 書類はデジタルでスキャンしておくと再提出時に便利
- 1つの「まとめファイル」を作って、進捗ごとに書類を管理
- 銀行ごとに手続き方法が異なるため、個別に問い合わせておく
専門家(司法書士・税理士・行政書士)に依頼するメリット
「全部自分たちでやるのは不安」「書類を見るだけで頭が痛い」
そんなときは、相続に詳しい専門家に相談・依頼することが、結果的に効率的で安心です。
✅ それぞれの専門家の役割と得意分野
| 専門家 | 得意分野 | 依頼するメリット |
|---|---|---|
| 司法書士 | 不動産の名義変更、戸籍の収集 | 法務局での相続登記をスムーズに進められる |
| 税理士 | 相続税申告、財産評価 | 相続税の節税対策や申告ミスの回避 |
| 行政書士 | 書類作成、相続人調査 | 協議書の作成や銀行提出書類の整備が得意 |
たとえば、不動産が絡む場合は司法書士の力を借りた方が安心ですし、相続税がかかりそうなときは税理士のサポートが不可欠です。
また、初回相談が無料の事務所も多いので、「今の状況で何をすべきか」だけでも確認する価値は十分にあります。
✅ 次にできること
- 地元で相続に強い専門家を調べて、比較検討しておく
- 家族の資産や書類を整理したうえで、相談の準備をしておく
- 手続きに関わる「時間と労力」をお金で買うという考え方も選択肢の一つです
関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識
注意したい税務・費用のポイント
「預金に税金がかかるって、本当?」
そう驚かれる方も少なくありません。
実は、銀行預金も相続税の対象になる財産のひとつ。また、相続手続きには見落としがちな実費も発生します。
この章では、預金にかかる相続税の仕組みと、実際にかかる費用の目安について、具体的にお伝えします。
相続税の対象となる預金額と非課税枠
相続税は、「一定以上の財産を相続した場合」に発生する税金です。
預金はもちろん、現金、不動産、株式、車などすべての財産が対象になります。
✅ 相続税がかかるかどうかの判断基準
相続税の課税対象かどうかは、「基礎控除額」と呼ばれる非課税枠を超えるかどうかで決まります。
基礎控除の計算式
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、相続人が子ども2人であれば
→ 3,000万円+(600万円×2)= 4,200万円までが非課税となります。
つまり、遺産総額が4,200万円を超えない場合、相続税は発生しません。
ただし、預金だけでなく、土地・建物・生命保険金・死亡退職金なども含まれるため、「思ったより金額が多かった」というケースもあります。
✅ 相続税の対象となる預金とは?
- 普通預金・定期預金
- 外貨預金
- 死亡日までの利息を含めた全額
- 凍結されているかどうかは関係なし
相続税の申告が必要な場合、原則として10か月以内に手続きを行わなければなりません。
✅ 次にできること
- おおよその財産額を一覧にして、基礎控除と比較してみる
- 相続税の対象になるもの・ならないものを区別する
- 不安な場合は、税理士に簡易なシミュレーションだけでも依頼しておく
手続きにかかる費用・実費の概算
相続手続きは“無料”でできるわけではありません。
戸籍の取り寄せから、印鑑証明、各種証明書類、郵送費用、そして専門家への依頼料まで、地味に費用が積み重なります。
✅ 銀行口座凍結解除にかかる実費の目安
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本・除籍謄本 | 1通 450円〜750円 | 死亡から出生まで複数通が必要 |
| 印鑑証明書 | 1通 300円〜400円 | 相続人全員分が必要 |
| 郵送・交通費 | 数百円〜数千円 | 複数の金融機関に提出する場合あり |
| 専門家報酬(行政書士など) | 3万円〜10万円前後 | 書類作成や提出の代行費用 |
| 相続登記(不動産がある場合) | 登録免許税+司法書士報酬 | 不動産評価額の0.4%+報酬数万円〜 |
これに加え、相続税がかかる場合は申告書作成や節税対策のための税理士報酬も必要になります。
相場は10万円〜30万円程度で、財産の内容や複雑さによって変動します。
✅ 覚えておきたいポイント
- 相続人が多いほど、書類作成や費用も増加しやすい
- 郵送や手数料を見越して「相続専用の出費項目」を準備しておくと安心
- 無理にすべて自分で行おうとせず、費用対効果で専門家活用を検討するのも◎
関連記事:岡山で遺品整理を依頼するなら知っておきたい業者情報
Q&A:親の銀行口座に関するよくある質問
「細かいことだけど、誰にも聞けない…」
相続手続きをしていると、そんな疑問が次々に出てきますよね。
ここでは、実際に相談の多い“親の銀行口座に関する素朴な疑問”にお答えします。
ちょっとした知識が、後の大きなトラブルを防いでくれることもあるんです。
亡くなった親のカードや通帳はどうすれば?
まず、通帳やキャッシュカードは勝手に処分してはいけません。
たとえ使えなくなったとしても、銀行手続きでは「原本の提出」が求められる場合が多いため、必ず保管しておきましょう。
✅ 処分前に確認すべきこと
- 口座番号や支店名が分かるか?
- 通帳・カードの名義人と一致しているか?
- 最後の取引履歴に不審な点はないか?
また、インターネットバンキングを利用していた場合、ログイン情報が分からなくなると、資産把握自体が難しくなることも。
紙の書類がない時代だからこそ、メールやパスワード管理アプリなども含めて、故人の情報は丁寧に調べておく必要があります。
✅ 通帳やカードの扱いのポイント
- 銀行手続きが完了するまで原則保管
- 複数口座がある場合は、一覧化しておくと整理がスムーズ
- 使用不能になったあとも、不正利用を疑われないよう慎重に扱う
生活費や家賃の支払いはどうやって継続すれば?
「光熱費や家賃、親の口座から引き落とされていたけど、どうすれば…?」
これは多くのご家族が直面する、切実な悩みのひとつです。
基本的に、口座が凍結されると引き落としも停止します。
そのため、放っておくと公共料金の未納や家賃の滞納につながりかねません。
✅ 対処方法(できるだけ早く手を打つのがコツ)
- 各サービス会社に連絡し、「契約者名義の変更」や「支払方法の変更」を依頼する
- 親と同居していた場合は、家族名義で新たな引き落とし口座を登録
- 賃貸契約が親名義なら、不動産会社に相続の旨を伝えて、契約更新の相談をする
このように、凍結後も支払いが続く契約は「引き継ぐ人が決まるまでの対応」が必要になります。
放置しておくと、信用情報や契約上のトラブルにつながることもあるので、早めに動くことが大切です。
✅ 次にできること
- 「親の引き落としリスト」を作って、支払先を整理する
- できれば、凍結前に名義変更や支払口座変更を準備
- 不明な支払いが多いときは、通帳の履歴から洗い出して対応する
まとめ:銀行口座相続の流れとスムーズな対処のコツ
親の死後、何をどう進めればいいのか分からず、時間だけが過ぎてしまう――
そんな不安の中で最初に直面するのが、銀行口座の凍結とその解除手続きです。
一連の流れを理解しておけば、「知らなかった」「間違えた」と後悔することなく、落ち着いて対応できます。
✅ 銀行口座相続の基本的な流れ
- 親の死亡確認 → 相続の開始
- 銀行への連絡で口座が凍結
- 遺言書の有無を確認(公正証書ならスムーズ)
- 相続人全員の確定と遺産分割協議
- 必要書類を整えて銀行に提出
- 凍結解除 → 遺産の払い戻し・分配へ
この流れの中で特に重要なのは、情報の整理と相続人同士の協力体制です。
たった1人の同意が得られないだけで、手続きが止まるケースもあります。
また、銀行口座以外にも、証券口座・保険・定期預金などさまざまな金融資産に波及するため、「全体像」を早めに把握することが大切です。
✅ スムーズな相続のために意識しておきたいコツ
- 「通帳・カード・パスワード」などの情報は、生前から家族で共有
- 早めに「誰に相談するか」「何を準備するか」を話し合っておく
- 無理にすべて自力で進めようとせず、専門家の力を借りることも選択肢
相続は、感情とお金が複雑に絡む繊細な問題。
だからこそ、安心できる第三者のサポートを得ながら、着実に一歩ずつ進めることが家族全員の負担を軽くする道です。
不安や疑問を抱えたままにせず、「今、何ができるか」を考えて動き始めてみてくださいね。
関連記事:遺品整理を安く済ませるための完全ガイド