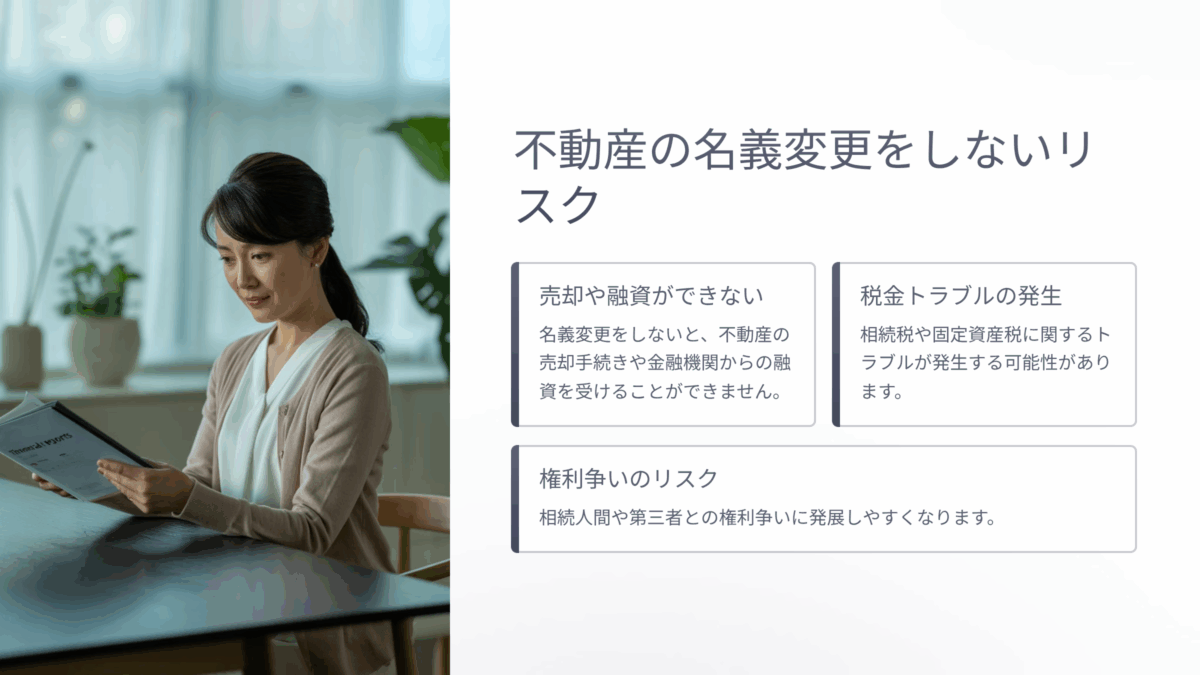「不動産の名義変更、つい後回しにしていませんか?」
相続後に登記を放置すると、税金・売却・家族間トラブルなど多くのリスクが生じます。
目次を見て必要なところから読んでみてください。
相続で不動産の名義変更を後回しにするリスクとは?
「親から不動産を相続したけれど、名義変更ってすぐに必要なの?」
そんな疑問を持ちながら、なんとなく手続きが後回しになっていませんか?
実は、不動産の名義変更をしないまま放置すると、後々取り返しのつかないトラブルに発展することもあります。
ここでは、名義変更を怠ることで生じる具体的なリスクや、その背景にある制度について、わかりやすく解説していきます。
名義変更をしないでおく“根本的な問題点”
相続が発生して不動産を引き継いだ場合、本来であれば「相続登記(=名義変更のこと)」を速やかに行う必要があります。
ですが、手間がかかる、費用が心配、誰がやるか決まっていない…といった理由で、放置されがちなのも事実です。
ただし、ここに大きな落とし穴があります。
名義が亡くなった方のままでは、「その不動産の所有者が不明確」な状態になるため、次のような問題が起こりやすくなります。
✅相続人が増えて、手続きが複雑化する
✅売却や建て替えができない
✅税金の納付や手続きが他の人に及ぶ
✅相続トラブルの火種になりやすい
たとえば「父名義の家を相続して住んでいるけれど、まだ登記は父のまま」というケース。
このまま10年、20年と過ぎていくと、相続人がさらに増え、全員の同意が必要になります。
もし相続人の一人が連絡が取れない、認知症で判断能力がない…となると、その不動産に関するあらゆる手続きがストップしてしまいます。
「まだ問題が起きていないから大丈夫」と思っている間に、問題の根っこは深く広がっていく。
それが、名義変更を後回しにする“根本的なリスク”なのです。
法的効力と登記制度の基本的理解
不動産の「所有者」は、登記簿に名前が記載されている人として法的に扱われます。
たとえ実際に住んでいたり、相続したつもりでいても、登記されていなければ“所有者とは見なされない”というのが日本の法律のルールです。
これを正しく理解しておかないと、「相続は済んだのに、なぜか売れない」「ローンが組めない」「勝手に名義が変わっていた」など、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
さらに、2024年4月からは「相続登記の義務化」が始まり、相続を知ってから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される場合も出てきました。
名義変更とは、ただの事務手続きではありません。
「その不動産を法的に守り、次の世代に安心して引き継ぐための第一歩」です。
わからないこと、不安なことがある方は、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することをおすすめします。
関連記事:遺品整理費用節約の秘訣とおすすめ手順
税務上のトラブル︓名義が変わらないと課税対象や評価に影響?
不動産の名義変更を後回しにすることで、税務上の思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。
たとえば、固定資産税の請求先が誤ったままだったり、相続税の評価にズレが生じて追徴課税を受けたり…。
この章では、そうした「知らなかったでは済まされない」税金面の落とし穴について、実務視点でお伝えします。
固定資産税・都市計画税の誤請求リスク
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点の「登記上の名義人」に対して課税されます。
つまり、相続が発生しても名義変更が済んでいなければ、亡くなった方宛てに税金の請求が届き続けるのです。
この場合、請求書が届いても「今は誰が払うべきか分からない」「名義が変わってないから放置してもいいかも」と判断してしまうケースが少なくありません。
ですが、納税義務は実質的には不動産を使用・管理している相続人にあるとされ、滞納すれば延滞金や督促が発生します。
また、誰がどの割合で相続したかが明確でないまま支払いが続くと、後で「自分はこんなに払ったのに不公平だ」といった相続人同士のトラブルにも発展しかねません。
✅税金の誤請求を防ぐためにも、名義変更は早めに済ませておくことが基本です。
相続税申告とのズレが招く追加税や追徴課税
相続税の申告は、「誰が、どの財産を、どの割合で相続したか」に基づいて計算されます。
しかし、名義変更が行われていない場合、実際の登記情報と相続税申告の内容に食い違いが生じることがあるのです。
たとえば、遺産分割が済んでいないのに形式的に分割した前提で申告してしまうと、後から修正が必要になり、追徴課税の対象になることも。
また、遺産分割協議が長引き、法定相続割合で一旦申告したものの、その後の登記と一致しないといった事例も多く見られます。
このズレを放置してしまうと、税務署から指摘され、ペナルティが発生するリスクも否めません。
✅「名義をどうするか」「分割内容はどうなるか」を早期に整理し、登記と税務の整合性を取ることが、結果的に余計な負担を防ぐ近道です。
不動産が関係する相続では、税務と登記は常にセットで考える必要があります。
複雑に感じる方も多いと思いますが、不安なまま放置せず、一つずつ確認・対応していくことで、トラブルは未然に防げます。
関連記事:岡山エリアの遺品整理業者選びに役立つ情報
売却・担保設定の障害になるケース
「名義変更をしていない不動産でも、住めているし特に困っていないから大丈夫」
そう思っている方は意外と多いのですが、いざ“動かす”段階になってから、大きな壁にぶつかることがあります。
特に、不動産を売却したい、リフォームや事業資金のために担保にしたいと考えた時、登記が変わっていないことで取引ができない・信用が得られないという問題が起きやすいのです。
ここでは、名義変更をしていないことによる現実的な「動かせないリスク」について解説します。
売却時に登記されていないことで起きる売買拒否リスク
不動産を売却するには、売主が「登記簿上の所有者」である必要があります。
つまり、登記が亡くなった親のままでは、売却そのものができないというのが原則です。
実際にあったご相談でも、
「親名義の土地を兄弟で売却して遺産分割にあてようとしたが、登記が変更されておらず、買主から取引を断られた」
というケースがありました。
また、売却にあたっては登記だけでなく、相続人全員の同意や署名が必要になります。
相続人の一人でも所在不明だったり、協力を拒否していたりすると、手続きが前に進まなくなるのです。
✅名義変更は、「いつか売るため」ではなく、「売れる状態を保つため」の備えと考えることが大切です。
ローン借り入れや担保設定の障害と信用問題
不動産を担保にしてローンを組む際も、同じように名義が申込者本人でなければ、担保価値として認められないことがほとんどです。
たとえば、相続した土地を活用して賃貸経営を始めようと思った方が、リフォーム資金を借りようとしたものの、
「名義が亡父のままで借入ができなかった」という事例もありました。
また、相続登記がされていない不動産は、金融機関からの信頼性も下がり、融資審査に悪影響を与えることがあります。
登記は単なる名義の問題ではなく、その不動産の“法的な整備状態”を示す情報として扱われているからです。
✅「まだ使う予定がないから」と油断せず、資産としての価値を活かす準備として、登記の整備は早めに進めておきましょう。
名義変更をしていないことで「売れない」「借りられない」といった機会損失が生じる前に、今できることを一つずつ確認していきたいですね。
相続人間・第三者とのトラブルの具体例
「うちは家族仲もいいし、もめることなんてないと思っていた」
そんな方ほど、名義変更をしないまま年月が過ぎたことで、思わぬ相続トラブルに巻き込まれるケースがあります。
また、不動産の名義が古いまま放置されていると、まったく関係のない“第三者”が権利を主張してくるようなことも。
この章では、よくある相続トラブルの具体例をもとに、名義変更の重要性を掘り下げていきます。
相続人間での所有権争いにつながる可能性
相続人の間で、「誰がどの不動産を相続するのか」が明確でないまま、名義変更をせずに放置してしまうと、
将来的に所有権をめぐって対立が生じる可能性があります。
たとえば――
・長男が実家に住んで固定資産税も払っているが、登記は故人のまま
・他の兄弟姉妹は口頭で了承していたつもりだったが、文書は残っていない
・10年後に遺産分割の不満が噴き出し、「持分があるはずだ」と主張される
こんな事例は、実は少なくありません。
相続人の一人が亡くなると、さらにその配偶者や子どもが「新たな相続人」として加わり、話がさらに複雑になります。
「当事者が増える」=「合意形成が難しくなる」という現実は避けられません。
✅早めの名義変更は、「将来もめないための手続き」として捉えるのが賢明です。
第三者への名義放置による第三者権利主張リスク
相続登記がされずに不動産の名義が放置されていると、登記簿上は「亡くなった方が所有者」のままです。
この状態が長く続くと、まったくの第三者が「自分が相続人だ」と主張してくるケースもあります。
たとえば、
・認知されていなかった非嫡出子が突然登場
・過去に交流のなかった親族が法定相続分を主張
・悪意のある第三者が登記簿を使って不正行為を試みる
登記簿は誰でも閲覧できるため、古い名義のままだと「狙われやすい不動産」としてリスクが高まるのです。
特に都市部や開発予定地にある土地では、実際に地面師(不動産詐欺)の被害にあった例も報告されています。
✅名義を放置することは、“自分の財産を守る意思を示していない”というサインにもなります。
「うちには関係ない」と思っていても、予期せぬタイミングでトラブルの種は芽を出します。
だからこそ、「今は何も起きていないからこそ、動いておく」という心構えが大切です。
関連記事:岡山で遺品整理を依頼するなら知っておきたい業者情報
手続きが遅れた場合の具体的トラブル事例(仮想ケース付き)
名義変更を後回しにしてしまう理由は、人それぞれです。
「急いでやらなくても困らないと思った」「忙しくてつい…」「誰が手続きをするかで話が進まなくて」
けれど、その“つい”が、後になって大きな壁となって立ちはだかることもあります。
ここでは、実際にありそうな2つの仮想ケースを通して、手続きを遅らせた結果、何が起きたのかを具体的に見ていきましょう。
ケース1:相続直後に名義変更しなかったAさんの体験
Aさんは父親が亡くなった後、実家の土地と建物を兄妹3人で相続しました。
しかし、兄妹の話し合いでは「とりあえずAさんが住むなら、それでいいんじゃない?」という曖昧なまま時間が経過。
結果として、名義は亡父のまま、誰も正式に手続きをしない状態が数年続いていました。
ある日、Aさんは実家を売却して新しい住まいへ移ろうと考え、不動産会社に査定を依頼。
ところが、登記を確認した営業担当者からこう言われます。
「名義が亡くなったお父様のままでは、売却できません。まずは相続登記が必要です」
さらに問題だったのは、兄妹の一人がすでに海外へ移住しており、連絡がつきにくい状態だったこと。
結局、売却の話は半年以上停滞し、Aさんは計画していた引っ越しや資金計画を大幅に変更せざるを得ませんでした。
✅「名義変更さえ済ませていれば…」と後悔したAさんのように、生活の節目でつまずかないためにも、登記は先延ばししないことが大切です。
ケース2:十年以上放置してしまったBさんが直面した現実
Bさんのケースでは、相続が発生したのはなんと15年前。
亡母の名義だった自宅について、誰も手続きを行わないまま現在に至っていました。
きっかけは、相続税がかからない範囲だったことや、兄妹間の関係も良好だったことから、「登記しなくても問題ない」と考えていたことです。
ところがある日、Bさんの兄が急逝。
その相続手続きのなかで、兄の子どもたちが「祖母の不動産の相続権」について権利を主張してきたのです。
「えっ、もう話は終わっていたと思っていたのに…」
Bさんにとっては青天の霹靂でした。
名義が祖母のままだったため、法定相続人として、兄の子どもたちにも法的な権利が発生。
再び遺産分割協議を行わなければならず、しかも相手は年齢的にも価値観的にも世代が違い、話し合いは難航。
最終的には弁護士を入れて調整することになり、精神的にも金銭的にも大きな負担となってしまいました。
✅相続登記をしないまま年月が過ぎると、当初の相続人が亡くなることで「新たな相続人」が増えてしまうというリスクがあります。
「そのうちやる」は、手遅れの原因になることを、Bさんの事例は教えてくれます。
このような事例を他人事にせず、“今できることを今のうちに”やっておくことが、将来の安心につながります。
名義変更をしないデメリットまとめ【比較表】
これまでご紹介してきたように、不動産の名義変更を後回しにすると、さまざまなリスクが複雑に絡み合って発生します。
ここで一度、リスクの種類ごとに何が起きるのかを一覧で整理してみましょう。
「何がどの分野に影響するのか」が見えることで、自分に関係のある問題がどこに潜んでいるかがわかりやすくなります。
| リスクの種類 | 起きうる具体的な問題 | 放置による影響 |
|---|---|---|
| 法律・手続き面 | ・売却や担保設定ができない・登記と実態のズレによる権利トラブル | 所有権を証明できず、取引が制限される |
| 税務面 | ・固定資産税の誤請求・相続税申告との不整合による追徴課税 | 税務署からの是正・罰則リスク |
| 家族・相続関係 | ・相続人間の対立や不公平感の発生・次世代で相続人が増えて手続きが複雑化 | 感情的な対立や、手続きに数年かかるケースも |
| 第三者リスク | ・他人による不正登記の可能性・知らない親族からの突然の権利主張 | トラブルの火種となりやすく、対処に手間と費用がかかる |
✅表を見て、「うちはこのケースに当てはまるかも…」と思った方は、できるだけ早めに手続きに着手することをおすすめします。
登記は、“その不動産を守るための盾”のようなもの。
使わない間も、きちんと手入れしておくことで、いざというときに安心して使える状態を保てます。
関連記事:岡山市のおすすめ遺品整理業者まとめ
早めの名義変更を成功させるためのポイント
「名義変更をした方がいいのは分かってるけど、実際にはどう進めたらいいの?」
そんな不安や疑問をお持ちの方に向けて、スムーズに名義変更を進めるための具体的なポイントをお伝えします。
必要書類の準備や専門家への依頼の判断基準を知っておけば、無駄な時間や費用をかけずに済むはずです。
必要書類を整理してスムーズに進めるコツ
不動産の名義変更(=相続登記)には、いくつかの書類を揃える必要があります。
まずは以下のチェックリストをご覧ください。
✅名義変更に必要な主な書類チェックリスト
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書(市町村で取得)
これらを揃えるには、役所や法務局に何度も足を運ぶ必要がある場合があります。
特に戸籍は「本籍地」ごとに取得する必要があるため、事前にリストアップして無駄のない動線で集めることがカギです。
また、手続きの途中で「誰が窓口になるか」で混乱しがちなので、相続人間で一人代表を決めておくと、進行が格段にスムーズになります。
行政書士や司法書士を活用する判断基準と注意点
名義変更は自分でもできますが、書類のミスや手続きの不備があると、再提出や手続きのやり直しが必要になることも。
そこで頼りになるのが、行政書士や司法書士などの専門家です。
✅こんな方は専門家に依頼を検討すると安心
- 相続人が遠方にいて協力が取りづらい
- 書類が多くて手続きに不安がある
- 時間的に自分で動くのが難しい
- 相続人同士での調整に中立な立場の人が必要
行政書士は「書類作成」や「相談窓口」として力になってくれますが、登記申請そのものは司法書士の専門領域です。
依頼する際は、自分がどこまでを任せたいか明確にしておくことがポイントになります。
費用は数万円〜十数万円と事案により幅がありますが、時間と手間を買う“保険”と考えれば決して高くはありません。
✅「最初の一歩が分からない」ときほど、早めの相談が後悔を防ぎます。
安心して相続を完了させるためにも、自分たちに合った方法で確実に手続きを進めていきましょう。
関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方
よくある質問Q&A
名義変更について調べていると、「実際どうなの?」「これって大丈夫なの?」といった素朴だけど重要な疑問が出てきます。
ここでは、めーぷる岡山中央店に実際に寄せられることの多い質問から、特に多くの方がつまずきやすいポイントをQ&A形式でまとめました。
名義変更せずに誰が固定資産税を支払うのか?
固定資産税は、登記上の所有者=亡くなった方に対して課税されますが、実際に納付するのは、その不動産を使用・管理している人になります。
つまり、名義変更をしていなくても、
- 実家に住み続けている相続人
- 管理を担当している家族
- 地代収入を受け取っている人
などが「納税義務者」とみなされ、事実上、請求書が届いた人が支払うことになるのが現状です。
ただしこれには落とし穴もあります。
名義を変更していないままだと、後になって「自分は支払っていただけで所有者ではない」といったトラブルの火種にもなりかねません。
また、支払いの記録が相続割合に影響する可能性もあるため、支払履歴を明確に残しておくことが大切です。
✅「払っている=所有者」とは限らないことを、知っておくことが肝心です。
名義変更の期限や法的なタイムリミットはあるのか?
これまでは、不動産の名義変更(相続登記)に法的な期限はありませんでした。
そのため、多くの人が「急がなくてもいい」と思って放置してしまっていたのが実情です。
しかし、2024年4月の法改正により、ついに状況が変わりました。
相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があると定められたのです。
これにより、「あとでいいや」が通用しない時代に突入したと言えるでしょう。
さらに、名義変更が遅れることで手続きが複雑になる、他の相続人に迷惑がかかる…といった実務面のデメリットもあります。
✅名義変更には「義務」としての期限も、「実務」としてのタイムリミットもある、と認識しておくことが重要です。
「急ぐ必要あるの?」と感じている方こそ、今こそが一番スムーズに動けるタイミングかもしれません。
関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識
まとめ 早めの名義変更で未来のトラブルを防ごう
不動産の名義変更は、相続のなかでもつい後回しにされやすい手続きです。
しかし放置すればするほど、法的・税務的なトラブル、家族間の対立、第三者からの権利主張など、思いがけない問題に発展するリスクが高まります。
今回ご紹介した内容を振り返ってみると――
✅ 売却や活用ができなくなる
✅ 相続人が増えて話し合いが複雑化する
✅ 税務上のミスで追加課税される
✅ 期限を超えて過料が科される可能性も
など、名義を変えていないことが未来の選択肢を狭めてしまうことがわかります。
「今はまだ大丈夫」と感じている方こそ、“まだ何も起きていない今”が動きやすいタイミングです。
相続された不動産がある方は、ぜひ一度、名義の状況を確認し、必要に応じて専門家に相談してみてください。
不安や疑問は、一歩踏み出すことで必ず小さくなっていきます。
あなたとご家族の大切な資産を守るために、できることから始めていきましょう。
関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方