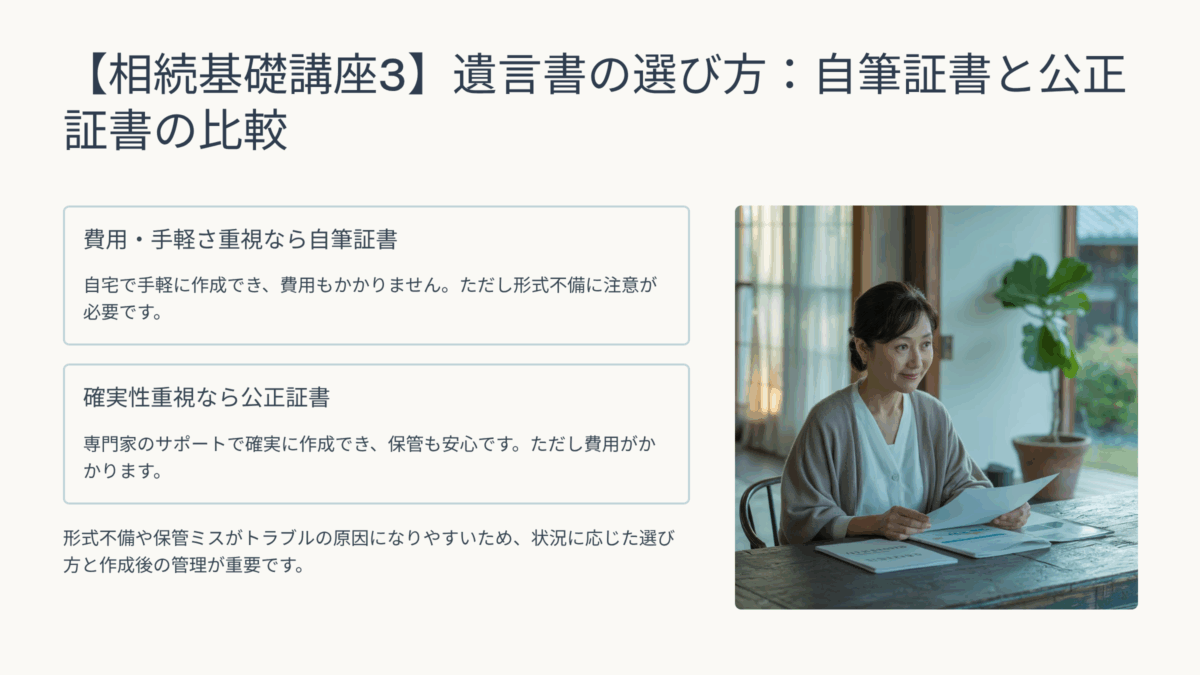遺言書を残すなら「自筆」と「公正証書」、どちらを選べばいい?それぞれの違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
自筆証書遺言と公正証書遺言、何が違う?基礎から理解する
「遺言書を残したほうがいいのは分かってるけど…どの方式を選ぶべき?」
そんな風に感じている方へ。
私たち“めーぷる岡山中央店”では、そうした悩みを抱える方の“最初の一歩”を一緒に整理することから始めています。
この記事では、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いを、実務的な視点でやさしく解説します。メリット・デメリットや手続きの違いを知ることで、納得のいく選択ができるようになりますよ。
自筆証書遺言とは何か|定義と成立要件
「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」とは、その名のとおり、遺言者本人が全文を自分の手で書く遺言書のことです。
紙とペンさえあればいつでも作成でき、費用もかからないのが大きな特徴です。
✅成立要件としては、以下のポイントが大切です:
- 遺言者が全文を自書(※一部ワープロ可:財産目録のみ)
- 作成日付と氏名を記入
- 押印(認印でもOK)
法的には有効でも、形式の不備で「無効になるリスク」も少なくありません。
実際、「親が遺言書を残していたけど、日付がなかったために争いになった」という相談も珍しくないんです。
自筆だからこそ、手軽だけど慎重さが求められる。これが自筆証書遺言の本質かもしれません。
【できること】
形式的なミスを防ぐためには、事前にひな形を確認したり、専門家のチェックを受けることをおすすめします。
公正証書遺言とは何か|仕組みと法的効力
「きちんと遺言を残したい。でも、自分で書くのは不安…」
そんな方に選ばれているのが公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)です。
これは、公証人(こうしょうにん)という法律の専門家に内容を伝え、正式な形で作成してもらう遺言書。証人2人の立会いが必要になりますが、そのぶん法的な効力や安全性は圧倒的です。
✅特徴としては:
- 自分で書かなくてもOK(口頭で伝えるだけでも作成可能)
- 公証役場で原本を保管してもらえる
- 検認(家庭裁判所での確認手続き)が不要
特に、家族間でトラブルの火種がありそうな場合や、相続財産が複雑な場合は、公正証書遺言が有効な選択肢になります。
【できること】
まずは近くの公証役場に問い合わせて、必要な書類や手続きを確認しておくとスムーズです。
作成にかかる手続きや費用の比較
「手軽に済ませたい」「でも将来のトラブルは避けたい」
そう思ったとき、気になるのがそれぞれの手続きと費用感の違い。以下に簡単にまとめてみました。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が全文を手書き | 公証人が作成(口述でOK) |
| 費用 | ほぼ0円(保管制度利用で3900円) | 数万円〜数十万円(財産額により変動) |
| 証人の有無 | 不要 | 2人必要(身内不可) |
| 保管方法 | 自宅または法務局 | 公証役場が原本を保管 |
| 検認の必要 | 必要 | 不要 |
| トラブル回避の確実性 | △ 形式不備で無効のリスクあり | ◎ 法的に強く無効リスクが低い |
費用はかかっても、安全性を優先したいなら公正証書遺言。
一方、費用を抑えつつ、簡単に遺言を残したいなら自筆証書遺言。
ご自身やご家族の状況に合わせて選ぶことが大切です。
【次の一歩】
迷ったときは、まず財産の種類や家族構成を整理してみましょう。それだけでも選ぶべき形式が見えてきます。
メリットとデメリットを比べてみよう
「自分に合った遺言の形式って、結局どっち?」
そんな風に迷っている方へ。
ここでは、それぞれの遺言形式にどんなメリットと注意点(デメリット)があるのかを整理してみます。特徴を理解することで、自分に合った選択肢が見えてきますよ。
自筆遺言の主なメリット
✅ 費用がほとんどかからない
自宅にある紙とペンだけで書けるので、思い立った時にすぐ作成できます。
✅ 自分ひとりで作成できる
公証人や証人を必要とせず、誰にも知られずに作成できる点は大きな特徴です。
✅ 内容の自由度が高い
気持ちを込めて細かな想いまで表現しやすく、「自分の言葉で伝えたい」という方に向いています。
たとえば、「長年介護してくれた長女に多めに相続させたい」など、心情を反映させやすいのもポイントです。
【できること】
内容を書いた後は、家庭裁判所の「法務局保管制度」を利用することで紛失リスクを減らせます。
自筆遺言の注意点・リスク
✅ 形式不備で無効になるケースが多い
日付の記載がない、署名が抜けている、第三者の加筆がある…など、細かなミスでも無効になる可能性があります。
✅ 検認手続きが必要
遺言書が見つかっても、家庭裁判所での検認(けんにん:内容の確認手続き)が必要で、相続開始後の手続きが煩雑になります。
✅ 紛失や改ざんのリスクがある
自宅で保管する場合、火事・水害・家族間のトラブルで失われるケースもあります。
形式を守るだけでなく、「内容の正確さ」「保管方法」まで含めて対策する必要があるのが、自筆遺言の弱点とも言えます。
【できること】
可能なら一度専門家に確認してもらうだけでも、トラブルの予防になります。
公正証書遺言の主なメリット
✅ 法律的に最も安全性が高い遺言書
公証人が関与するため、形式不備による無効のリスクがほぼありません。
✅ 原本が公証役場に保管される
紛失や改ざんの心配がなく、相続人が「見つからない」という事態にもなりません。
✅ 検認が不要
家庭裁判所を通さず、すぐに手続きに移れるのも大きなメリットです。
相続人の精神的・時間的な負担が軽減されます。
相続に慣れていないご家族でも、「これがあるなら安心」と思えるのが公正証書遺言の強さです。
【できること】
費用は発生しますが、「大事な家族のために何を残すか」を考える視点で検討してみてください。
公正証書遺言の注意点・デメリット
✅ 作成に費用と手間がかかる
財産の内容や相続人の数によって費用が変動します。
また、事前準備(戸籍・財産一覧・印鑑証明など)も必要です。
✅ 証人2名の立会いが必要
証人には一定の要件があり(推定相続人は不可)、信頼できる第三者を選ぶ必要があります。
✅ 内容の秘密性が低い
証人が立ち会う以上、完全に「内緒」で作成することはできません。
家族間での配慮が求められる場面もあります。
費用と手間がかかる反面、「確実に想いを形にする力」があるのが公正証書遺言です。
【できること】
一度、公証役場で見積もりを取ってみると、具体的なイメージがつきやすくなりますよ。
ケース別に見る、「どちらを選ぶべきか」
「結局、私のケースだとどっちがいいんだろう?」
これが一番多くいただくご相談です。
遺言の形式には、それぞれ向き・不向きがあるからこそ、ご自身やご家族の状況にあわせて考えることが大切です。
ここでは代表的なケースごとに、自筆遺言と公正証書遺言のどちらが適しているかを整理してみました。
自筆遺言が向いているケース
✅ 財産がシンプルで、法定相続人に沿った分配を考えている方
「預貯金だけで不動産もない」「子どもが2人で半々にしたい」など、財産や相続関係が複雑でない場合には、自筆遺言でも十分なケースが多いです。
✅ 費用を抑えて、まずは意志だけでも残しておきたい方
「本格的に準備する前に、自分の考えだけは書いておきたい」
そうした“最初の一歩”として、自筆遺言はとても有効です。
✅ まだ気持ちがまとまらず、何度か書き直す予定がある方
遺言は更新も可能です。気持ちや状況が変わりやすい方には、手軽な自筆遺言が合っています。
✅ 誰にも知られずに準備を進めたい場合
内容を家族や他人に知られずに進められる点も、自筆遺言の強みです。
【できること】
将来的に公正証書遺言へ切り替えるつもりで、まずは自筆で想いを形にしてみるのも選択肢のひとつです。
公正証書遺言を選ぶべきケース
✅ 財産が多い・複雑な相続が想定される方
不動産が複数ある、非同居の家族がいる、前婚の子がいる…こうしたケースでは、後々のトラブル防止のために、公正証書遺言の信頼性が力を発揮します。
✅ 相続トラブルの火種がすでにあると感じる方
たとえば「相続人同士の関係がよくない」「特定の人に多めに残したい」など、揉める要素がある場合は、法的に確実な遺言書が欠かせません。
✅ 身体が不自由で、自筆が難しい方
筆記が困難な場合でも、公証人に口述で伝える方法なら遺言が作れます。
ご本人の意思を尊重しながら、安全に作成できる方法です。
✅ 確実に家族に遺言内容を届けたい方
公正証書遺言なら原本が公証役場に保管されるため、「遺言が見つからなかった」「誰かに隠された」などのトラブルを回避できます。
【できること】
専門家のサポートを受けながら進めることで、書きたい内容をきちんと整理し、トラブルの芽を事前に摘むことが可能になります。
関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方
作成時のポイント|注意すべき実務上のコツ
「いざ作ろうと思ったら、どこでつまずくのか分からない…」
そんな声もよく聞かれます。遺言書は形式や手順を正しく踏まえて初めて、法的に効力を持ちます。
この章では、自筆・公正証書それぞれの作成時に注意したい“実務的なコツ”をまとめました。ちょっとしたポイントを知っておくだけで、失敗を防げますよ。
自筆遺言の作成における書き方の注意点
✅ まず押さえるべきは、「形式」のルール
自筆遺言は、ちょっとしたミスでも無効になるリスクがあるため、基本のルールを丁寧に守ることが何より大切です。
以下に、よくあるミスとその対策をまとめました。
| よくあるミス例 | 避けるためのポイント |
|---|---|
| 日付を「○月吉日」と記載 | 必ず「西暦年月日」で具体的に記入 |
| 押印を忘れる・シャチハタ使用 | 認印でもOKだが、実印が望ましい |
| 署名がフルネームでない | 戸籍上の氏名(漢字・フルネーム)を記入 |
| 財産の記載が曖昧 | 不動産は「登記簿どおり」、預貯金は「支店名・口座番号」も明記 |
✅ 内容にも配慮が必要です
たとえば、「全財産を妻に」だけでは、特定できない場合があります。財産の種類ごとに明確に記載することが大切です。
【できること】
書いたあとは、家族に一言「遺言書を書いた」と伝えておくことで、存在が知られないまま失われるリスクも減らせます。
公正証書遺言の手続き準備と役所・公証人とのやり取り
✅ 準備がすべてを左右します
公正証書遺言は、確実な手続きができる分、事前の準備がやや煩雑。
しかし、順を追って整理すれば、そこまで難しくありません。
✅必要な書類は以下のとおり:
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(推定相続人の確認用)
- 財産に関する資料(登記簿謄本・通帳コピーなど)
- 遺言内容のメモ(誰に、何を、どう分けたいか)
✅ 証人の手配にも注意が必要
証人は2名必要ですが、配偶者や相続人、未成年は不可。
困ったときは、公証役場に紹介してもらうことも可能です。
✅ 公証人とのやり取りの流れ:
- 公証役場へ相談(電話やメールでOK)
- 内容の素案を提出し、調整
- 公証役場にて本人・証人立会いのもと作成・署名
- 完了後、正本・謄本を受け取り、原本は保管される
「時間がかかりそう…」と感じる方もいますが、実際は1ヶ月以内に完了することも多いです。
そのぶん、得られる安心感は大きいですよ。
【できること】
費用が心配な方は、財産の概算をもとに事前に見積もりを取るとよいでしょう。
公証人が出張してくれるサービスもあるので、体が不自由な方でも対応可能です。
関連記事:岡山で遺品整理を依頼するなら知っておきたい業者情報
トラブルを防ぐために知っておきたいこと
「せっかく遺言書を作っても、後で揉めたら意味がないのでは…」
そんな不安を持つ方は多くいらっしゃいます。
実は、遺言書に関するトラブルの多くは「保管方法」「形式の不備」「更新の仕方」など、実務的なところで起きるものなんです。
ここでは、そうした失敗を防ぐために、押さえておきたい基本と注意点をまとめます。
遺言書の保管・検認の違いと注意点
✅ 保管方法で「見つからない」「隠された」のリスクを防ぐ
自筆遺言を自宅に保管する場合、火事・紛失・第三者による改ざんのリスクがあります。
そのため、近年は法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用する方も増えています。
✅ 検認手続きとは?
自筆遺言は、たとえ法的に有効でも、相続手続きの前に家庭裁判所での「検認(けんにん)」が必要です。
これは、遺言の存在と内容を相続人全員で確認する手続きであり、約1ヶ月〜2ヶ月かかることも。
一方、公正証書遺言なら検認不要で、スムーズに相続手続きに入れます。
【できること】
自筆遺言の場合は、保管場所を明確にし、信頼できる家族に伝えておくことが大切です。
また、公的保管制度の活用も検討しましょう。
形式不備や無効のリスク,対策は?
✅ 遺言書は形式重視。1つのミスが命取りに
「全財産を長男に相続させる。山田太郎」
このような遺言、一見問題なさそうに見えますが、日付や押印がなければ無効になる可能性があります。
✅ よくある形式不備の例:
- 日付があいまい(「令和〇年〇月吉日」など)
- 署名がニックネームや名字だけ
- 押印がされていない、印影が不鮮明
- 書き直しで加筆・修正跡がある
✅ 無効対策のポイント:
- 作成前に形式要件をチェックする
- 一度書いたら、コピーして保管用とする
- 書き直す場合は、「新しい日付の遺言書を新たに作成」し、古いものを破棄する
【できること】
不安な場合は、専門家の無料相談やセミナーなどを利用し、作成前に確認するのが確実です。
後で修正したいときの対応方法
✅ 遺言の修正は、書き加えではなく“作り直し”が基本
自筆遺言で「あとから一部だけ直したい」と思っても、二重線を引いて書き直しただけでは無効になる可能性があります。
✅ 修正の基本ルール:
- 自筆遺言の変更には、訂正箇所に署名・押印・訂正印が必要
- それよりも、新しい日付で全文を改めて作成する方が安全
- 公正証書遺言も、内容変更時は「再度作成」扱いになる
✅ 過去の遺言と新しい遺言が矛盾する場合はどうなる?
法的には、日付が新しいものが有効とされます。
ただし、残された遺言が複数あると、解釈をめぐってトラブルになりやすいため、古いものは明確に破棄しておくことが大切です。
【できること】
新しい遺言を作成したら、前のものを手元で破棄するだけでなく、「前の遺言を取り消す」と明記しておくと安心です。
関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識
まとめ|最適な遺言の選び方は?比較早見表付き
「ここまで読んだけど、やっぱり迷う…」
そんな方も大丈夫です。
最後に、自筆証書遺言と公正証書遺言をどう選べばよいのかの“判断基準”と、よくある疑問への回答をまとめました。
ご自身やご家族の状況と照らし合わせて、納得のいく選択に役立ててくださいね。
選ぶ際の判断基準一覧
✅ こんな方には「自筆証書遺言」がおすすめ
- 財産が少なく、複雑な分配を考えていない
- とにかく今すぐ、費用をかけずに意志を残したい
- 家族に知られずに準備したい
- 将来的に内容を何度か変更する予定がある
✅ こんな方には「公正証書遺言」がおすすめ
- 不動産など評価の高い財産がある
- 法定相続分とは異なる分配を考えている
- 相続人同士の関係が微妙でトラブルを避けたい
- 確実に法的効力を持たせたい
比較早見表(まとめ)
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成費用 | ほぼ0円(保管制度で3900円) | 数万円〜(財産額により変動) |
| 作成の手軽さ | ◎ 自宅で簡単に書ける | △ 公証人とのやり取り・証人が必要 |
| 安全性・信頼性 | △ 無効リスクあり/保管は自己責任 | ◎ 公証役場に原本保管/形式不備なし |
| 秘密性 | ◎ 家族に知られず作成可能 | △ 証人が内容を知る場合あり |
| 相続手続きのしやすさ | △ 検認が必要 | ◎ 検認不要で手続きがスムーズ |
【できること】
判断に迷う方は、「どちらが自分の大事にしたい価値観に近いか」で選ぶのもひとつの視点です。
迷ったら、まずは自筆で始めて、のちに公正証書に切り替える方も少なくありません。
初心者向けQ&A(よくある疑問に回答)
Q:そもそも遺言って必要なんですか?
→ はい。遺言がないと、法定相続分での分配になります。気持ちや想いを反映したい場合、遺言は非常に有効です。
Q:夫婦で連名の遺言はできますか?
→ いいえ。遺言は「一人につき一通」が原則です。夫婦でもそれぞれ別に作成する必要があります。
Q:自筆遺言は書き直しできますか?
→ もちろん可能です。ただし、古いものは破棄し、「新しい日付」で作り直すようにしましょう。
Q:費用が心配ですが、無料で相談できますか?
→ はい。公証役場では事前相談を無料で受け付けているところもありますし、市区町村で開催される終活セミナーなども有効です。
【できること】
疑問や不安をそのままにせず、一つずつ解消していくことが大切です。「書くこと」が目的ではなく、「家族に安心を残すこと」が本当のゴールですから。
関連記事:岡山市内で評判の良い遺品整理業者一覧