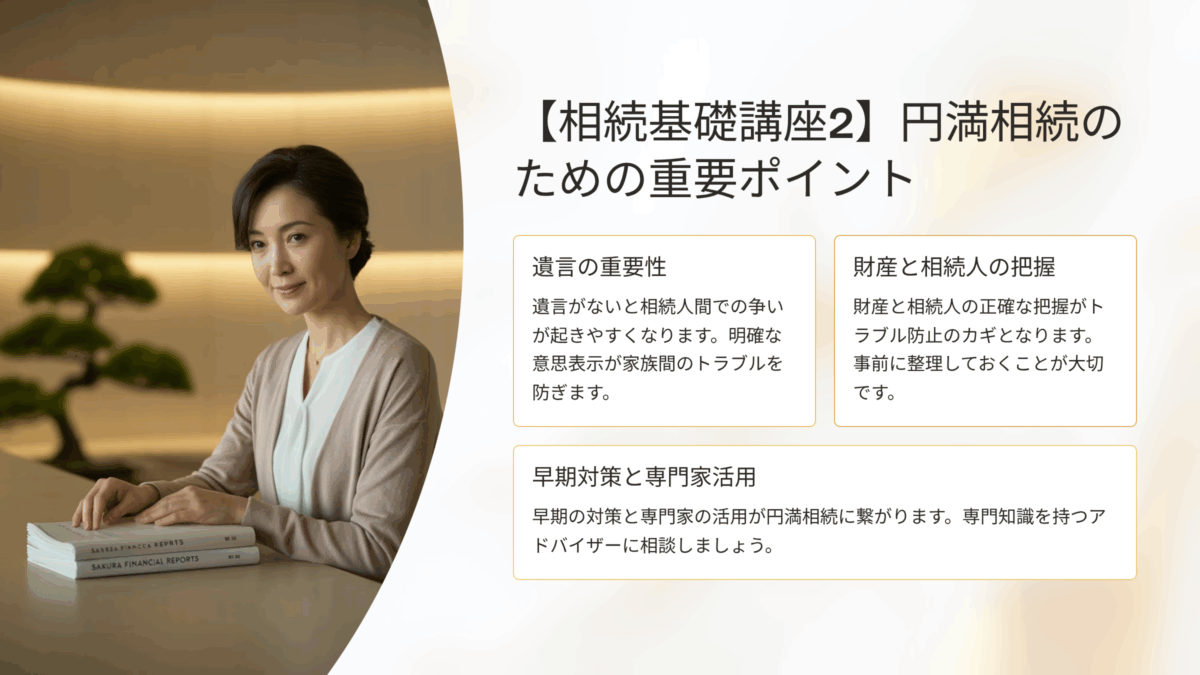遺言がないまま相続を迎えると、家族間で深刻なトラブルに発展することもあります。事前に何を知っておくべきか、目次を見て必要なところから読んでみてください。
遺言がない相続でよくあるトラブルとは?
動画で解説
「遺言があれば、こんなことにはならなかったのに」
私たちの現場でも、そうした声を何度も耳にしてきました。
遺言がない相続では、遺産の分け方を相続人全員で話し合って決めなければなりません。ここで意見がぶつかり、関係性に亀裂が入ってしまうケースは少なくありません。
この記事では、よくある相続トラブルの具体例を通じて、何が起こりやすいのか、なぜそうなるのかを一緒に整理してみましょう。
遺産分割協議がまとまらず揉めるケース
相続では、誰が何をどれだけ受け取るかを話し合う「遺産分割協議」が必要です。
遺言がない場合、この協議がうまくまとまらないことが非常に多いのです。
たとえば、実家の土地をめぐって「住んでいた長男がそのまま住みたい」「次男も平等に財産をもらいたい」と主張がぶつかり、話し合いが平行線になるケースもあります。
話がまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判に発展することも。時間もお金もかかるだけでなく、家族の関係が修復不能になることもあるのです。
✅ できること
・相続が始まったら、早めに話し合いの場を持つ
・第三者(司法書士・行政書士など)を交えて冷静に進める
法定相続人の判断ミスや認定漏れによる対立
相続人は誰か、ということ自体がトラブルの原因になることもあります。
特に注意が必要なのは、婚外子(婚姻関係にない間に生まれた子)や養子縁組した人の存在です。
たとえば「知らない相続人が突然現れて遺産を主張してきた」というケースでは、他の相続人との関係が一気に悪化することも。
相続人の範囲は民法で定められていますが、戸籍を正確にたどらなければ把握は難しいもの。
認定漏れがあると、後から遺産分割協議が無効になるリスクもあるため注意が必要です。
✅ できること
・被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて確認
・専門家に調査を依頼することで漏れを防げる
代償分割の負担での金銭トラブル
「実家を長男が相続する代わりに、他の兄弟へ現金を支払う」
こうした形を代償分割と呼びますが、この負担が思った以上に重くなり、後で揉める原因になることもあります。
たとえば不動産の評価額が3,000万円だとしても、売れるかどうかは別問題。
長男が住宅ローンを抱えながら、兄弟へ代償金を払う約束をしてしまい、支払いが滞ってトラブルに発展するケースも珍しくありません。
✅ できること
・財産評価を専門家に依頼して正確に把握
・代償金の支払い方法(分割・契約書作成)を事前に明確にしておく
遺留分侵害に対する請求トラブル
相続人には、最低限の取り分として「遺留分」という権利が保障されています。
たとえば「全財産を長男に」といった遺言があっても、他の相続人が遺留分を主張すれば、その遺言は一部無効になりうるのです。
問題になるのは、遺留分の計算や金額についての解釈のズレ。
「もっともらえると思っていた」「勝手に処分された」など、感情的な対立に発展しやすい場面でもあります。
✅ できること
・遺留分の請求は原則1年以内。時効に注意
・請求は書面で行うのが基本。証拠を残すことが大切
相続人間の意見不一致と感情的対立
相続の話し合いは、お金の問題であると同時に、家族の歴史や感情が絡む場面でもあります。
「親の介護をしたのに評価されない」「昔から不公平に扱われていた」といった気持ちが表面化し、話がこじれてしまうことも。
中には「話し合いの場にすら出てこない相続人」「連絡がつかず放置されるケース」もあり、協議が前に進まない原因になります。
✅ できること
・話し合いは冷静に、感情より事実を優先
・第三者に進行を依頼することで対立を避けられることも多いです
関連記事:遺品整理の料金目安と失敗しない選び方
なぜトラブルが起こるのか?原因を整理する
「まさか、うちの家族が相続で揉めるなんて…」
実際にご相談を受ける中で、そんな言葉を何度も耳にしてきました。
相続は“お金の問題”だけでなく、“人と人の信頼関係”が深く関わる場面です。
なぜ相続でトラブルが起きてしまうのか? その原因を整理することで、未然に防ぐためのヒントが見えてきます。
遺言がないことで明文化された指示がない不安定さ
まず大前提として、遺言がない状態では、誰が何をどう受け取るかの「明確な指針」が存在しません。
そのため、相続人同士で協議しなければならず、解釈や希望が食い違えばトラブルになります。
たとえば、「この家は長男が継ぐと思っていた」「預貯金は平等に分けたい」といった価値観のズレが出たとき、それを調整する役割を果たす“文書”がないのです。
✅ できること
・将来の争いを避けるには、遺言の作成が最も効果的
・簡単なメモ書きではなく、法的に有効な形式で残すことが大切です
争いの芽:情報共有と透明性の欠如
相続において、「誰がどれだけの財産を知っているか」が不透明な状態は非常に危険です。
「兄が預金の内容を隠していた」「不動産の評価額を故意に低く見積もっていた」といった疑念が、関係悪化の引き金になることも。
特に銀行口座や保険、不動産など、財産の全容が見えにくいと、話し合いが進まなくなってしまいます。
✅ できること
・相続財産をリスト化(遺産目録)し、全員で確認すること
・専門家のサポートで“見える化”するのも一つの手です
相続人間の関係性の変化と不信
親が元気だった頃は良好だった兄弟姉妹の関係が、相続を機に一変することは珍しくありません。
過去の出来事(介護・同居・借金など)が、相続時に再燃し、「不公平だ」と感じる気持ちが表面化するのです。
また、遺言がないことで「親はどう考えていたのか」がわからず、相続人同士の“推測”で話が進むため、感情的な摩擦が起こりやすくなります。
✅ できること
・関係が悪化する前に、親と一緒に将来について話しておく
・相続人全員が納得するプロセスを意識することが重要です
法律知識の不足による判断誤り
相続は、民法や税法など複雑な制度が絡みます。
専門的な知識がないまま、自己判断で動いてしまうと、思わぬ損失やトラブルを招くことになります。
たとえば、「寄与分」や「特別受益」などの法的概念を知らずに主張した結果、他の相続人と対立してしまうケースもあります。
✅ できること
・初期段階で司法書士や弁護士に相談することがトラブル回避の近道
・制度の基礎を知ることで、冷静で公平な判断がしやすくなります
関連記事:遺品整理費用節約の秘訣とおすすめ手順
トラブル回避のためにできること
「争うつもりなんてなかったのに…」
相続の話し合いが思わぬ方向に進んでしまったという声、決して少なくありません。
相続のトラブルは、事前の準備とちょっとした工夫で大きく減らせます。
ここでは、実際の現場で効果的だった対策を中心に、誰でも今日から始められるポイントをご紹介します。
早期からの相続対策と専門家への相談活用
「相続なんてまだ先」と思っているうちに、準備のタイミングを逃してしまう人が本当に多いのです。
でも、相続の話は“元気なうちにこそ”始めるべき。
早い段階から司法書士や税理士、行政書士などの専門家に相談しておけば、無理のない形で財産の整理や意見のすり合わせができます。
✅ ポイント
・事前相談は無料の窓口も多く、ハードルは意外と低い
・「誰に相談すればいいか分からない」場合は、まずは信頼できる地元の窓口から
遺産目録の作成と共有で透明性を高める
財産の全体像が不明確なままだと、不信感が生まれやすくなります。
「何がどれだけあるか」を見える形にすることが、信頼の第一歩です。
そこで役立つのが「遺産目録」。
これは、不動産、預金、株式、保険などすべての財産をリストアップしたものです。
相続人全員で共有すれば、「隠している」「不公平だ」という誤解を避けることができます。
✅ 注意点
・通帳、登記簿などの証拠書類をセットで保管
・金額は「評価額」で記載。できれば専門家に確認してもらいましょう
分割方法の工夫:現物分割・代償分割のメリット・注意点
「家は長男、預金は次男」など、財産をそのままの形で分ける方法を現物分割といいます。
一方で、「不動産をもらう代わりに現金で補填する」形が代償分割です。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に応じた選択が必要になります。
| 分割方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 手続きが比較的簡単 | 不動産の共有名義は後々トラブルになりやすい |
| 代償分割 | 不動産を共有せずに済む | 支払い能力が必要。契約書の作成が重要 |
✅ できること
・分割方法は、税金や将来の売却可能性も考慮する
・感情ではなく「公平性」と「現実的な運用」を基準に話し合う
家族会議の記録化と協議の進行方法
「言った・言わない」がトラブルの火種になるのは、相続でも同じ。
話し合いの内容は議事録として残すことで、後の誤解を避けやすくなります。
また、家族会議の進行には「進行役」がいるとスムーズです。
できれば中立の立場にある第三者(行政書士など)を交えると、感情的になりがちな場面でも冷静な対話が続けやすくなります。
✅ できること
・議事録は手書きでもOK。日付と参加者、内容を記録
・「一度で決めよう」とせず、段階的な話し合いを心がける
遺留分を見据えたバランス調整と納得形成
どんなに家族の合意があっても、遺留分(相続人に保障された最低限の取り分)を侵害すると法的な争いが発生する可能性があります。
たとえば「全財産を長男に」という遺言があったとしても、他の兄弟が遺留分侵害を主張すれば、裁判になることも。
だからこそ、遺留分をふまえた分割案を立てることが重要です。
不動産の価値、税金、生活状況などを含めた“納得のいく説明”が必要になります。
✅ できること
・遺留分の計算は専門家に相談して正確に
・バランスを意識した分配と、誠実な説明が信頼をつくるカギ
関連記事:岡山で遺品整理を依頼するなら知っておきたい業者情報
トラブルが起こってしまったときの対応ステップ
「ここまで揉めるとは思っていなかった…」
相続の話し合いがこじれてしまったとき、多くの方がそう語ります。
でも、行き詰まってしまっても対応のステップを知っていれば、落ち着いて前に進むことができます。
ここでは、実際にトラブルが発生した後の流れと、できることを段階的に整理してお伝えします。
まずは話し合いで解決を試みる
感情的な衝突があったとしても、まずは「相続人全員での話し合い」による解決を目指すのが基本です。
特に初期段階では、感情よりも事実と冷静な対話がカギになります。
たとえば「長女が実家に住んでいるが、他の兄弟には納得感がない」といったケースでも、お互いの立場や事情を丁寧に説明することで、解決に近づけることがあります。
✅ できること
・話し合いの場には第三者を立てると客観性が生まれる
・記録を残しながら、焦らず段階的に進める姿勢が大切
調停や審判の利用:家庭裁判所の制度を知る
話し合いだけでは解決できない場合、家庭裁判所の「調停」や「審判」という制度を活用する選択肢があります。
調停では、中立の立場にある調停委員が間に入り、話し合いを仲介してくれます。
一方で、どうしても合意に至らなかった場合は「審判」となり、裁判所が内容を判断します。
| 制度 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 調停 | 話し合いを仲介 | 感情的対立をやわらげ、柔軟な解決が可能 |
| 審判 | 裁判所が判断 | 最終的な決着がつくが、双方に不満が残る場合も |
✅ できること
・話し合いが難しいと感じたら、早めに調停を検討
・提出書類の準備や説明のサポートには専門家が役立ちます
専門家(弁護士・司法書士)が介入するメリット
「家族のことだから自分たちで何とかしたい」と考える方も多いですが、こじれてしまった後は第三者の冷静な目が必要になります。
特に感情的な争いになっている場合、専門家が入ることでトーンが落ち着き、話が前に進むこともよくあります。
弁護士は代理交渉や調停のサポート、司法書士は登記や財産調査の面で力を発揮します。
✅ できること
・専門家は「誰の味方でもない第三者」としての役割を果たす
・早い段階での相談が、結果的に費用や時間の節約になることも
時効に注意:遺留分請求の期限とは
遺言で不公平な分け方がされた場合などに認められる「遺留分侵害額請求」ですが、これは期間制限(時効)がある点に要注意です。
請求の期限は以下のどちらか早いほうになります:
- 相続開始と侵害を知ってから「1年以内」
- 相続開始から「10年以内」
期限を過ぎると、たとえ正当な権利があっても請求できなくなるため、情報を得たらすぐに動くことが大切です。
✅ できること
・「知らなかった」では済まされないので、早めの確認を
・請求は内容証明など、記録に残る方法で行いましょう
関連記事:遺品整理の節約術と処分方法の選び方
実際のトラブル事例に学ぶ(仮想ケースで整理)
「自分の家では起こらないと思っていた…」
そう話される方ほど、トラブルに直面したときのショックは大きいものです。
でも、事前に他の事例を知っておくことで、回避のヒントや心構えができます。
ここでは、実際のご相談をもとに再構成した仮想ケースを通して、どんな場面で相続がもつれるのかを整理してみましょう。
ケース1:相続人の一人が存在を主張し、協議が頓挫
4人きょうだいだと思っていた家族に、突然「認知された婚外子」を名乗る人物から相続の申し出があったケース。
戸籍をたどってみると、たしかに法的に相続人と認められる立場でした。
結果、既に進めていた遺産分割協議は無効になり、すべてやり直しに。
「知らなかった相続人の存在」が、協議の土台を崩してしまった典型例です。
✅ 学びのポイント
・相続人は「知っている人」だけではない
・戸籍調査は“出生から死亡まで”の通しで確認するのが基本
ケース2:代償分割の返済が困難になり、他の相続人と対立
長男が実家を相続し、代わりに妹2人へ現金で代償金を支払う形で合意。
しかし、住宅ローンとの二重負担で支払いが滞り始めた結果、妹たちとの関係が悪化。
最終的には弁護士を交えて返済スケジュールの見直しが行われましたが、信頼関係には深い溝が残りました。
✅ 学びのポイント
・代償分割は「払えるかどうか」を冷静に試算すること
・合意時に、返済計画と担保条件を明文化しておくと安心
ケース3:遺留分侵害で裁判に発展したケースとその結果
遺言書には「長女に全財産を相続させる」と明記されていたものの、次女が遺留分の侵害を主張して提訴。
調停では折り合わず、家庭裁判所での審判へ。
結果、長女は一部財産の返還を命じられ、関係修復も難しくなってしまいました。
「親がそう決めたのだから大丈夫」と思い込んでいた長女にとっては、想定外の展開だったのです。
✅ 学びのポイント
・遺言があっても、遺留分には配慮が必要
・“全額相続”はトラブルの火種になることも
関連記事:遺品整理費用を抑えるための基礎知識
遺言がない相続トラブルに備えるポイントまとめ
「相続のこと、ちゃんと考えなきゃ」と思ってはいても、日常に追われて後回しにしてしまいがちですよね。
でも、いざというときに「もっと早く動いていれば…」と後悔する方はとても多いのです。
これまでの内容を踏まえて、遺言がない相続でトラブルにならないための基本ポイントを、最後にもう一度整理しておきましょう。
✅ 1. 遺言の作成は、トラブル防止の最も確実な手段
→ 自分の意思を明文化し、相続人間の解釈のズレを防げます
✅ 2. 財産の“見える化”で、不信感を未然に防ぐ
→ 遺産目録の作成・共有が大切
✅ 3. 相続人の確認は「戸籍の取得」から始める
→ 意外な相続人が存在するケースもあります
✅ 4. 分割方法は“納得感”と“現実性”のバランスが大事
→ 感情論に流されず、将来のことまで見据えた話し合いを
✅ 5. 専門家への相談は早めに。相談先に迷ったら、まずは地元の信頼できる窓口へ
→ 一人で抱え込まず、必要なときに必要なサポートを受ける姿勢が大切です
どれも難しいことではありませんが、「何もしないまま時間が過ぎる」ことこそが一番のリスクになります。
いま気になっていることがあれば、小さなことでも、一歩踏み出してみてくださいね。
関連記事:岡山市内で評判の良い遺品整理業者一覧